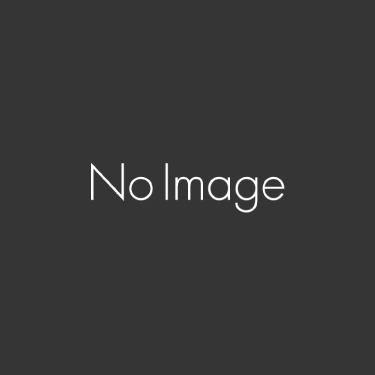死より怖いものはない
「精神的なストレス源は、究極的には人類最大の恐怖、死への恐怖につながっている」(アルベルト・ヴィロルド/心理学者/州立サンフランシスコ大学教授)
どれぐらい怖いのか
哲学者のショーペンハウエルは、「人生は免れることができない死と、死に対する恐怖との合宿所である」と言いましたが、死の恐怖といっても強弱があります。
完全な死の直前である臨終の恐怖が最も強い死の恐怖であり、本物の死の恐怖です。臨終以外でも死の恐怖を感じることができますが、臨終の恐怖とは比較になりません。
しかし、その臨終以外の死の恐怖でさえ、「ハンマーで殴られたような衝撃」と形容するほどの大きな衝撃を受けます。
お笑い芸人の宮迫博之はガンを告げられた時、「目の前が真っ暗になった」といいます。
女優の仁科亜季子もガンの告知を受けた時、「頭をハンマーで打ち砕かれたようでした。自分の身に何が起きたのか理解できませんでした」と振り返っています。
詩人の高見順もガンになった時、「恐ろしいものが背後から迫って来る。夢中で逃げ惑うばかりだ」と死の恐怖を語っています。
岸本英夫も次のように語っています。
「まっくらな大きな暗闇のような死が、その口を大きくあけて迫って来る前に、私はたっていた。私の心は、生への執着ではりさけるようであった」
「死が目の前に迫り、もはやまったく絶望という意識が心を占有したときに、にわかに、心は生命飢餓状態になる。そして生命に対する執着、死に対する恐怖が、筆舌を超えたすさまじさで心の中に起ってくる。このように生命飢餓状態というものは、生存の見通しに対する絶望がなければおこってこないというところに、大きな特徴がある」
「死の恐怖は、人間の生理心理的構造のあらゆる場所に、細胞の1つ1つにまで浸みわたる。生命の執着は、わらの一筋にさえすがって、それによって迫って来る死に抵抗しようとする」
「私は、しばしば、死刑囚のことを思った。死刑囚は死を宣告されて、しかも、独房にいなければならない。何時、刑を執行されるかわからない不安な状態で、死を見つめながら、2年も3年も置かれたら、いったい、どういう精神状態になるであろうか。予告された死の苦しみは、実際に刑が執行される時だけのものでは、断じてない。死の苦しみは、予告されたその刹那から始まる。それ以後は、3日生きればその3日間が苦しみである。10日生きればその10日間が、必死の激しいたたかいである。わずか2週間のたたかいですら、私は相当にまいった。私自身も死刑囚のような気持ちで、本物の死刑囚に深い同情を寄せざるを得なかったのである。そのように、私の内心は、絶え間ない血みどろのたたかいの連続であった」
「レ・ミゼラブル」などで知られるフランスの文豪、ヴィクトル・ユゴーは「死はいかに人を邪悪にすることか」と言い、文学者のラ・ロシュフコーは「死と太陽は直視することは不可能である」と死の恐ろしさを表現しています。
私自身の体験からいっても、死の恐怖を感じれば全身の毛が逆立ち、全身の細胞が「死にたくない」と叫びます。
・死が怖くて自殺する
死が怖くて自殺しようとする人がいます。死ぬことで死の恐怖から解放され楽になれると思ったということです。
たとえばロシアの文豪トルストイは、その1人です。
「この恐怖から逃れんがために、自殺を思ったのである。私は自分を待ちもうけているものに対して恐怖を覚えた。
そして、その恐怖が現在の状態よりも恐ろしいことを知っていたけれど、私は辛抱強く終わりを待っていられなかった。どうせ遅かれ早かれ心臓の脈管が破裂するか、それとも何かほかの器官が破れるかして、万事終わってしまうのだ。こういう理屈が、どんなにもっともらしく思われても、私は辛抱強く終わりを待っていられなかった。暗黒の恐怖はあまりにも大きすぎた。
で、私はピストルの弾丸で、少しも早く、一刻も早く、その恐怖から逃れようと思った。つまり、この感情が何よりも強く、私を自殺へとひいていったのである」(トルストイ)
死そのものが怖い
あらゆる恐怖の根源には死があります。
ウイルスが怖いといっても、ウイルスそのものが怖いのではありません。ウイルスによって死んでしまうことに怖がっているのです。
地震が怖いといっても、地震そのものが怖いのではありません。地震によって死んでしまうことに怖がっているのです。
ガンが怖いといっても、ガンそのものが怖いのではありません。ガンによって死んでしまうことに怖がっているのです。
病気・災害・事件・事故etc.人間には様々な恐怖がありますが、これらはすべて縁(間接原因)にすぎず、あらゆる恐怖の根底には「自分の死」があり「死そのもの」があります。
しかし、人間は「死そのもの」の恐怖や苦しみに目が向かず、ウイルスといった縁にばかり目が向いてしまっています。死はあまりに怖いことであり、解決法もわからないため、こういった縁を退けることにばかり躍起になっているのです。そして、多くの場合、縁を恐怖の根本原因とさえ思っています。
念のために言いますと、「ガンは怖くない」と言う人は少なくないですが、これはガンが治る病気になり死に直結しなくなったことが一因です。これから医学が発達し、「ガンは怖くない」と言う人がさらに増えるでしょうが、死に直結する縁の例として便宜上使っているだけです。ウイルスも地震もすべて同じです。
恐怖の根本原因は「死そのもの」であり自分の心にあるのであって、縁そのものは単なる物質であり生物であり自然現象にすぎません。物質だろうが、生物だろうが、食物だろうが、音楽だろうが、幸せや安心をもたらしてくれるものだろうが、死に直結すれば、どんなものでもすべて恐怖の対象になってしまいます。「死は怖くない」という主張に対しては後で詳しく説明します。
死の恐怖は地獄からくる
人間の死後は必ず地獄です。しかも、地獄の中でも最悪の地獄である無間地獄です。地獄は荒唐無稽な世界ではありません。実在する世界です。この世に地獄と形容できるような苦しみが実在するように、死んだ後にも実在するのです。第1巻では科学的な知見を交えて、このことを説明しました。そして、臨終から地獄の片鱗が見えてきます。
地獄は本当にあるのか?苦しみはどれくらいか?誰が堕ちるのか?
無間地獄
「命終わらんと欲る時、地獄の衆火、一時に倶に至る」(観無量寿経)
(訳:命が終わろうとする時、地獄の猛火が一斉に迫ってくる)
「終りに臨み、罪あひはじめてともに現じて、後に地獄に入りてもろもろの苦にかかる」(往生要集)
(訳:無数の悪業の結果は、臨終に一斉に現れ、地獄に堕ちて無限の苦悩を受ける)
死苦には、死後の地獄の苦しみの1部が含まれているのです。
死の恐怖は地獄からきます。死の恐怖の本質は死後の地獄にあるのであって、「肉体の苦痛」だとか「無になる恐怖」などといったものは地獄の恐怖に比べたら無きに等しいのです。
哲学者の古東哲明は、なぜ死は怖いのか、死の恐怖の原因として、次の2つを挙げています。
肉体の死滅自体への生理的恐怖(死去する際の身体的苦痛など)
自己の存在が消失してしまうことに対する哲学的恐怖(無限にうち続く自己の虚無を想っての恐怖)
このように考える人は多いでしょうが、これは死の恐怖の原因のほんの一部にすぎず、要である圧倒的な地獄に対する恐怖が抜けています。
・自然発火
第1巻では、地獄の火は自身の悪業による消せない火だと説明しましたが、心の問題ですので、何か現象面に現れてもおかしくないでしょう。
たとえば、臨終に、その人が寝ていた形に布団が焼けるといった自然発火現象なるものが報告されていますが、それらの真偽は別として、実際にあり得る現象なのではないでしょうか。自然発火現象の原因として物質的な理由があげられているようですが、そうではなく、根本原因は心(悪業)にあるのではないでしょうか。
・後悔と恐怖に襲われる
臨終は、激しい後悔と恐怖が代わる代わる襲ってくるのです。
「大命将に終わらんとして悔懼交至る」(大無量寿経)
(訳:命が終わろうとする時、後悔と地獄の恐怖が代わる代わるやってくる)
ちょっとやそっとの後悔ではなく筆舌に尽くし難い後悔であるため、血の涙を流して後悔するとも表現されます。
「死は怖くない」は本当か
「死は怖くない」と言う人は多いです。関連して、たとえば「死にたい」「いつ死んでも満足」「死ぬ覚悟はできている」「若くして死ぬのも嫌だけど、あまり長生きし過ぎても嫌だ」「死は怖いと思うけど1番怖いものではない」といったものもあります。
しかし、これらの言動はすべて本心ではありません。このように思ってしまう理由は、簡単に言えば自分の死が遠いからです。平生元気がいい時に想像する死と、実際の自分の死との間には「底なし」といっていいほどの深い深いギャップがあります。
先に説明した通り、死の恐怖といっても強弱があり、強い死の恐怖を感じれば、「どれほど苦しい思いをしようが永遠に生きていたい」という本心が剝き出しになるのです。
フリーアナウンサーの黒木奈々は、ガンになり、今回見つけられなかったら2年後には命はなかったと医師に言われた時の心境をこう語っています。
「怖かった。『死』がこんなに近くにあったなんて考えたこともなかった。私は昔、バカなことを言っていたことがある。
『人生、細く長くは嫌だ。太く、短くでいい』と。その発言、撤回したい。ごめんなさい。『太く短く』なんて嫌。太く、長くがいい」
「何かあると冗談で『あー死にそう』などと言っていた。今は絶対にそんなこと言えないし、自分の周りの人にも絶対に言ってほしくない。今まで当たり前のように使っていた言葉もずっしりと重く、一言一言が胸に響く。もしもいつか子供ができたら、そんなこと絶対に言ってはいけないと教えようと思った」
このように語り、彼女は間もなくして逝きました。
ある芸能人が、初めてバンジージャンプを体験した時を振り返り、「柵の手前は何とでもいえる。柵を超えると恐怖で震えが止まらなくなる」と語っていました。命綱があり助かる保証があるとわかっていても、震えが止まらないほどの恐怖を感じます。まして、命綱がない実際の死は想像を絶する恐怖です。
「死んだら死んだで、その時はその時だ。怖がっても仕方ない」などと高を括っていた人が、いざ死に直面すると怖いと言い出す、こういう事例はゴマンとあります。
いくつか、その人の置かれた状況ごとに分けて紹介しましょう。
・死刑囚
残忍な死刑囚は、一見すると死など恐れていないように見えますが、果たしてどうでしょうか。
・医師
医師は仕事柄、多くの死に直面しているため、一見すると死に対する免疫がありそうに思えますが、果たしてどうでしょうか。
・超心理体験者
臨死体験など、神秘体験や超心理体験と呼ばれる体験をしたという人たちがいます。また、最近では、そういった分野を科学的に研究する人もいます。こういった体験や研究から死が怖くないと主張する人は多いですが、精神科医のエリザベス・キューブラー=ロスのように、実際の死がやってくると一変してしまう例もあります。
・僧侶
悟りを開き、死をも乗り越えた境地にいると自他共に認める仏教徒は少なくないですが、果たしてどうでしょうか。
・成功者
世間的な成功者の中には、「やりたいことは全部やったから、いつ死んでもいい」などと言う人がよくいますが、果たしてどうでしょうか。
・老人
「死は怖くない」と自信たっぷりに言う老人は多くいます。
国の統計によれば、年を取るほど「死は怖くない」と思う人が増えるようです。人生経験が豊富で、統計上は若者よりも死ぬ確率が高い老人がそのように言うのを聞いて、死は怖いものではないと思うようになった人も多いでしょう。果してどうでしょうか。
・兵士
「戦時中の兵士たちは、国のために喜んで死んでいった」という話は多いですが、果たしてどうでしょうか。
・自殺者
自殺する人は、今より死んだほうがマシだと考え自殺を選びます。死にたいという欲求と死の恐怖を天秤にかけた末に、自殺しようと「最後の一歩」を踏み出しているので、一見すると死の恐怖を乗り越えられたように見えますが、果たしてどうでしょうか。
「人間は他人の死ということについては、あくまでもそれを他人事として見る。人の死にざまなどは軽い気持ちで語り、ときとしてはジョークとして話すこともある。だが、いったん、わがこととなったとき、その人は慌てふためき、見栄も外聞もかなぐり捨てて狼狽するものである。その狼狽ぶりは社会的な地位の違い、年齢の違い、財産の違いなどとはまったく無関係に露呈するものである。人間が死に直面したとき、死と向き合ったとき、大会社の社長でも、平社員でもまったくおなじように慌てふためくのだ。『ええっ、ま、まさか、誤診では』」(中岡俊哉)
小説家の大佛次郎は、「死は救いとは言いながら、そうは悟りきれぬものである」と言いました。
ペスタロッチは、「臨終は完成した秋の木の実が成熟して使命を果たした後に、冬の憩いのために地に落ちるような趣はない」と表現しました。
平生元気がいい時に想像する死は、檻の中の虎を眺めるようなものです。「恐ろしい牙だなー、あれに襲われたらひとたまりもないな」などと言いながら、自分に襲い掛かってくることはないから安心して見ていられます。
しかし、実際の死は、山の中で突然虎に出くわすようなものです。心して眺めてなどいられません。
・誰もが死は未経験
世の中に、死を論じる人は多くいます。そういう人の話を聞いて「死は怖いものではない」と思うようになった人も多いでしょう。
しかし、どれほど人生経験が豊富な人であろうが、生きている人間は皆、死は未経験です。未経験者が死を論じていることに注意する必要があります。
「死は怖くない」と言っていた人が、その後どういう心理になっていくのか、最期までよく観察し続けることが大切です。
死にたくないという願い
普段は感じないでしょうが、「生きることができる」ということほど人間にとって幸せなことはありません。
これがいかに強い幸福感であるかは、臨終になればわかります。
底知れない地獄の恐怖の片鱗に触れれば、誰でも「死にたくない、どんなに苦しくても生きていたい」と願うようになるのです。
人間の願いを表現した次のような歌があります。
「いつも三月花の頃 おまえ十八、わしゃ二十 死なぬ子三人みな孝行 使って減らぬ金百両 死んでも命があるように」
順に、次のことがずっと続いてほしいという願いを表しています。
1.暑くも寒くもない3月のような季節
2.初々しくて楽しい夫婦関係
3.親孝行してくれる3人の子供
4.いくら使ってもなくならないお金
5.寿命
最後の願いは、要するに無量寿になりたいという願いですが、人間にとってこれより強い願いはありません。人間には無数の願いがありますが、すべて死の前には空しいのです。
「生命飢餓状態におかれれば、人間は、どうしても、どんな苦しみの下におかれても、生きていたいと思う。人間は、この状態では、いつでも、もっと生きていたいのである。ゴーリキーが描き出すように『いくら苦しくてもよいから、もっと生きたい』というのが、人間の本音である」(岸本英夫)
元ボクシング世界王者の竹原慎二は、膀胱がんになった時の心境を振り返り、「命さえあれば、金なんかいらないと思った。すごかったんですよ本当に、とにかく人生観変わりますよ」と訴えます。
プロレスラーの力道山は「金はいくらでもだすから助けてくれ」と医者に懇願して死んでいきました。
京都大学文学部助教授の高橋和巳は、腸の手術を受けた時の印象を次のように語っています。
「手術台に寝かされて麻酔薬をかがされる瞬間、目隠しの布の隙間から、巨大な蜻蛉の複眼のように光る無影灯を、今は死んでも死に切れぬという痛憤の念でみた。私の確信によれば、死者たちの最後の映像なるものは、立って歩く動物である人間が見落しがちな、地面に打ちのめされて一番低い所から上を見上げる視覚になる。それはなんともいえぬ悲しい視覚であって、何年かの喜怒哀楽、思い定めた志、そして何か素晴らしいことがあるかも知れずないかも知れない未来が、そこで不意に切断される」
こう語り、彼は39歳の若さで死んでいきました。
秦の始皇帝は不死の薬を本気で求めましたが、誰でもこの願いを持っているのです。
「それは、子供の夢にも等しいことであった。所詮、達することのできないあがきであった。しかし、現代人は、あえて、これを嘲笑することができるであろうか。現代人が死に立ち向かった場合に、秦の始皇帝より、少しでも、すぐれた態度を取り得ているということができるであろうか」(岸本英夫)
江戸時代の禅僧、良寛のもとへ、80歳の婆さんが長命の祈祷を頼みに来ました。良寛に手土産を渡し、遠慮がちに用件を伝えると、良寛も素直に応じました。
「ところで婆さん、何歳ぐらいまで生きたいのじゃ」
そこまで考えてこなかった婆さんは、少し考えて100歳と答えました。
「よしわかった。しかし101歳になると迎えにくるがそれでもいいか」
それを聞いて怖くなった婆さんは、今度は150歳と答えました。
「よしわかった。しかし151歳になると迎えにくるがそれでもいいか」
こうして、200歳、300歳と上がっていきました。
しかしきりがないので、良寛は無量寿の祈祷をしてみてはどうかと提案したところ、婆さんはそれをお願いしたといいます。
中国北魏の僧、曇鸞が四論(中論・百論・十二門論・大智度論)の学者だった時のことです。
大集経の注釈を志しますが、大病を患ってしまいます。
(健康でなければ大集経の注釈さえ満足にできない・・・・)
膨大にある経典の1部も満足に学べないことに暗澹たる気持ちになった曇鸞は、不老長寿の法を求めるようになります。
そして、道教の第一人者とされる陶弘景を訪ね、猛烈な修行を始めます。
やがて陶弘景から「もう教えることは何もない」と言われるまでになり、直々に仙経十巻を授かります。
曇鸞は意気揚々と帰りました。
途中、洛陽で、北インドからやってきていた訳経僧の菩提流支三蔵に出会います。
「長生不死の法で、この仙経に勝る法は仏法のなかにはありますまい」
曇鸞が得意げに言うと、菩提流支は地に唾を吐き、こう叱責しました。
「何を血迷っているのか。たとえ寿命が延びたとしても、苦しみ迷いの人生が延びたにすぎず、輪廻することに変わりはない」
そして、仏教にこそ本当の不死の法があると言い、「観無量寿経」を曇鸞に授けます。曇鸞は大いに恥じ入り、仙経を焼き捨てて、深く浄土教に帰依したといいます。
死がある限り幸せになれない
死がある限り、人間は絶対に幸せになれません。
・地獄と隣り合わせ
「板子一枚下は地獄」という諺があります。船乗りの仕事が危険であることのたとえですが、これは漁師だけではありません。人間は常に死と隣り合わせです。つまり、人間は常に地獄と隣り合わせで生きているということです。今日地獄に堕ちるかもしれないのです。朝には健康で元気いっぱいであっても、夜には死んで地獄に堕ちていてもおかしくないという深刻な世界に人間は生きています。まさしく地獄の釜で一休みしている状態です。
・現在は未来に影響を受ける
現在の禍福は、未来の禍福の影響を強く受けます。
未来必ず幸せになることが確定していれば、現在も幸せを感じます。明日、恋人とデートとなれば今から幸せでしょう。粗末な食事でさえ美味しく感じるはずです。
逆に、未来必ず不幸になることが確定していれば、現在も苦しくなります。明日、激しい痛みを伴う手術をすることになっていれば、今から不安で苦しいでしょう。贅沢な食事でさえ不味く感じるはずです。
・人生は常に最悪
この現実を知れば、24時間365日いつどこで何をしようが、常に絶望的であり、常に最悪であり、苦しみしかないというのが人生の実相です。たとえば「楽しいこともある」とか「希望もある」などと思っているのは、まだ人生の見つめ方が甘く、人生に無知で未熟であり、いい加減な状態です。
・祝日はない
誕生日・正月etc.世間では「おめでたい日」といわれる日が色々とありますが、人生の実相がわかれば、まったくめでたくありません。悲しい日です。こういった日がやってきた時は、祝うのではなく、無常を問い詰める機会にするのが正しい受け止め方です。
たとえば、誕生日であれば、1年生きたということは1年死んだということであり、それだけ死に近づいたということです。人間に生まれたことや父母に感謝する縁とするのもいいですが、肝心の無常観が抜けてはなりません。
・信念を貫けない
どんなに強い信念を持っていても、死がある限り貫き通すことができません。たとえば、「これだけは絶対に曲げられない」といった強い正義感を持っていたとしても、本物の死を前にすれば一瞬で折れてしまいます。舌鋒鋭く批判していた人が、自分や家族の身の危険を感じると急に大人しくなったりします。
・何もできない
もっと言えば、本当は死がある限り何もできません。死が遠いから平然と動けているのであって、死の実態が本当にわかれば恐怖で一歩も動くことさえできません。
・弱みを握られている
死後が地獄であれば、死が人間最大の弱点となります。すべての人間は、生まれながらにして死という弱みを握られており、不幸になるようにできているといえます。
・生きていればいいことはあるのか
世間では「今は苦しくても、生きていればいいことがあるよ」といった励ましがよくなされます。しかし、これは正しい善悪がわからない盲目の愛というもので、非常に無責任なものです。
死は信じられない
「死が怖い」と悩んでいた人に対して、「死なんて有り得ない心配せずに、もっと楽しいことを考えよう」とアドバイスしていた人がいました。
古代インドの叙事詩マハーバーラタには、ヤクシャという精霊が賢人ユディシュティラに「最大の脅威は何か」と尋ねる場面があります。いわく、「日々無数の人々が死んでいるのに、私たちはまるで不死であるかのように生きていること」
人間は、自分の死は信じられません。
オルソップに学ぶ死の恐怖と人間の本性
死の恐怖を感じただけでなく、その恐怖が続かない心理も描写している事例を1つ紹介します。
死を生み出す根本原因
こちらで説明したように無明が根本原因です。
死の解決の境地
死の解決がどういう境地であるか簡単に紹介します。
〇破闇満願
破闇満願とは、闇を破って願いを満たすという意味で、闇とは無明の闇を指します。人間には、「死にたくない」という願いをはじめ無数の願いがありますが、どんな願いであっても死の解決をすることですべて満たすことができます。つまり、破闇満願とは、苦悩の根源である無明の闇を破り、死なない身になりたいという人間最大の願いを満たすということです。
「無碍光如来の名号と かの光明智相とは 無明長夜の闇を破し 衆生の志願をみてたまう」(高僧和讃)
(訳:阿弥陀仏の名号と、阿弥陀仏が放つ智慧の光明は、無明長夜の闇を破り、人間最大の願いを満たす)
「大悲の願船に乗じて光明の広海に浮かびぬれば、至徳の風静かに、衆禍の波転ず。すなわち無明の闇を破し、速やかに無量光明土に到りて、大般涅槃を証し、普賢の徳に遵うなり」(教行信証)
(訳:阿弥陀仏の本願は苦悩の海を渡す大きな慈悲の船であり、死の解決をしてこの船に乗れば、光り輝く広大な海に浮かぶことができ、この上ない喜びの風が吹いて、すべての不幸の波は消える。すなわち、無明の闇を破り、速やかに極楽浄土へ至って仏の悟りを開き、すべての生物を救おうとする力を得るのである)
〇すべての恐怖が消える
死の解決をすれば、死の恐怖を始めとした一切の恐怖がなくなります。華厳経には、次の5つの恐怖が消えると説かれています。
「歓喜地を得れば、あらゆる怖畏は、即ち皆遠離す。いわゆる不活の畏、悪名の畏、死の畏、悪道に堕する畏、大衆威徳の畏なり。是くの如き等の一切諸々の畏を離る」(華厳経)
(訳:死の解決をすれば、不活の畏、悪名の畏れ、死の畏れ、悪道に堕する畏れ、大衆威徳の畏れといったものなど、あらゆる恐怖が消える)
・不活の畏れなし
人間には無数の生活上の不安がありますが、それらの不安は死から生じており、死の解決をすることで一切の生活の不安が消え去ります。
・悪名の畏れなし
悪口を言われることへの恐怖がなくなります。
・悪道に堕する畏れなし
悪い世界へ行くのではないかという恐怖がなくなります。
悪いことをしたら悪い結果を受けるというのが悪因悪果の法則ですが、人間は大なり小なり、悪因悪果を理屈抜きで魂が感じています。そして、臨終にはこの上ない恐怖に襲われることになります。死の解決は、「死後は極楽浄土間違いなし」という境地であり、この恐怖は消えます。
・大衆威徳の畏れなし
大衆というのは威圧感がありますが、どれほどの大衆を前にしても恐怖はありません。
・死の畏れなし
人間にとって一番恐ろしい、死の恐怖がなくなります。
そのことがわかる話をいくつか紹介しましょう。
文明六年3月28日に吉崎御坊が火事になったことがありました。蓮如は退避することができましたが、大変なことに気づきます。親鸞真筆の証巻を残してしまったのです。
歯ぎしりする思いで見つめていると、本向坊了顕という人が前に進み出ました。
「私が取ってまいりましょう」
こう言うと了顕は燃え盛る火の中に飛び込んでいきました。やっとのことで証巻を見つけ戻ろうとしますが、火が広がって出られなくなっていました。すると何を思ったのか、了顕はその場にどっかりと座りました。そして腹を十字に掻き切って腸をつかみ出し、証巻をその中へ押し込めうつ伏せになりました。
しばらくして火が収まり、焼け跡を探してみると、焼け焦げた死骸が横たわっていました。了顕でした。仰向けにしてみると、腹の中に証巻がありました。その場にいた人々はその姿を見て泣いたといいます。
この証巻は、今日、「腹籠りの聖教」とか「血染めの聖教」などといわれています。
本光坊了顕の行為は死の解決をしていない人から見れば凄まじいばかりの行為ですが、死の解決をした人の目から見ればごく自然です。「偉い人だ」とは思わず、「幸せな人だ」と思います。
庄松が、たくさんの同行と京都の本山へ参詣した時のことです。帰りの船で播磨灘にかかった時、思いがけない暴風雨となり、船は木の葉の如く浮きつ沈みつ、今や海の藻屑とならんとする勢いでした。日頃の信心はどこへやら、人々は上を下への大混乱となりました。
そんな中で、船底で鼾をあげて寝ている人がいました。庄松でした。
「庄松起きんか!こんなときに何寝てんだ!大胆にもほどがある!」
同行が揺すり起こすと、庄松は眠い目をこすりながら一言、言いました。
「何だ、まだ娑婆か」
「死んで極楽だと思っていたけど、まだ死んでなかったのか」ということですが、これも死の解決の境地がわかるエピソードです。
もう1人紹介しましょう。
〇金剛心
金剛とは仏教用語で、絶対に崩れない、壊れないという意味です。
「信心やぶれず、かたぶかず、みだれぬこと、金剛の如くなるが故に、金剛の信心と言うなり」(唯信鈔文意)
(訳:信心が破れず、傾かず、乱れないこと、金剛のようであるので金剛の信心と言うのである)
ダイヤモンドのことを金剛石といいますが、ダイヤモンドは非常に硬いために、こう名づけられています。
無常の幸福も、一見するとダイヤモンドのようにキラキラ輝いて見えます。だから人間は惹かれてしまいますが、第2巻でも説明したように、実体はすぐ壊れてしまう、いわばガラスのような偽の幸せです。また、無常の幸福を得ることで生まれる自信は、死を始めとした圧倒的な苦しみがやってくるとすべて崩れるため、自惚れであり偽の自信です。それに対して、金剛心は死が来ても崩れません。