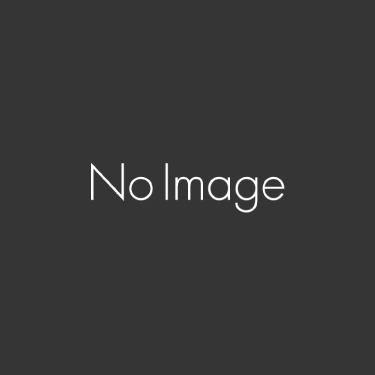「死が怖くない」などと高を括っていた人が、いざ死に直面するとまったく逆の反応を示すことを、こちらで詳しく説明しました。
同じことは戦争で戦う兵士にもいえます。「戦時中の兵士たちは、国のために喜んで死んでいった」という話は多いですが、果たしてどうでしょうか。
巣鴨拘置所の教誨師だった花山信勝は、次のような話をしています。
「私は、死なねばならない境遇に置かれた27人の青年たちに接する機会が与えられた。その語るところは、『戦争のときは、死ぬことを、なんとも思わなかったのですが——』ということに、一致していた。中には、特攻隊を志願した人たちもあれば、しばしば弾丸雨下の死線を越えてきた人たちもある。身命を捧げて一途に必勝へと突進したその当時と、戦敗によって平和を迎え、過ぎし日の責任が問われて死に直面する現在とでは、その心境に大きな相違のあることを、彼ら自身が認めて、告白するのであった。国家全体が異常に興奮した、その大きな、環境の中にあったときの自分の身命に対する考え方と、周囲のすべてがおちついて、平常の状態にかえった現在のそれとの、大きな相違を実証しているのである。それは、戦時中の死はやすく、平時のそれは容易ではないという証左であり、人間は普通の状態にあるときは、決して死を欲するものではないという事実である」
太平洋戦争中に学徒出陣し、特攻隊員になった兄弟の岩井忠正さん(99)と忠熊さん(97)が、早稲田大学で講演した時の話が毎日新聞に載っていました。
「今はそれぞれ東京、滋賀と離れて暮らすが、どうしても若い世代に『最後の言葉』を伝えたいと顔をそろえた。これまでそれぞれ講演する機会はあったが、兄弟そろって話すのは最初で最後かもしれない。2人が伝えたかったメッセージとは——」
「辛くも2人は生き残ったが、多くの若者が特攻隊員として命を散らし、遺書が残されている。
『遺書には勇ましい言葉が書いてある。私は喜んで死ぬ、と書いてあるのを読んで感激する人もいるはずです。だけど、私は、待ってくださいと言いたい』
忠正さんは会場にこう呼びかけた」
「忠正さんは、命を落とした隊員の無念を代弁するように語気を強めて会場に訴えた。
『本当は死にたくない。でも(死ぬのが)嫌なのに殺されたと聞いたら家族も悲しむから、喜んで死んだと思ってもらおうと。もう一つは自分を励まさなきゃやれない。決して犬死にじゃないと自分を奮い立たせて慰める気持ちの表れなんです。そういうことを理解してやらないといけない。つらいんですよ、本人は・・・・』
忠正さん自身、当時、内心は戦争には批判的だった。海軍で上官から毎日のように暴力を振るわれ逃げ出したい一心で特攻隊員に志願した。『もし遺書を書くとすれば自分も同じことを書いていた』と打ち明けた」
他にも特攻隊員として出撃する直前になって暴れまわる人や、深刻な顔をして女を買いに行った人などの話もあります。
ちなみに、「天皇陛下万歳!」などと言いながら死んでいった人はほとんどいなかったようです(「お母さん!」と言って死んだ人は多い)。