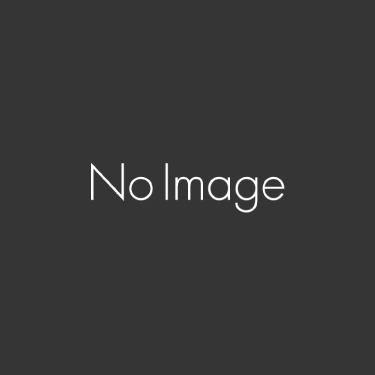人間の愛は自分の都合を優先する、自己中心的な愛です。
「すべての生物は、自分の利益が高まるように利己的に行動している。そして、利害が対立する相手とは競争したり、時には戦ったりする。もちろん、自然界には助け合いの関係もある。しかし、それも助け合うほうが得だから、助け合っているのである。ただ、それだけのことなのだ」(稲垣栄洋/静岡大学農学部教授)
小説家の有島武郎は、「愛の表現は惜みなく与えるだろう。しかし愛の本体は惜みなく奪うものだ」と言いました。
太宰治の小説「畜犬談」には次のように書かれています。
「犬の傍を通るときは、どんなに恐ろしくても、絶対に走ってはならぬ。にこにこ卑しい追従笑いを浮べて、無心そうに首を振り、ゆっくりゆっくり、内心、背中に毛虫が十匹這っているような窒息せんばかりの悪寒にやられながらも、ゆっくりゆっくり通るのである。つくづく自身の卑屈がいやになる。泣きたいほどの自己嫌悪を覚えるのであるが、これを行わないと、たちまち噛みつかれるような気がして、私は、あらゆる犬にあわれな挨拶を試みる」
犬を人に置き換えれば、「人間失格」の対人恐怖症の世界です。太宰が犬にも人にも、これほど愛情を振りまくのは自分が可愛いからです。そのことを太宰の妻である美知子夫人は「回想の太宰治」の中で次のように語っています。
「一緒に歩いていた太宰が突如、路傍の汚れた残雪の山、といってもせいぜい50センチくらいの山にかけ上がった。前方で犬のケンカが始まりそうな形勢なのをいち早く察して、難を避けたつもりだったのである。
それほど犬嫌いの彼がある日、後についてきた子犬に『卵をやれ』という。愛情からではない。恐ろしくて、手なずけるための軟弱外交なのである。人が他の人や動物に好意を示すのに、このような場合もあるのかと、私は怪訝に思った。
『恐ろしいから与えるので、欲しがっているのがわかっているのに、与えないと仕返しが怖ろしい』
これは他への愛情ではない。エゴイズムである。彼のその後の人間関係を見ると、やはり『子犬に卵』式のように思われる。がさて『愛』とはと、つきつめて考えると、太宰が極端なだけで、本質的にはみなそんなもののようにも思われてくる」
ビートたけしは次のような話をしています。
「結局、自分にとってアフリカで難民が何人死のうが、ヘルツェゴビナで撃ち合いやろうが、日本人でいるかぎり何も思ってないじゃん。で、食いたくないタイ米を援助として送るなんていってる程度だもん。そのくらいのことしか頭にないんだよ。完全な投げ銭ってのはしないのであって、後で取り返そうと狙っているんだ」
政治家のシャルル・ド・ゴールは、「支配者になろうとして、政治家は下僕のふりをする」と言いましたが、これは政治家に限りません。
哲学者のモンテスキューは、「友情とは、誰かに小さな親切をしてやり、お返しに大きな親切を期待する契約である」と言いましたが、これは友情に限りません。
自分の利益を一切期待しない純粋な愛を与えることは、人間にはできないのです。自分の利益の延長としての利他ということであり、この点、「利己的な遺伝子」の著者で知られる動物学者のリチャード・ドーキンスと共通点があるでしょう。彼は、人間の行動はすべて利己的な性質を持つ遺伝子を運ぶための手段にすぎないと主張している人ですが、利他的行動が多くの動物にみられる理由について、利他的に振舞ったほうが結果的に自分の遺伝子の生存の可能性を高めるからだと書いています。
それは最も純粋な愛に近いといわれる親の愛であっても同じです。
「生命原則の『個体が生き残る』ことと『種が繁栄する』ことは並列ではなく、まず個体として生き残ることが先で、次に種が繁栄するために行動する。私たちの視野が狭い理由は、まず個体として生き残るために必要な機能」(高橋祥子著「生命科学的思考」より)
何の利益も求めない無償の愛を与えていると思っている人は多いですが、それは自惚れです。裏切られて初めて有償の愛だったことに気づく人も多いです。愛とは、己を利するためにする狡猾な演技であり商売ともいえます。