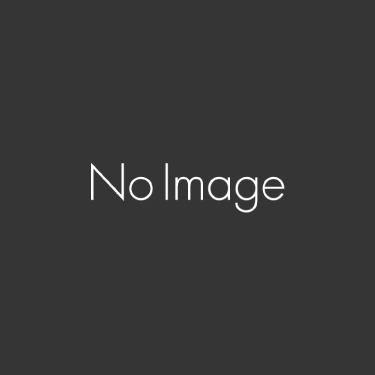人間は必ず死ぬ
「生あるもの必ず滅す」といわれるように、すべての人は死から逃れることはできません。人間は膨大な金と時間と労力を使って、必死に死を遠ざけ抵抗しますが、必ず負けることが決定しています。
致死率100%
幸せな時であろうと不幸な時であろうと、意識するとしないとにかかわらず死は確実に近づいています。
「人生は死に向かっての行進」と言った人もいますが、統計上は、死ぬ確率は年齢とともに上がり、最後は100%になります。日本対がん協会が「がんは、万が一じゃなく二分の一」という広告を出していましたが、「死は、万が一じゃなく一分の一」です。
「人生でただ1つ確実なことがあります。人生の最終解答は『死ぬこと』だということです。これだけは間違いない。過去に死ななかった人はいません。人間の致死率は100%なのです。ガンの5年生存率が何パーセントだ、SARSの死亡率が何パーセントだと世間では騒いでいますが、その比ではないのです。
ところが、そのへんを勘違いしている人が非常に多い。現代人は皆、人は必ず死ぬということをわかっていると思い込んでいるけれども、どこまで本気で考えた末にわかっていると感じているのかは甚だ怪しいように思えます」
「人間というのは、生まれた時から死に向かって不可逆的に進行する存在なのです」(養老孟司)
「人間の生きんとするたたかいは必死であり、その中に悲壮な美しさを見出し得る場合もある。しかしこのたたかいは結局、いつかは、生命を主張する側の、惨憺たる敗北に終るべき宿命の下にあるものである」(岸本英夫/宗教学者/東京大学教授)
「人生は山登りのようなものさ。登っている間は人は頂上を見ている。そして自分を幸せと感じるが、上に着いたが最後、たちまち下りが見える。終わりが、死である終わりが、見える」(G.モーパッサン/小説家)
「症状軽減のため、医療を利用するのはいいでしょう。しかし、医療には、若返らせることもできず、死ぬことも防げないという『限界』が厳然としてあるのです。今後どんなに医療が発達しようとも、『老いて死ぬ』という大枠は、どうすることもできないでしょう」(中村仁一/医師)
「死は人間の貴賤、貧富、その他一切の差別を潰して平垣にする偉大なる平等実施者、ブルドーザーである。死は人間を虫ケラほども尊敬しない。執行猶予は贖うことができない。我々一人一人は否応なく死にとらえられてしまう」(モーリス・ローリングズ)
「どこもかしこも健康食品ブームです。いつまでもピンピンしていないと不安だという人たちが、それに飛びつきます。そんなことはありえないわけで、いくらアンチエイジングに励んでも、必ず死にます。それが、少しだけ延びるか延びないかだけです」(村上和雄/筑波大学名誉教授)
「どんな馬鹿でも死ぬ時はくる。『あんまり馬鹿なもんで、生かされ続けた』っていうヤツはこれまでいないんだ。じつに、死ぬという事実は平等だからね。これほど平等なことはない」
「自分の健康に異常に気を使っているヤツが多くてさ、どうして、もっと死ぬことを考えないんだろう。株価も地価も右上がり神話は崩壊したっていうのに、寿命だけは右上がりだと信じているヤツがいっぱいいる」(ビートたけし)
釈迦でも死ぬ
釈迦でさえ死から逃れることはできませんでした。
「上は大聖世尊よりはじめて、下は悪逆の提婆に至るまで、逃れ難きは無常なり」(御文)
(訳:最も偉大な人間である釈迦から、その釈迦を殺そうとした極悪人の提婆に至るまで、すべての人間は死からは逃れられない)
釈迦教団の隆盛を妬み、理不尽に邪魔する者は数多くいましたが、その中でも有名なのが提婆です。提婆は釈迦の従弟にあたる男ですが、釈迦の教団を乗っ取るため、釈迦を何度も殺そうとしました。山の上から大岩を投げ落としたりしますが、提婆の計略はすべて失敗に終わっています。
しかしこの時、釈迦は足の指を潰してしまいました。提婆は仏の身体から血を流させるという大罪を犯したのです。この罪によって提婆は生きながら地獄に堕ちたと説かれています。
こういったことから「釈迦に提婆」といわれるように、提婆は悪人の代名詞のような存在になっています。
・死に始めている
見方を変えれば、すでに死に始めているともいえます。詩人のマルクス・マニリウスは「私たちは生まれたとたん死に始めている」と言いました。1日生きたということは、1日死んだということです。今、この瞬間も命は削られているのです。
健康はない
WHO(世界保健機関)によれば、「健康とは、ただ疾病や傷害が無いだけでなく、肉体的、精神的並びに社会的に完全に快適な状態であること」とあります。
しかし、人間は確実に死に向かっているわけですから、不治の病にかかった病人と見ることもできます。
「生きているということは一つの病気である。誰もがその病気によって死ぬ」(ポール・モラン/作家)
「人生とは、病人の一人一人が寝台を変えたいという欲望に取り憑かれている一個の病院である」(シャルル・ボードレール/詩人)
「人間は弱点や煩悩を持っているから常に病的部分を少しは有しているので完治は有り得ない」
「つまり一般健常人といわれている人も部分的に病的であり、完治していないのである。人間は永遠の寛解状態にあるのである」(平井孝男/精神科医)
阿含経には、「人間はあたかも、古びた車が革ひもであちこち補修されて、やっと動いているようなものだ」とも説かれています。
生と死は一体
詩人のカリール・ジブランは「川と海が一体であるように、生と死は一体である」と言いましたが、生と死は別々なものではなく、表裏一体であり切っても切り離せない関係にあります。
人生は死で決まる
「人事は棺を蓋うて定まる」といわれるように、死は人生の総決算にあたるものです。「終わり良ければすべて良し」という諺がありますが、人生の良し悪しは死の良し悪しで決まります。
「人間最高の幸福とは何か、幸せに死ぬことだ」(アンティステヌス/哲学者)
「汝が生まれたとき汝は泣き、汝の周囲の人々は喜び、汝がこの世を去るときには汝の周囲の人々が泣き、汝のみ微笑むようにすべし」(インドの諺)
今どんなに幸せだと思っている人でも、臨終(完全な死の直前)が不幸なら「不幸な人生だった」と思うということであり、今どんなに不幸だと思っている人でも、臨終が幸せなら「幸せな人生だった」と思うということです。
古代ギリシャで、当時繁栄していたリディアのクロイソス王は、富に恵まれた自分は世界一幸福な人間に違いないと考えました。そこで、クロイソス王は賢人として知られていたソロンに「世界一幸福な男は誰か」と尋ねました。「鏡よ鏡、世界で一番美しいのは誰?」の男版のようなものです。
するとソロンは、こう答えました。
「ある人が幸福かどうかは、亡くなって初めてわかるものです。あなた様はまだご存命なのですから、一番幸せ者かどうかは判断できません。それに今後あなたをどんな運命を待ち受けているか、誰も知りようがないではありませんか」
ソロンの言葉にクロイソス王は憤慨しました。
しかし、その後、愛する子供を先に失い、財宝も国土もペルシア軍に奪われ、自身もとらえられてしまいます。焼き殺されようとする時、クロイソス王はソロンの言葉がいかに正しかったかを悟ったといいます。
人生で学ぶことは死ぬこと
詩人のマシュー・アーノルドは「真理は瀕死の人の唇からもれる」と言いましたが、死ぬ時になって初めてわかる真理があります。しかし、死んでからでは遅いので、その真理を死ぬ前に知る必要があります。哲学者のセネカは「生涯をかけて学ぶべきことは、死ぬことである」と言いましたが、こういった理由から、人生は死を知るためにあるといってもいいのです。
死の備え
「備えあれば憂いなし」とはいいますが、来ないかもしれない災害でさえ万が一に備えて莫大な予算や労力、時間を使います。まして、やってくることが確実な死です。備えなくていいはずがありません。
「『ベッカーさんは、なぜいつも死を考えるのか』と聞かれることがある。(中略)
病気や老衰、事故、犯罪、自殺などで人が死なない日もなければ、戦争が起こっていない日もない。図書館に入ると死者の功績である書籍に囲まれるし、町を歩くと、死者が作ってくれた道や壁、建物などが目に入る。スーパーやレストランに入ったり、自分で食事を作ったりすると、死にたくなかった動物を手や箸で摘む。テレビやインターネットでニュースを見るたびに、死は目につく。『なぜ死を考えるのか』と聞かれても、『死を考えずに、どうしていられるのか』と答えたくなる。教育というのは、起こるかも知れない事への準備だと言えよう。将来的に作文や計算、外国との交流などの必要があろう、という前提で、その準備として義務教育で国語や算数、英語などを学ぶ。ただ、起こる確率が最も高いことは死であるに違いない。ならば、死に対する準備として、死の準備教育や、死の受容教育があっても当然と言えよう」(カール・ベッカー/京都大学教授)
人間は死を考えない
ところが、平生元気がいい時に死について真剣に考え続ける人は少ないです。「人間は唯一、死を考える能力を持っている生物」といわれていますが、その能力を使わないのです。その理由はいくつかあります。
考えてもわからない
まず、考えてもわからないという点が挙げられます。科学もまだ死について答えることができませんし、自分自身に死んだ体験も当然ありません。考えたところで何をどうしたらいいのかわかりません。
死は嫌なもの
このような理由から、死を考えないように考えないようにという方向にバイアスがかかっていきます。ほとんどの人は、死をごまかし、臭い物に蓋をする生き方をして臨終に突っ込んでいくのです。
「死は生の不可欠な一部である。われわれはみな、生きることの代償として正面から死と向き合わねばならない。それなのに、われわれは愛ゆえの嘘のために臨終の場面をないがしろにしている。そこでは、医師も患者もその状況が現実であることを否定しているのだ」
「死の問題はかつての性の問題と同じく、口にしてはいけないタブーとなっている。性については、性教育が学校のカリキュラムに組み込まれる時代になったが、死はないがしろにされたままである」(メルビン・モース/小児科医)
「必ずしも遭遇するとは限らない災害ですが、万一を考え入念な対策を講じることはもちろん大切です。しかし、死はすべての人間が必ず遭遇する『究極の災害』です。にもかかわらず、それに対する制度的な備えは、あまりにお粗末なように思われます」(大門正幸/言語学者/中部大学教授)
「結局、人間は、生まれた以上、いつかは死の準備を始めなくてはならないのです。しかし、情報化時代にもかかわらず欠けているのが、そのための案内書です」(NHKスペシャル「チベット死者の書 仏典に秘められた死と転生」より)
死なないと思っている
そして後述するように、人間は「自分だけは絶対に死なない」と思うようになります。
「人は、必ずこの世を去る。考えてみれば当たり前のことなのですが、医師がどんなに手を尽くしても、人の寿命を覆すことは絶対にできません。しかし、この厳然とした『真理』を我々はとかく忘れがちなのではないでしょうか」(矢作直樹/東京大学医学部教授)
生もおかしくなる
死を見つめないと生もおかしくなります。
「本来、『生死一如』、生と死はセットのはずなのに、死から切り離し、生のみが謳歌されてきました。その結果、すぐ自殺する、一度人を殺してみたかった、誰でもよかったなどと、『生』までがおかしくなってしまったような気がしてなりません」(中村仁一/医師)
「死に備えている」
「死を考え、死に備えている」と自負している人もいます。
では、彼らは何をもって死の備えとしているのかというと、それが世間一般で幸せとされているもの、つまり無常の幸福になってしまっています。
無常の幸福しか知らないので、それは無理がないことですが、後述するように、無常の幸福では死の備えにはまったくなりません。
若者を憂う老人を憂う釈迦
古代エジプトでも「最近の若者は」と言われていたという説もありますが、その真偽は別として、老人が若者の視野の狭さを批判するのが世の常です。
しかし、かくいう老人も、やがてやってくる死や死後といったもっと広い視野までは見渡せていません。つまり、こういう老人は「木を見て森を見て山を見ず」というような状態になっているのです。