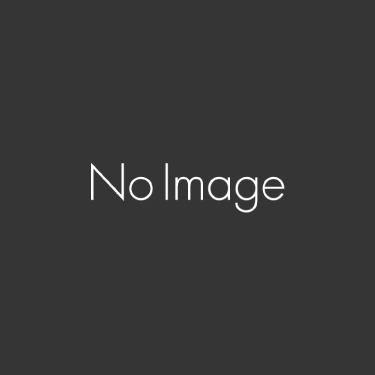死は、世間一般で思われているよりもはるかに深刻な世界です。
死は最大の苦しみ
人生には無数の苦しみがありますが、死の苦しみは他のどんな苦しみより大きいものです。死以外の苦しみは浅い水溜りで溺れているようなものですが、死は大海で溺れるようなもので、とにかく比較になりません。
・他の苦しみが幸せに思える
苦しみは相対的なものなので、比較するものによって苦にも楽にもなります。どれほど強い苦しみであっても、死の苦しみに比べれば幸せに感じられます。
たとえば、「自分が死ぬより家族が死ぬほうが苦しい」という人は多いですが、そうではないのです。家族のように大切な人を失う苦しみは愛別離苦であり、これは四苦八苦のうちの1つです。死苦より苦しいことはないのです。
死で目が覚める
「人生は夢を見ているようなものだ」と言われても中々わかりにくいものですが、死ぬ時にそれが一瞬で理解できます。
「人生は夢である。死がそれを覚まさせてくれる」(ホジヴィリ/哲学者)
すべての信心が崩れる
どんなに強い意志や精神力、信念や信仰心といったものがあろうが、すべて死によって砕かれます。不退転の悟りを開いたと思っていても死を前にして退転する境地だったことを自覚する人もいます。
どんな幸せも力にならない
どんな幸せも、死の苦しみには無力です。
「死を前にしてはニーチェもキルケゴールも役に立たなかった」(瀬田栄之助/小説家/臨終の言葉)
「死というものの凄さというのは、自分の人生振り返って、何をしたとか何をしてないとかいうのは全然関係ない。そんなことはビタ一文かすんないんだよ。おれは生前いいことしてたんだから長生きさしてくれとか、そんなこと全然関係なく、ドンと来るんだよね」
「これほどまでに人間があっけない存在だってことには気がつかなかったね」(ビートたけし)
「人間の最高の栄冠は、美しい臨終以外のものではないと思った。小説の上手下手など、まるで問題にも何もなるものではないと思った」(太宰治)
芥川は、死を目の前にして作品が紙切れに思えたといいます。
ウィンストン・チャーチルは臨終に、「私は随分沢山のことをやって来たが、結局何も達成できなかった」と言って死んでいきましたが、死を前にすれば、何も手に入れてなかったことがわかります。
「種々の悪業をもって財物を求めて、妻子を養育して歓娯すと謂へども、命終のときに臨みて、苦、身に逼まり、妻子もよく相救うものなし。彼の三途怖畏の中に於て、妻子及び親識を見ず。車馬も財宝も他人に属し、苦を受くるとき誰か能く苦を分つ者あらん。父母・兄弟及び妻子も、朋友・僮僕ならびに珍財も、死し去れば一として来りて相親しむもの無し。唯黒業のみ有りて、常に随逐す」(宝積経)
(訳:無数の悪業を造って財宝を求め、妻子を養って楽しみとするが、死ぬ時には苦しみが身に迫り、妻子も救うことができない。地獄の恐怖が迫れば、妻子も親族も眼に入らない。車馬も財宝もすべて他人のものとなり、この苦しみを共に分かち合うものは誰もいない。父母も兄弟も妻も子も、友も僮僕も財宝も、死んでいく時には1人としてついてきてはくれず、ただ悪業だけが常につきまとう)
幸せでなかったことがわかる
先に説明したように、臨終の禍福(不幸や幸せ)で人生の禍福が決まるので、今どれほど幸せだという人でも、自分の人生は幸せではなかったことが臨終になればわかります。
「隠者の夕暮」などの代表作がある教育家のペスタロッチは、「臨終に自分が幸せでなかったことを声高く叫ぶ」と言いました。
努力してなかったことがわかる
一概に「必死」といってもレベルがあります。どんなに必死に努力して生きてきたと自負している人でも、死を前にすれば自惚れだったことがわかります。つまり、「一生懸命生きていなかった」「時間を無駄にしていた」ということがわかるのです。
小説家の平林たい子は臨終に、「今度こそ一生懸命生きますから、何とか生かしてください」と医者に懇願して死んでいきました。
武将の伊達政宗は、「いたずらに月日を送り 病におかされ 床の上にて死なん命の口惜しや」という辞世の句を残しています。
ビートたけしは事故の後、「今までどうしてこんな生き方したんだろうって反省が猛烈に襲ってきた。過去の自分に対する自己嫌悪」と語っています。
精神科医の加賀乙彦の著書「死刑囚の記録」には、ある死刑囚の次の言葉が紹介されています。
「死刑の執行が間近いと思うと、毎日毎日がとても貴重です。1日、1日と短い人生が過ぎていくのが、早すぎるように思えます。それにしても社会にいたとき、なぜもっと時間を大切にしなかったかと、くやまれてなりません。もういくらも時間が残っていない。だから急がねばなりません」
老人を対象にしたあるアンケートでも「人生で1番後悔していること」として、「もっとチャレンジすればよかった」を挙げている人が1番多いそうですが、どれほどチャレンジしようが必ず後悔します。
死は孤独
「まやかしだよ家族なんか。一定期間は大事よ。でも死が近づいてきた時に1人になるんだよ、人間は。子供なんて一番薄情よ。いざとなったら。ある程度までは幸せだよ。最後を迎えるときは家族とかそういう問題じゃなくなってる気がするんだよな」(マツコ・デラックス/タレント)
死は、この上なく孤独な世界です。死んでいく時には、1人で死んでいかなければならず、誰もついてきてはくれません。
「人、世間愛欲の中にありて、独り生れ独り死し、独り去り独り来る」(大無量寿経)
(訳:人は世間の愛欲の中に生きているが、独りで生まれ独りで死に、独りで来て独りで去るのである)
「もし只今も、無常の風きたりて誘ひなば、いかなる病苦にあいてかむなしくなりなんや。まことに、死せんときは、かねてたのみおきつる妻子も、財宝も、わが身には一つも相添うことあるべからず。されば、死出の山路のすえ、三途の大河をば、唯一人こそ行きなんずれ」(御文)
(訳:もし今、無常の風が吹いてしまえば死んでいかなければならない。いざ死んでいく時は、頼りにしていた家族や財宝も、1つもついてきてはくれず、1人で地獄へ堕ちて行かなければならない)
次のような古歌もあります。
「独り来て 独り死にゆく 旅なれば つれてもゆかず つれられもせず」
「人の世の 生死の道に 友はなし 一人淋しく 独去独来」
「むつまじき 親子にだにも すてられて 独りゆくべき 道と知らずや」
死は、この上ない苦しみですが、その苦しみは誰にも理解できません。
すべてに裏切られる
力になると思っていたのに力にならないということは、つまり裏切られるということです。意識するとしないとにかかわらず、「これだけは裏切らない」と信じているものが人間にはありますが、すべてに裏切られて死んでいかなければなりません。
雑阿含経には三夫人の話があります。
ある金持ちの男が3人の妻を持っていました。
第一夫人は一番のお気に入りで、片時も離さず、あれが食べたいと言えば食べさせてやり、あれを着たいと言えば着せてやりました。
第二夫人は第一夫人ほどではありませんが、他人と競争して手に入れただけに執着は相当なもので、できるだけ側においてかわいがりました。
第三夫人は第一夫人や第二夫人と違い、たまに顔を合わせる程度でしたが、それでも淋しい時や苦しい時には無性に逢いたくなり、すぐに呼びつけて心を慰めました。
やがて、その男が不治の病にかかりました。死に臨んでは医者も薬も何の力にもならないことを知らされた男は、死に怯え、その救いを第一夫人に求めました。しかし、「そこまではできない」とあっさりと断られてしまいます。
続く第二夫人にも「自分から望んであなたの側にいたのではありません」と言われ、第三夫人にも「村はずれまでならいいですが、そこから先はご勘弁ください」と同じように断られます。
男は猛烈に腹を立て後悔しましたが、すでに手遅れで、死に1人飲み込まれていきました。
「金持ちの男」は私たち1人1人のことであり、第一夫人は自身の肉体、第二夫人は財産や宝、第三夫人は「父母」「兄弟」「妻子」「友人」などをたとえています。
臨終は、人生が根本から覆ってしまうのです。
全身を失う
たとえば、片腕を失っただけでも耐え難い苦痛であり、両腕がある人には想像もできないでしょう。
まして、死は全身を失うということなので、その苦痛は想像してもし切れないのです。
「人間にとって何より恐ろしいのは、死によって、今持っている『この自分』の意識が、なくなってしまうということだからである。死の問題をつきつめて考えていって、それが『この、今、意識している自分』が消滅することを意味するのだと気がついたときに、人間は愕然とする。これは恐ろしい。何よりも恐ろしいことである。身の毛がよだつほど恐ろしい」
「死が、実際に自分の上に襲ってきたら、どういうことになるのか。自分は床の上で、最後の息を引き取る。息の絶えた自分の死体は、棺桶におさめられる。火葬場に運ばれる。この身は、牢獄のような火葬場の窯の中に置き去りにされる。そして、一瞬のうちに焼き尽くされてしまう。自分は、白骨と髑髏とひとにぎりの灰だけになる。そして、永久に、この世から消えてなくなってしまうのである。自分がなくなるということは、一体どういうことか。いま、ものを考えているこの自分というものがなくなるのである。自分にとっての、なにもかもがなくなってしまうことである。これは、考えようとしてみても、うまく考えられない。つかみどころのないようなことがらでありながら、思っただけでも、身の毛のよだつようなことである」(岸本英夫)
すべての記憶が消える
今、過去世の記憶がないように、死ねば大切な人の記憶もすべて消えます(第1巻でも見たように正確には「忘れる」ですが)。
家族も死ぬ
死ぬ時についてきてくれないということは失うということであり、家族が死ぬ苦しみ(愛別離苦)も含むということです。「自分が死ぬより家族が死ぬほうが辛い」という人は多いですが、「自分だけが死んで家族は生き残る」という表現は正確ではなく、「自分も家族も死ぬ」という表現が正確です。
もちろん、家族だけに限りません。自分が生きた証を何かしらの形や記憶として、自分の子孫など、後世の人々に残すことができれば満足だと思っている人は少なくありません。
しかし、これは残された人間の視点であって、「自分の死」が抜けており、すべて失うという視点が抜けています。もちろん死後の地獄も抜けています。
楽な死に方はない
なぜ死が苦しいのかというと、心が死ぬからです。心の死苦に比べれば、肉体の死苦は取るに足りません。
「ぽっくり逝きたい」「眠るように死にたい」「ピンピンコロリがいい」といったように誰もが楽な死に方を望みます。そして、その期待に合わせて「医師が選ぶ、楽な死に方」とか、あるいは逆に「この死に方が1番苦しい」といったテーマの記事がよく出されます。
第一生命のアンケートで「医師に『死期が近い』と宣告されたら、不安や心配になることは何か」と聞いたところ、最も多かったのは「病気が悪化するにつれ、痛みや苦しみがあるのではないかということ」で、56.2%と過半数を占めています。そして、「死への恐怖心は、死そのものよりも、苦しみや痛みに対してが大きい」という結果を公表しています。
しかし、こういった話はすべて肉体の死苦のことです。肉体の死苦だけに目を向ければ「比較的楽な死に方」というのもあるでしょうが、圧倒的な心の死苦と比較すれば大して違いがありません。死そのものの苦しみのほうが、肉体の苦しみや痛みよりはるかに大きいのです。よくハンマーで思い切り殴られたような激しい痛みを伴うと形容される「くも膜下出血」も、高層ビルからの飛び降り自殺も、溺死も、焼死も、老衰も、苦という点では大差はないということです。
人間は肉体の死苦に目が向きやすいですが、それは、1億の苦に目を向けず1や2の苦に目を向けているようなものです。
「死は、ほとんどすべての場合に肉体的な苦痛を伴う。生物というものは、肉体的苦痛なしでは、その生命を終ることができないようにつくられているらしい。それは、進化論の適者生存の理論から考えても、やむをえないことである。(中略)それゆえ、死の苦しみについて人々がまず思うのは、死に至るまでの肉体的な苦しみである。(中略)そこで、死に至るまでの病の苦しみさえなければと、人々は考える。それさえなければ死も、それほど怖いものではない、とすら思う。
しかし、その考え方は、まだまだである。それには、まだ、問題の混同がある。死に至るまでの苦しみが、あまりに激しいので、それと、死そのものの苦しみとを混合しているのである。そして、死に至るまでの肉体的な苦痛を解消できれば、それで死の問題は、すっかり解決したかのように考える。しかし、問題はそれほど単純ではない。死の苦しみの中には、もっともっと深刻なワナが隠されている。肉体的な病気の苦しみは、かりにそれが苦しくても、それは、死に至るまでのことである。その途中の苦しみにすぎない。死そのものの苦しみではない。死に至るまでの肉体的な苦しみと、死そのもののもたらす精神的な苦しみは、別のものである。死の苦しみは、いわば、二重の構造を持っている。途中の苦しみとは別に、その奥に、もっと直接な、死自体の苦しみが潜んでいる。この2つは混同されてはならないのである。
死自体を実感することのもたらす精神的な苦しみが、いかに強烈なものであるか、これは知らない人が多い。いな、むしろ、平生は、それを知らないでいられるからこそ、人間は幸福に生きていられるのである。しかし、死に直面したときには、そうはいかない。人は、思い知らされる。その刺し通すような苦しみが、いかに強烈なものか、そのえぐり取るような苦しみを、心魂に徹して知るのである」
「この2つは、質的には、まったく異なった要素でありながら、両者は、時間的には、ほとんど同時に人間を襲ってくる。それで多くの場合、両者は混同されてしまう。
ところかまわず襲ってくる激痛、高熱、吐瀉、下痢、呼吸困難、このような、思ってもゾッとするような苦痛なしには、この人間の肉体は、生命を失ってゆくことのできない場合が多い。それだけに心を奪われて、それだから自分は死ぬのが怖いのだと思っている素朴な人々も多い。
しかし、これは前山の高さに気をとられて、そのうしろにひかえている真の高山を見誤る考え方である。肉体の苦痛はいかに激しくとも、生命を断たれることに対する恐怖は、それよりももっと大きい」(岸本英夫)
このように心の死苦に比べれば肉体の死苦は取るに足らないものですが、肉体の死苦についても、老衰含め、楽な死に方はおそらくないでしょう。
「絵に描いたような美しい見解だし、社会通念として『老衰で死ぬ』というのはポピュラーで、多くの人が望んでいる。(中略)しかし、老衰で死ぬのは実際ありえない。歳をとるごとに心臓の鼓動がゆっくりになっていき、最後の夜遅くについにピクリとも動かなくなる・・・なんてことはない。老化すると、がんや認知症などの病気にかかるリスクが増していき、そのうちのどれかが命取りになりかねない。しかし、老衰そのものが死を招いたわけではない」(デビッド・カサレット/デューク大学医科大学院教授、緩和ケア部門主任)
すべての死は惨殺
死にたくないという願いに反して圧倒的な死苦がやってくるわけですから、言い方を変えれば、人間は必ず「惨殺」されることになります。もちろん他の誰でもない、自分が造った悪業によってです。詩人のプーシキンは臨終に「もう命はおしまいだ。息をするのが苦しい。何かが僕を粉砕する」と言って死んでいきましたが、この「何か」が悪業です。
必ず後悔する
愛別離苦などでも見たように、大切なものを失うと人間は必ず後悔します。死は、人間にとって一番大切な自分の肉体を始めすべてのものを失うということなので、必ず後悔します。今、幸せであろうが苦しんでいようが、善をしていようが悪を造っていようが、人生は後悔で終わるのです。
仏教で説かれる一切は臨終に体験的に証明されますが、その証明は悲惨です。体験的な証明では遅いのです。
「それ、朝にひらくる栄花は、夕べの風に散りやすく、夕べに結ぶ命露は、朝の日に消えやすし。これを知らずして常に栄えんことを思い、これを覚らずして久しくあらんことを思う。
しかる間、無常の風ひとたび吹きて、有為の露永く消えぬれば、これを曠野にすて、これを遠き山におくる。屍はついに苔の下にうずもれ、たましいは独り旅の空に迷う。妻子眷属は家にあれどもともなわず、七珍万宝は蔵に満てれども益もなし。ただ身にしたがうものは後悔の涙なり」(登山状)
(訳:さて、朝に開いた栄華という花も夕べには風が吹いて散りやすい。夕べに結んだ命の露は、朝日がくれば消えやすい。この道理を知らず常に栄えていたいと思い、この道理を自覚せずに「まだまだ生きられるだろう」と思う。
そのように思っているうちに、無常の風が一度吹いて儚い命が永遠に消えてしまえば、荒野や山で焼かれてしまう。屍はやがて苔の下に埋もれ、魂は独りで空を彷徨う。妻子や親族は家にいてもついては来れず、どれほど財宝があっても何の役にも立たない。ただ身に従うものは後悔の涙だけである)