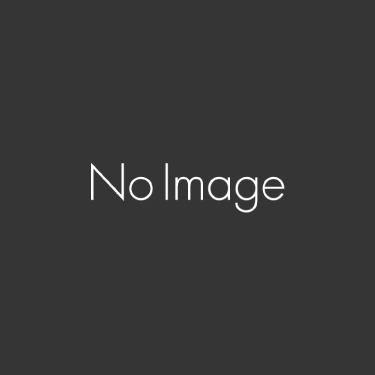動物を殺しても何とも感じない心理がある
ある畜産高校の女生徒が、大切に育ててきた豚を出荷することになった際、次のように言っていました。
「もう出荷されるのか、と寂しくなったが、人に食べられるために生まれてきたんだと。美味しく食べてもらえたらうれしい」
豚は、人に美味しく食べられることを本当に喜んでいるのでしょうか。そんなはずはないでしょう。
「ブタも人間同様、生への欲望や、殺されるときには苦しみ、悲しみを感じている。違いは、それを言葉にできないということだけである」
「ウシたちの望みは分かっている。彼等は生きたいのだ。何のためであれ、自分を犠牲にしたいはずはない。ウシが肉として食べられたがっているというのは、作り話である」(ジェフリー・M・マッソン)
BBCのニュースで、「火事から救出の子豚たち ソーセージとなって助けた消防士たちに」というタイトルの記事がありました。
英南西部ウィルトシャーの養豚場で火事が発生し、消防士たちが豚を救出、その後、農場主は、その豚をソーセージに加工し、消防士たちにプレゼントしたというものです。
消防士たちはバーベキューでソーセージを楽しみ、「最高だった」「おすすめだ」と称賛したといいます。
焼き殺されるか、切り殺されるか、豚の立場からすればどれほどの違いがあるのでしょうか。
解剖学者の養老孟司(東京大学名誉教授)は、次のような差別をしていたことを告白しています。
「30代の後半の一時期、私は動物や虫を殺せなくなったことがありました。急に殺生ができなくなった。解剖に使うのは死体だから、殺す必要はない。だから、それには支障がないのですが、実験に使うネズミも飼っていると情が移ってきて、殺せなくなった。それでどうしたかというと、わざわざ野生のネズミを捕まえてきて実験に使ったりもしました。殺すという行為は同じなんですが、捕まえてくるという要素が入ると、狩猟のような感じがして、自分の心を合理化しやすかったのかもしれません」
ペットを飼っている人なら、「自分は動物を可愛がっている」と自負しているでしょう。しかし、首輪をつけられたり、鎖につながれたり、狭い小屋に閉じ込められたりして、動物たちは本当に幸せなのでしょうか。
「仕事だから仕方ない」とか「感謝して食べれば許される」と思っていたりと、人間は自分に都合がいい理由をつけて罪悪を肯定化してしまいます。
「人が虎を殺そうとする場合には、人はそれをスポーツだといい、虎が人を殺そうとする場合には、人はそれを獰猛だという。罪悪と正義の区別も、まあそんなものだ」(バーナード・ショー/劇作家)
人間の都合で、天然記念物として守られる動物もいれば、害獣として殺される動物もいます。
中国で犬を、「可愛いよ、可愛いよ、食べても美味しいよ」と言って売っている人がいましたが、人間は皆、自分の都合で動物を可愛いペットにも食材にもしてしまいます。
人気漫画「進撃の巨人」では、人間が巨人に捕食される残酷さがリアルに描写されていますが、人間も他の動物に対して同じことをしています。
動物が虐待されるのを見れば「かわいそう」と言い怒りを感じますが、人間は皆、何の罪悪感もなく虐待しているのです。
膨大な殺生をしていながらその自覚が無く、たまに動物に優しくし、それをもって善い人間だと自惚れているのが人間です。
この点、有名な「浦島太郎」にもたとえられるでしょう。
確かに浦島太郎は1匹の亀を助けました。しかし、彼は漁師ですので膨大な魚を殺してもいます。こういった自覚がないまま、あっという間に年を取って死んでしまうのです。
金子みすずという詩人がいます。
彼女の詩は、東日本大震災の際、ACジャパンのCMで頻繁に流されたので知っている人も多いでしょう。
彼女は仏教徒でもあったため、彼女の詩には仏教の生命観が表れています。たとえば、次の「大漁」という詩があります。
朝焼小焼だ 大漁だ 大羽鰮の 大漁だ
浜は祭りの ようだけど
海のなかでは 何万の 鰮のとむらい するだろう
前に「魚天国」という歌も流行りましたが、魚の立場からすれば魚地獄です。この歌の中には「魚は僕らを待っている」という歌詞が何度も出てきますが、殺されるのを待っているわけがなく、実際、捕まえようとすれば彼らは逃げます。
ACジャパンのCM「犯罪者のセリフ」が話題になっていました。可愛らしい子犬を段ボールに入れて捨てる親子。親子が「親切な人に見つけてもらってね」と言って子犬を捨てようとする場面に、「優しそうに聞こえても、これは、犯罪者のセリフです」というナレーションが入るのです。
このように、人間の自己中心的な生命観は至る所で見られます。
生物学研究員として長年、動物実験を行っていたマイケル・A・スラッシャーは、なぜ動物実験に対して罪悪感がなかったか、その理由を著書「動物実験の闇 その裏側で起こっている不都合な真実」の中で次のように分析し懺悔しています。
「食肉加工施設で働く人々と同じく、私は自分の内にある『思いやりスイッチ』を切っていた。私は業務をこなすだけで、絶滅収容所に勤めるナチスの看守よろしく、命令にしたがっていたにすぎない。学のある科学者の上司がやれと言ったことに、そう大きな問題があるとは思えなかった」
「自分の行為は衛生的かつ臨床的な環境で、利他的な意図から行われていた。それは私の中では人間生活の向上を目指す科学であって、飽食家の舌を満足させるだけの心ない屠殺解体とは違った」
「この仕事に就いていた時のことを思い返すと、当時の自分が業務に対して罪悪感を覚えていなかったことに驚く。確かに、大量殺戮をしながら気落ちする瞬間はあった。(中略)病気の対処法や治療法を見つけるという大きくて高邁な目標にしがみつくことで、道徳的な咎を免れているような、自分の所業をもってしてもなお悪に染まってはいないような気分になれた」
「けれどもその後になって、生物医学研究で実験用動物を人間の代用とすることの恐ろしさを知った」
「どうして自分があんなにも長い間、あんなにも盲目でいられたのか、不思議でならない」
「ちょうど人々が動物の肉身を食べながら、それがどこから来たものなのかを考えず、感情を具え個性を持った生き物が生涯にわたり苦しみを味わった末に食卓に並べられる現実を無視する如く、私もやはり実験用動物を個の生き物として見つめることがほとんどなかった。ただ膨大な数の同じようなラットやマウスがいるだけで、その存在理由は名誉ある人間の営みの歯車となることにしかないように感じていた」
「不透明性。保健所が殺処分を行うことは知っていたり、知らなかったりするだろうが、とにかく自分の中では、連れていかれた猫たちが親切な里親に引き取られるだろうと納得する。自分の庭で飼うニワトリ、隣家に暮らす大きくて人懐こい牛は愛おしいかもしれないが、食料品店で見かけるビニール包装された肉の塊はその動物たちではない。そもそも、それらはもう何の動物でもない。その呼び名は本質を包み隠す。それは今や『ヴィール』『ロースト』『サーロイン』である。『ポーク』『ハム』『ベーコン』である。それは単なる『肉』の塊である」
「現実が目の前にあってもなお、私は幻想に囚われ、動物たちは可哀想ながらも必要不可欠なモノだと考えていた」
「菜食人(ビーガン)の視点を得て初めて、私は動物や動物製品の利用が現代生活のあらゆる場面に浸透していることを知った。これは衝撃だった」
「動物実験者として長年にわたり働いてきた末にようやく、私はこの動物研究業界がことごとく故意の無知に根ざしていることを知った。それは旧態依然とした考え方への頑なな固執であり、『今までこうしてきたから』という理由だけでどこまでも現状を維持したがる姿勢である」
そして、ポール・マッカートニーの「もしも屠殺場の壁がガラス張りだったら、誰もが菜食主義者になるだろう」という言葉を引用しています。
人を殺しても感じなくなる
殺人でさえ罪悪感がなくなっていく心理が人間にはあるようです。
海兵隊員としてベトナム戦争の前線で戦ったアレン・ネルソンは、著書「『ネルソンさん、あなたは人を殺しましたか?』 ベトナム帰還兵が語る『ほんとうの戦争』」の中で次のような話をしています。
「女性や子供たちを数多く殺害しました。これは戦争です。戦争では安全な人間などひとりもいないのです。女性だろうが、子供だろうが、年寄りだろうが、戦闘にまきこまれれば死ぬであろうし、わたしたちに刃向かえば殺されるのは当たり前のことだと思っていました。それが、ベトナムの人々にとっては、たった1つの家族とたった1つの命をかけた絶望的なものであったとしても、わたしたちにとってはありふれた戦闘のひとつでしかありませんでした」
「子供たちは死んだ母親の腕や足にしがみつき、泣き叫びます。その泣き声は、家々が燃え盛る炎の音とともにジャングル中にひびきわたってゆきます。わかい女性が、その子供にかけ寄り、死体から子供を引き離そうとしますが、子供は力をふりしぼって母親の死体にだきつき、けっして離れようとしないのです。一方で老婆たちは死体の山の中に家族をさがします。そして、身内がみな殺されてしまったことを知ると、老婆は地面につっぷし、子供のように泣きじゃくるのです。こんなことが、何度も何度もくりかえされたのです。そして、その光景が目の前で何度くりかえされようと、わたしたちの感情は少しも動かされることがなく、ただただ無関心でした」
彼だけではありません。
「俺はハードディスクをぶっ壊したよ。死体やそういったもののそばで撮った写真やなんかが入ってた。恐ろしい。本当に恐ろしい。恐ろしいものだ。俺たちは死体と仲良くしてたんだ。あの当時、俺たちはひどい状態だった。最低の卑劣な殺人マシンだった。いまその当時を思い返すと、こう思う。ああ、俺たちは何をやってたんだ?何を考えてたんだ?」(「帰還兵はなぜ自殺するのか」より)
「10人で1人の女性を暴行した。女は足りなかった。そこで少女たちを捕まえようとした。12,3歳の少女たち・・・・泣き出したりしたら、殴りつけ、口に何かつっこんで黙らせた。痛がっても、こちらは愉快でしょうがない。今はどうしてあんなことに加わることができたのかわからない・・・・教養のある家庭で育った自分が?でも、あれは自分なんだ」(「戦争は女の顔をしていない」より)
「こういう兵士は悪人じゃありません。みなさんと同じような人間です。でも、ひどい状況に置かれていると誰だって恐ろしい反応をしてしまう。あんなにも多くの死に取り囲まれていたら、道に立っていた男を一人轢いたことなんて大したことじゃなくなる。それよりも、それを報告することで、あと2,3時間ベッドがおあずけになることのほうが重大なことになるんです」
「ある日、車でバグダードあたりを走っている時、道端に死体を見つけました。死体を確保するために車を脇に寄せ、憲兵が来て男の死体に対処するのを待っていた。男は明らかに殺されていました。すると仲間たちが車から降り、おきまりの満面の笑顔で死んだ男と一緒に写真を撮り始めた。そして聞きました。『おい、バイジェス、おまえもこいつと写真を撮るかい』
『いいや』と答えました。そう言ったのは、その行為が倒錯的だからでも倫理の基準に反しているからでもありません。断ったのは自分の殺しではなかったからです。自分が殺してもいないのに戦利品を得るわけにはいかない。それがあの時の思考状態でした。その男が死んでいることにうろたえてさえいなかった。自分でやってもいないことを手柄にするものじゃないと考えていた。しかし、それが戦争です。それが戦争なんです」(「冬の兵士 イラク・アフガン帰還米兵が語る戦場の真実」より)
「戦争ができるということ、ある文脈下では人を平気で殺すことに違和感がないということは、環境もしくは社会の中で、おそらく人が持っている脳の特質なのだと思います」(藤井直敬/脳科学者)