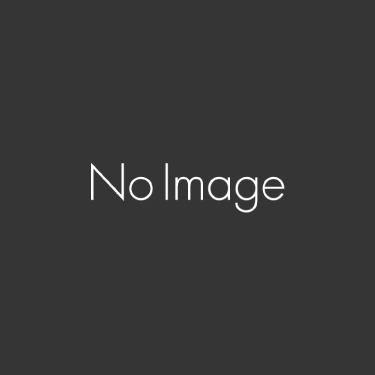現代の日本は飽食の時代なので、食欲の強さは普段感じないかもしれませんが、満たされない極限状態になると恐るべき本性が表れます。いくつか事例を紹介しましょう。
信長の家臣であった太田牛一が著した信長の一代記「信長公記」には、鳥取城の兵糧攻めについて次のように書かれています。
「初めのうちは、5日に1度、あるいは3日に1度、鐘をつき、それを合図に、雑兵が全員で柵ぎわまで出て来て、木の葉や草を採り、特に稲の切り株は上々の食い物であったようであるが、後にはこれらも採り尽くし、城内で飼っていた牛馬を殺して食い、寒さも加わって、弱い者は際限もなく餓死した。餓鬼のように痩せ衰えた男女が、柵ぎわへまろび寄り、苦しみ喘ぎつつ『引き出して、助けてくれ』と悲しく泣き叫ぶ有様は、哀れで見るに堪えなかった。
これらの者を鉄砲で撃ち倒すと、まだ息のある者にも人々が群がり、手に手に持った刃物で手足をばらし、肉を剥がした。五体の中でも特に頭部は味がよいと見えて、一つの首を数人で奪い合い、取った者は首を抱えて逃げて行った。まったく、命を守る瀬戸際となると、こんなにも情けないことになるのであった」
また、アウシュビッツの強制収容所での体験を綴ったヴィクトール・フランクル著「夜と霧」にも、次のような話が紹介されています。
「収容所での最後の数か月というものは、食料不足が深刻化(収容所職員は依然として肥っていたが)、囚人たちは人肉嗜食に頼るまでにいたった。友人は死体の片づけに従事していたとき、十にひとつくらいの割合で死体の股やその他の部分が切り取られて食べられているのを発見した。私もこの目で1人の囚人がナイフを死体に突き刺し、脚の一部を切り取り、それを急いで口に押し込んでいるのを見ました。真っ黒になった死体から、一片の肉を切り取って食う。それは、見るも恐ろしい光景でした。でも、そんなことまでしなければならないほど、囚人たちは追いつめられていたのです」
そして、ニューギニア戦線での体験を綴った、梅原千治(東京医科大学教授)の「飢餓の戦記」にも次のように書かれています。
「敵陣から漂って来る肉を焼く匂いに、飢え果てた兵らはたまりかねて突撃し、全滅した。椰子の実を獲ろうと登れば、たちまち敵陣に狙われ、猿のように打ち落されて死んだ」
「白人の肉を白豚と呼んだ。白豚の肉を切り取って飯盒一杯煮て食った兵隊もあった」
「私の部隊の一人の兵は、戦友から三升の米を奪おうとして、小銃を向けて射ち殺した。彼もまた直ちに捕えられ銃殺に処せられた。この加害者は大学出のインテリであり、しかも僧籍の兵であった」
同じく、ニューギニア戦線での体験を綴った、尾川正二(関西学院大学講師)の「極限のなかの人間」にも次のような記述があります。
「腐木に巣食う蛆、数匹の分配をめぐって、流血の騒動をひきおこす」
「白人・黒人を、白豚・黒豚と呼ぶようになってきた」
「8,9割が(人を)食うだろうというのが生き残ったものの答えだった」
「ある夜、国民兵のたった1人の生き残りであるO兵長の告白をきいた。
『人間て、つまらんものですね。自分は、気の弱い男だと思っています。なんにも、できはしません。だのに、自分の心の内をさぐってみると、誰かが自分の飯盒の中に入れてくれないかと、ひそかに期待している気持ちがあるんです。こうして打ち明けて、自分を恥じてみても、明日もまた同じことを待っているように思われるんです。もう、なさけのうて・・・・・』というのである。160センチそこそこの単身、3つ年長だったが童顔そのもの、顔のつくりもすべてが円く、いかにも人のよさを全身に示しているような男だった」
「限界状況における人間実験だった。人間がいかにありうるか、の恐ろしい試練だった。身の皮を引き裂いて、なかを覗いてみよと──」
他にも、たとえば天保の飢饉では、自分の子供を殺し半分食べ半分売り歩いたといった記録も残っています。
五欲の中で、最も強い欲が食欲とされています。つまり、極限状態に置かれた時に、食欲が最優先されるのです。
有名な千日回峰行を満行したという塩沼亮潤は、1番きつかったことは寝れないことでも横になれないことでもなく、水を飲めないことだと語っていました。
「hunger is the best spice(空腹は最高の調味料)」という諺もありますが、それだけ食欲は強いということです。
第2巻でも紹介したように、天下統一を果たした豊臣秀吉は贅の限りを尽くしていますが、後年、「位が高くなっていろいろ贅沢なものを食べたが、貧しい時代腹が減ったときに食べた麦飯ほど美味いものはなかった」と語っています。
【食欲の正体】極限状態になれば人を殺してでも食う
- 2022年7月15日
- 学ぶ