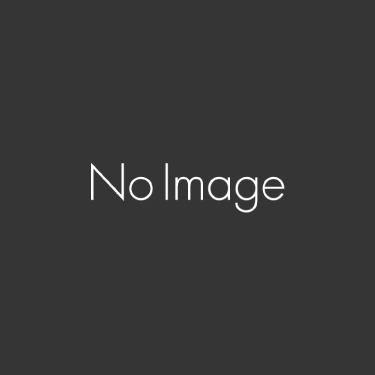「死が怖くない」などと高を括っていた人が、いざ死に直面するとまったく逆の反応を示すことを、こちらで詳しく説明しました。
同じことは医者にもいえます。
医者は仕事柄、多くの死に直面しているため、一見すると死に対する免疫がありそうに思えますが、果たしてどうでしょうか。
心療内科医の星野仁彦(福島学院大学教授)は、自分がガンと宣告された時の心理状態を、著書「末期がんを克服した医師の抗がん剤拒否のススメ」にまとめているので、いくつか抜粋します。症状から「もしかしたらガンではないか」と疑うところからです。
「ガンの可能性がある。後輩の内科医に症状を話して、判断してもらおう。万一、本当にガンであっても動揺してはいけない。いや、動揺することはない、これまでパニックに陥った患者を何人も診てきた私ではないか。そんな私が我を失い、取り乱すことなどあるはずがない」
「検査結果がどうであれ、すべてを受け入れる心の準備はできている。私は精神的に強い人間なのだ。そのときまでは、そう信じていた」
しかし、検査の結果ガンだと告知されると様子が一変します。
「ガンを告知された瞬間である。しかし、どんな患者の前でも決して内面をそのままには表さない医師の習慣なのか、平静を装うことができた。一度、頭の中で確認してみた。
『私は、大腸がんである』
動揺はない。私はやはり強い人間だった。
ホッとして足元に目を移すと足が震えている。デスクに手をついていなければ倒れていたかもしれないほど、激しく震えていた。動揺していることを自覚した私は、パニック状態に陥った。
『死ぬ危険性はどのくらいなのか』『残りの人生はどのくらいなのか』『手術で治るものなのか』『家族はどうなるのか』『私の将来は、ここで終わるのか』
浮かんでくる言葉は、すべてがネガティブなものだった。後輩が声をかけているようだが、何を言っているのか聞き取れない。聞き取れないが、平静を保とうとする私は頷くことでごまかそうとしている。
私はガンが発覚しても精神的に動揺しない自信があった。自分ほど精神的に強い人間はいないと思っていたからだ。精神科医として、うつ病やパニック障害、不安神経症などの心の病に悩む患者を数多く診てきた。精神科医としてのキャリアを積み重ねることで、強く冷静な自分、を確立していたはずだった。激しく足が震え動揺している私のどこが強く、冷静なのだろうか。私は弱い人間だった」
彼の妻は「抜け殻のようなあなたを見たのは、出会って以来、あれが初めてだったと思います」と言います。
他にも次のような描写が続きます。
「何も考えられない状態になっていた。頭が真っ白になるというのはこういうことなのだろう」
「私は・・・、『死』を恐れている。医師はその職業柄、死に接する機会が多い。ある意味、絶えず死と向き合いながら仕事をしているともいえる。だからこそ、医師は死の恐怖に強いと思っていた。
しかし、実際に対峙する死は自分のものではない。あきらかに距離感がある。私はガンであることがわかった瞬間、その距離感が消えた。死というものが観念的なものではなく、実感として意識せざるを得ない状況になったのである」
「わずかな身体の異変も気になって仕方なかった。
『頭が痛い。ガンが脳に転移したのでは?』
『横っ腹が痛い。肝臓に転移したのでは?』
『咳が出る。肺への転移か?』
『腹痛と便秘がある。ガン性腹膜炎かもしれない』
精神医学でいう心気症である。気にすれば気にするほど、ネガティブな想像力は増幅する。精神科医でありながら、その不安を抑え込むことはできなかった。心気症のメカニズムは理解していたが、どうすることもできなかった」
京都新聞に「わらじ医者、がんと闘う死の怖さ、最期まで聞いて」という題の記事がありました。
「わらじ医者」と慕われ、テレビドラマのモデルにもなった早川一光医師(91)は、老いや認知症を取り上げた著書も数多く、KBS京都のラジオ番組に28年にわたり出演し、講演も精力的にこなしてきたといいます。
多くの人を看とり、老いや死について語ってきたはずでしたが、自身が病気(血液がんの多発性骨髄腫)になると一変、心が千々に乱れ、布団の中では最期の迎え方をあれこれ考えてしまい、眠れなかったと語ります。そして、長年の友人である医師に「僕がこんなに弱い人間とは思わなかった」「初めて病む人の気持ちがわかった。死ぬ怖さを知りました」と嘆いています。
また、消化器腫瘍外科を専門にする船戸崇史医師は、妻に勧められた人間ドックでガンが見つかった時の心境を次のように語っています。
「私は、自分ががんになるなんて夢にも思いませんでした。私はがんに罹る人間ではなく、がんを治す側の人間なのだ、という勝手な思い込みと奢りがあったのです」
「私は現実を到底、受け入れられませんでした。
『違う違う!私じゃない。私ががんになるはずがないんだ!』
がんはもっともっとデリケートな人がなるんだ。繊細でストレスを抱えやすい、そして免疫的にも弱い人が罹る病気なんだ。私なんか正反対な人間なんだから罹るわけがないんだ!
何度そう言い聞かせても、足は宙に浮いている感じでした」
「医師ですからあらかじめ知識はあるのですが、改めて本を開きました。泌尿器系腫瘍の多くが悪性。良性は少ない。放射線も抗がん剤も効きづらく、手術でとってしまうしかない・・・・。あらかじめ知っていることを改めて確認していけばいくほど、心臓がバクバクしました。幸いなことにまだ私は手術が間に合うんだから・・・・いやいや、何を言ってるんだ、私はそもそもがんなんじゃない・・・・いや、がんなんだ・・・・でもきっと悪性じゃなくて良性なんだ・・・・いや、私はそもそもがんじゃないんだ・・・・いや・・・・。医師とて人の子。私は混乱していました」
「告知された日。私は少し泣きました。ふと『死』を意識して震えました。そして気がつくと呆然としているのです。まるで足がなくなったような、ふわふわ浮遊しているような感覚でした」
「多くのがん患者さんを診てきました。落ち込む患者さんには『大丈夫大丈夫』なんて励ましたことも多々ありました。
しかし、いざ自分が患者という立場になってみると、到底大丈夫だなんて思えないのです。がんになって助かるという保証はない、ステージ1でもダメなものはダメになる・・・・やっぱりがんになったらお終いだ・・・・そんな風に思い至って頭を抱えるのです。なんと無責任なことでしょう。どの口が患者さんを励ましてきたのか」