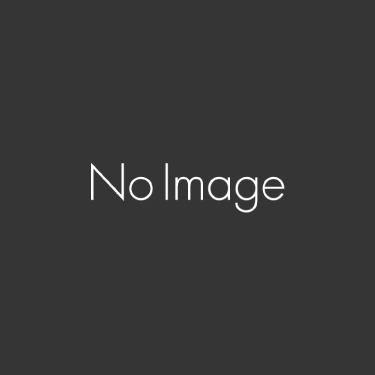「死が怖くない」などと高を括っていた人が、いざ死に直面するとまったく逆の反応を示すことを、こちらで詳しく説明しました。
同じことは死刑囚にもいえます。
残忍な死刑囚は、一見すると死など恐れていないように見えますが、果たしてどうでしょうか。
画家や教師と偽り、2か月足らずの間に女子高生を含む8人の女性を暴行して殺して埋めた大久保清。死刑囚になってからも反省することはなく、「被害者は俺のほうだ」とか「立派に死んでみせる」などと強がっていました。
しかし、死刑当日の朝、拘置所長から「お別れです」と告げられると、恐怖で腰を抜かし、2人の刑務官が腕をつかまえて引きずるようにして連れ出したといいます。そして、教誨師から「何か言い残すことはないか」と聞かれても身を震わせるだけで一言もしゃべれなかったそうです。
元無期懲役囚の合田士郎は、服役中に多くの死刑囚の最期を見ており、その内容を著書「そして、死刑は執行された」にまとめていますが、たとえば次のように書いています。
「出所してから俺は折にふれ、世間に出回っている『死刑に関する本』を読みあさった。
だが、どの本もきれい事ばかりだった。ほとんどの死刑囚は、罪を悔い、深く悟って、静かに処刑されていくかのように書かれている。塀の外からでは想像もつかないような現実だが、官を中心に中から漏れてくる話はほとんど、作られたきれい事だけで塗り固められている」
「午前十時前、死刑囚棟の鉄扉がギーと開かれでもしようものなら、死刑囚棟は、各房の扉越しに心臓の音が聞こえてくるほど、しーんと不気味に静まりかえる。咳音ひとつなく、息をひそめたら死刑囚たちの呼吸音さえ聞こえてきそうだ。ある者は正座し、両手を合わせて神仏に祈り、ある者は体を震わせ、心臓が破れんほどに鼓動を高鳴らせ、必死に死の恐怖におののいている姿が、痛いほどわかる。
鉄扉を開けたお迎え官や特警の靴音が自分の房の前を行き過ぎれば、『助かった』とほっとして、全身から力が抜け、ぐったりした次の瞬間、『今日一日生きられる』と、満面に狂喜の色が湧いてくる。
だが特警の靴音が、とある監房の前で止まり扉を開けようものなら、その瞬間から地獄になる。ほとんどの死刑囚は『死ぬのは嫌だ!』『助けてくれーっ!』と泣き叫ぶ。あるいは『ウォーッ!』と言葉にならない大声を張り上げて暴れまくる。腰を抜かして立たなくなり、瞳はうつろでよだれさえ垂らし、時には小便をもらしたり脱糞までしている死刑囚を見る。
それを、特警が後手錠をかけ、両脇からつりあげ、引きずるようにして、三途の川のトンネルをくぐり、雑木林の中の処刑場へと連行していく。連行されて行った後には、垂れ流された糞尿が、点々と続いていることもある。
静かに処刑されて逝った者などはほとんどいないというのが実情なのだ。死刑執行は、そんな甘く切なく悲しいものではない。まさにこの世の地獄なのだ」
「俺も死刑を求刑されていたときは、何を食ってもうまくなかった。大好物の焼肉を食っても、ゴムを噛んでいるみたいだった。好きなラーメンも、紙でも食っているような気がした」
「誰も知らない『死刑』の裏側」の著者である近藤昭二も、「今日は執行の日かもしれない」というプレッシャーから、食事には不自由しなくても、実際にはどの人も痩せ細り、生彩がなくなると語っています。
また、朝日新聞の取材によれば、大阪拘置所関係者が、オウム真理教の井上元死刑囚らの最後の日々を次のように証言したといいます。
「刑務官は皆、井上と新実は死刑執行が前提で移送されたとわかっていましたから、すごくピリピリしていました。井上は礼儀正しく、死刑執行が近いとは思えない様子でした。
しかし、井上、新実とも日が経つにつれ、顔色は悪くなり、異常に汗をかくなど、精神的に不安定になっていた。
しばらくすると、彼らのいる独房には臭気が漂いはじめた。2人とも毎晩のように失禁するようになり、ズボンや布団を頻繁に取替えるようになっていたのです。死刑の恐怖に怯えていたんだと思います。凶悪事件を起こしたとんでもない連中と思っていたが、2人とも普通の人間だったということでしょう。どうして道を間違えてしまったのか、残念でならない」
市川一家4人殺人事件の犯人である関光彦は、死刑は怖いかと聞かれ次のように答えていました。
「あまり考えません。毎日、灰色の壁に向かって、誰とも話さずに暮らしていると、頭がマヒしてしまうんです。鉄格子のはめられた部屋に入れられたらわかりますよ。1~2年でマヒしてしまいます」
しかし、「ただ、何かあると死と直面することもあります」と言い、その「何か」を具体的に説明してくださいと言われてこう答えています。
「一緒に暮らしている人がある日、突然、連れていかれるんですよ。ああ、死刑執行だな、とわかる。やはり、死ぬことを考えてしまいます。そういうとき、怖い、と思います。死ぬことはやっぱり怖いです」
さらに、オウム真理教の教祖である麻原彰晃・元死刑囚の裁判を傍聴してきたジャーナリストの青沼陽一郎は、麻原が死刑判決を言い渡された時の様子を次のように記しています。
「風貌も随分と変わった。とにかく痩せた。初公判の頃のでっぷりとして、どこかに自信を滲ませた余裕の姿は、跡形もなく消えていた。(中略)
『被告人は、そこに立ちなさい』
小川裁判長が言った。しかし、被告人は椅子の上にじっと固まったまま、無視している。全身の緊張の具合から、それが彼の意思表示なのだと察した刑務官が、直ぐさま彼の腕に手をやった。これを振り払うようにした被告人に、今度は両脇から腕を掴み、立たせようとする刑務官。ところが、教祖はこれにあくまで抵抗する。お尻に力を入れ、身体をくの字にしてまで椅子にしがみついていようとする。いやだ!主文なんて聞きたくない!現実なんて受け入れたくない!まるで駄々をこねる子どもだった。(中略)
こんなに精一杯の抵抗を示したのは、初めてだった。いつもは、刑務官の指図になすがままに従っていたはずだった。なんのことはない。この男、現実をちゃんと把握できていたのだ。それで、こんなに嫌がってみせるのだ。これが、死をも超越したと自負する最終解脱者の正体だった。日本を支配しようとした男の末路だった。あからさまな感情表現に、芸達者の側面も色褪せて消えていく。死刑を怖がる男の本性を、むき出しにしていた」
2021年11月4日、ある死刑確定者2人が、死刑執行の当日通知は違法と提訴したそうです。原告代理人は、「死刑確定者は、毎朝死ぬかもしれないとおびえている。告知当日の執行は極めて非人間的だ」と話しているといいます。
死に怯える人間心理は古今東西どこも同じです。
アウシュヴィッツ強制収容所所長のルドルフ・ヘスは次のような話をしています。
「いくつも前科のある一人の風俗犯が、ベルリンのある家の玄関で、18歳になる娘を誘惑し、暴行したあげくに、絞め殺した。(中略)彼は、銃殺のため、ザクセンハウゼンに送り込まれた。今でもよくおぼえているが、私は作業所の墓地の入り口のところで、彼が車から降りてくるのを見た。せせら笑うように顔をゆがめ、いかにもすさんだ感じの落ちぶれた年輩の男で、まったく典型的に反社会的人間だ。(中略)
私が銃殺を告げると、彼は、真蒼になり、吼えたけり、哀願して、荒れ狂った。それから、今度は、お慈悲を、と叫び出す始末で——じつに嫌悪すべき光景だった。この男も、杭にくくりつけさせねばならなかった。——こうした無道徳な人間どもでも、果して、『あの世』への不安を感じるのであろうか。もっとも、私には、そうとでもしか説明のしようがないのだが」
話はズレますが、大量虐殺に加担したヘスが「反社会的」「無道徳」と批判している点も注目です。己知らずも甚だしいのですが、人間の善悪観はヘスと似たり寄ったりで、この点についてはこちらで詳しく説明します。