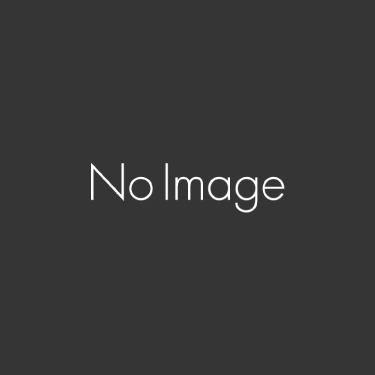死に際の言葉
臨死体験研究を紹介しましたが、臨終に起こる不思議な現象についても近年研究されています。
言語学者のリサ・スマートは、無神論者で合理主義者だった父親が死の間際に「天使を見た」「自分は3日後に死ぬ」などと言ったことをきっかけに(実際に3日後に死んだ)、死の間際の言葉に興味を持つようになったという人です。
1500件以上の「最期の言葉」を分析し、死の間際にいる人が発するナンセンスな言葉(五感で知覚できる3次元の普通の現実では意味をなさない言語)に一貫性があることを発見、著書「人は死にぎわに、何を見るのか:臨終の言葉でわかった死の過程と死後の世界」にまとめています。
夢の中で使われる言語がそうであるように、死に瀕した時の言語もまったく独自な言語だといい、物理的な世界を去る時、「根本的なコミュニケーション手段」に戻るのではないかと推測しています。
「臨死体験者が説明しているように、レイモンド・ムーディはナンセンスについて、生後学んだ言語の世界と死後の領域に存在すると見られるある種のテレパシー的言語の世界の間にある中間的な言語と考えています。言葉を介さないテレパシーの領域こそが、仏教指導者を含めた神秘主義者が語る、言葉では言い表せないものの領域なのです」
「言語学的観点から見ると、最後の日々には言語機能が崩壊すると考えられるにもかかわらず、実際にはより複雑な言語が観察されるのです」
「あの世との境に到達した人とこの世への門が背後で閉じる音を聞いたばかりの幼児は、同じように物事を理解しているのかもしれません。きっとどちらも私たちとは違った方法でコミュニケーションをしたり、知覚したりできるのでしょう」
「コミュニケーションはテレパシーの形で子供の頃に始まり、私たちが死ぬ時には非言語的な『魂の言葉』に回帰していくと考えることができます」
「末期意識清明(死ぬ間際に突然意識がはっきりする現象)は患者の言語中枢が破壊されていても起こることが知られており、それまでまったく動けなかった患者の運動能力が回復したという事例もあります。これは医学の中でも異例の分野で、今まで数々の事例が集められてきたにもかかわらず、まだごくわずかしか研究されていません。こうした事例は、脳と自己はそれぞれ独立したものであり、脳は明らかに死にますが、自己は死なない可能性を示唆しているのかもしれません」
「亡くなる人が口にする言葉に目を向けると、言語はしばしば徐々に変化する連続体であることがわかりますが、これは脳の機能と関連しているようです。文字通りの言語から比喩的な言語、理解不能な言語、そしてついには言葉を介さない、テレパシーによるコミュニケーションにまで発展するのです」
「私たちが死ぬ時、ほとんどの人は文字通りの現実を表す意味のある言語を離れ、より意味のない、非感覚的あるいは多感覚に基づく意識へと移行します。そして、臨死体験者の言語パターンもこれとよく似た軌跡をたどるのです」
「人生の終わりに見られる言語の変化は、ナンセンスではなく、新たな感覚が発達するプロセスの一部なのかもしれません」(リサ)
死に際に地獄を見た例
ボルテールは臨終に、「そこに恐ろしい鬼がいる。地獄が見えてきた、助けてくれ」と言いましたが、臨終に「地獄を見た」という人も少なくありません。
モーリスの著書にも、ある医師の報告として臨終の地獄体験の事例が紹介されているので引用します。
「この患者が、これだけの世間的な成功を成し遂げた立派な人であるのに、こんなに意気消沈しているなんて誰も想像できなかったろう。彼は私に、生がせいぜい与えてくれる以上のものを自分は探求しつつあるのだと語った。私は一体彼が何を言おうとしているのか理解できなかった。実はもっと腰を据えてよく傾聴すべきだったといま後悔している。
というのは、実にその晩、私はビバリーヒルズの彼の家へ来てくれと家人から呼び出されたのだ。急いで駆けつけてみると、彼は床に倒れていた。そして、助からなかったのだが、死ぬ少し前、しばらくではあるが意識を取り戻し、私の蘇生術に反応を示した。痛いかと聞くと、彼は首を振るだけだ。私は彼に、皆であなたを救命しようと頑張っているのだと言った。彼は頷いた。最期の言葉は、『私は怯えているんです。どうか私を地獄へ戻さないでください。私には今それが見える・・・・』というのであった。私は彼が何を見たのか、わからなかった」
死の直前に過去の行いが走馬灯のように脳裏をよぎることを紹介しましたが、ベルグソンなど、この行いが悪い行いであると主張する人もいます。