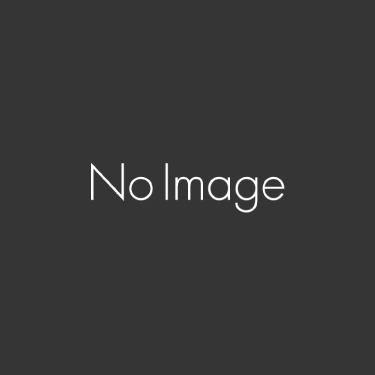死の恐怖を感じただけでなく、その恐怖が続かない心理も描写している事例を1つ紹介します。
〇本の内容
アメリカの政治コラムニスト、スチュアート・オルソップは、1971年に急性骨髄性白血病(AML)と診断され、その体験を著書「最後のコラム」に綴っています。AMLは発病後1年ほどで死に至るとされており、死を間近に感じた人間がどういう心理になるか詳細に描写しています。
・処刑の一時停止
本の原題は「Stay of Execution(処刑の一時停止)」となっていますが、この点について、この本の訳者である崎村久夫氏は次のように言います。
「原題にこめられているのは、処刑、つまり死を待ちながら、という思いであろう」
「オルソップの場合は、当初、AMLと判定されたが、病気が典型的な経過をたどらぬため診断が二転三転し、適切な治療法も見出されないまま入院と退院を繰り返すことになる。その間に、迫りくる死を予期しつつ書かれたのが本書である」
・最大の混乱
次のように、今回の病は人生最大の混乱だったとオルソップは言います。
「私のこれまでの生涯が混乱そのものだったのだが、初めて急性白血病と診断されて以来味わった、地獄と天国と煉獄の間をさまようような奇妙な危険ほどの混乱はなかった」
〇性格
オルソップ家は、一族から2人の大統領(セオドア・ルーズベルトとフランクリン・ルーズベルト)を出している、いわゆる上流階級の家柄で、そのためもあってか、オルソップはかなり楽観的な性格です。たとえば戦争については次のように言っています。
「戦争にはもちろんおぞましくも悲しいことがたくさんあるが、運さえよければ、面白いこともいっぱいある。戦争でできた友人は、平時に知りあった友人より親密な友となることが多い。
それにまた、子供たちは自分自身を見つめ、自分をより深く知る機会を逃したともいえる。なぜなら、戦争は自分自身を知る、またとない機会だからである。そのほか、もっと有益ななにものかを取り逃している可能性もある」
・病気への偏見
また、「貧乏人は頭が悪いから貧乏なのだと思っている金持ちのように、病気になるのは意志が弱いからだ、という考えにとらわれがちだった」と言い、妻が病気になったり、出産で入院したりしても「そう親身に心配してやることはなかった」といいます。
そのため、今回の発病について「今自分が本当に病気だとは、どうしても信じられなかった」と言います。
〇死の恐怖
まず、体調に異変を感じ、診察を受けるまでの流れが書かれています。
楽観的な性格のオルソップですが、癌ではないかという疑いが確信に変わるにつれ恐怖が生じています。そして、医師から白血病と告げられた時の恐怖を次のように語っています。
「私の心の中に、恐怖が黒々とした穴をあけたのである」
「死が近いことを初めて宣告されたときには、私は逃げ場のない絶望感に捉われた」
「この五十年来初めて、私は泣き出しそうになった。そのことに私はひどく驚き、狼狽した。私は、男が人前で泣くなどとは最も軽蔑すべきことであり、男らしくないことの証拠である、と信じるべく育てられてきた。私は、かがみながら小さなバスルームへ逃げこみ、ドアを閉め、声を消すために水を流しながら、便器の上に腰かけて思いきり泣いた」
他にも次のような描写が続きます。
「すっかり惨めな気持ちになっていて、長い生涯で初めて、手帳にものを書く意欲を失っていた」
「家族の顔を見ることも、もうできないし、友人たちと談笑もできない。春が来ても、もう何も感じないのだ。恐ろしい孤独と傷心、まる裸で、救いのない思いが私を襲った」
「ダモクレスの剣を頭上に感じ、心の奥では恐怖が膨らんでいる」
「手術不可能の癌にかかった人間は、ワラをもつかむ気持ちになる」
〇安心
恐怖だけが常に絶え間なく続くのではなく、安心する心も生じています。
・生きられる喜び
病態が改善に向かっていることを知った時、次のように、その喜びは非常に大きなものだと言っています。
「一度は死に直面した私が、今や生きるほうに向かったのである。これがどんな気持ちのするものかは、こうした一種の処刑延期を経験したことのある人にしかわかるまい。
少なくともしばらくの間は、どんな麻薬からも得られない特別な幸福感が生じるのだ。あらゆるものが色鮮かに見え、生活は喜びに満ち、親しい友がこれまで以上に親しく感じられるのである。血液の測定値が上昇し、それまでのめり込んでいた絶望の沼から這い上がるにつれ、私は、『生』というものを、自分の手で触れ、見、嗅ぎ、味わい、そして胸の奥深く吸いこみたいと思った」
・防御のメカニズム
また、どれほど強い恐怖を感じても長くは続かず、次第に和らいでいったといいます。この理由について、「死が間近に迫っていると告げられた最初のショックが過ぎると、一種の防御のメカニズムが生じてきたからである」と分析しています。
ここで、オルソップが戦争中に弾丸の標的となった時の体験を話しています。銃弾が近くに撃たれ、自分が標的であるにもかかわらず、「銃弾や地雷に当たって死ぬのは誰か他人で、自分じゃない」という考えがあったといいます。
「こうして、耐え難いことも耐えられるようになり、死についてあまり考えることなく、死と共に暮らすことを、人は学ぶのである」
そして、次のように死の恐怖が続かず安心する心理についても繰り返し説明しています。
「(病を通してわかったこととして)人間は四六時中怖れ続けてばかりはいられない、ということである」
「手術不可能の致命的な癌に冒されていると知ったときの最初のショックがやわらぐと、自己防衛の心理作用がメカニカルに働き出したのだ」
「『普通の』生活を送っているうちに、死への恐怖が薄らいだのである」
「私が恐怖でとり乱さなかった最大の理由は、いわく言いがたい不思議な心理プロセスが知らず知らずに進行していたためだと思う。この本の中で、なんとか表現しようとしてきたことだが、それは人が死と折り合いをつけてゆく適応のプロセスなのである」
次第に治る見込みはないと確信し始めていたオルソップでしたが、「入院したてのころに比べると、その半分も苦にならなくなっていた」と言います。
「死が陳腐で退屈なものに思えるようになってきた」
「病気になる前は、死について考えたことなどほとんどなかった。死を考えはじめると、それによって学ぶこともあった。この期間に私が学びえたものは、健康な人間が死について考えたとしても、とても理解しつくせぬたぐいのものだった。若く、気力に溢れ、健康を謳歌している人にとっては、死はいまわしい観念であるばかりでなく、本質的に信じられぬものなのだ。この、死が信じられぬということが、防御のメカニズムとして作用する。戦場の兵士が正気でいられるのは、まさにこのためである」
・恐怖と安心を繰り返す
このように、悪化したと思っては恐怖が増し、しばらくして安心するという具合に、恐怖と安心が交互に繰り返しやってきて一喜一憂している姿が書かれています。
「ときには、自分が手術不可能の癌患者だということを忘れていられる時間もあったが、突如として逃れようのない現実に圧倒されることもあった」
「(死の恐怖は)ときには、ほとんど感じとれぬくらい小さくなることもあったが、ふたたび深い懐疑心を伴って戻ってくるのだった」
「ふたたび元気になり、病気が癒えたと思ったとき、死について考えることは、またまた恐ろしいものとなった」
〇罪悪感
罪悪感についても変化が生じています。
・生き物に対して
オルソップは鳥のウズラを撃つのを趣味にしていましたが、それに対してはあまり罪悪感を感じていませんでした。
「ウズラ撃ちでは、心は全然痛まなかった。ウズラは小さなニワトリのようなもので、食用のニワトリを殺すのはどうということもないからである」
また、ハト撃ちもしていましたが、ハトに対しては罪悪感があったようです。
「ハトは小さなニワトリではない。ピンクの腹と青灰色の翼を持った、美しい野鳥である。ハトはまた平和のシンボルでもある」
そして、次のようなことも言っています。
「こうした趣味に私の子供たちを引き込むことができなかったのは、かえすがえすも残念である。子供たちは、生き物を殺すのには反対だと言う。彼らの考え方も、それなりに正しいのであろう」
こんな考え方を持っていたオルソップでしたが、発病してから次のような変化が生じています。
「病状が重くて死の恐怖におののいていたときは、どんな生き物も殺す気になれなかった」
「いやな夢を見た。中でも恐ろしかったのは、私が幼い自分の子供を撃って、傷ついたハトのように、子供が地べたでバタバタともがいている夢だった」
「私は散弾銃で小鳥を撃ったり、蚊針で小魚を釣り上げたりするのがマニアックに好きである。こうした小さな生き物を殺すことに、かすかなやましさをおぼえるという、矛盾する気持ちもつねづね抱いていた。
この気持ちが、発病後いちだんと強まってきたのだ。特に小鳥の場合がそうなのだが、最近では、小魚が手の中でもがき、まばたきしない目でじっと私を見つめたりするとき、かすかな罪の意識すらおぼえるようになってきた。これまでに殺した幾千もの小鳥や小魚が、いつの日か復讐をしにやってくるかもしれぬという考えが、ときおり胸をかすめたりするのだ」
〇死は必ずくる
オルソップは言います。
「若いうちは、死がいつかくるなどとは考えてもみない。しかし、そのときは必ずくるのである」
また、本の最後は次の言葉で締められています。
「人間には生きるべきときがある。しかし、同様に、死すべきときがある。私には、まだそのときは訪れていない。が、いずれそのときがくる。何人にも、そのときは来る」
そして発病から3年、正確な病名が決まらないまま感染症による肺炎を併発し、3回の開胸手術を受けたのちオルソップは60歳で死にました。