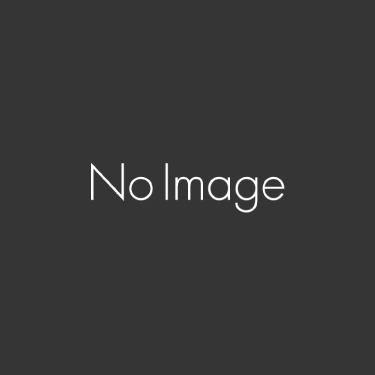死は信じられない
「死が怖い」と悩んでいた人に対して、「死なんて有り得ない心配せずに、もっと楽しいことを考えよう」とアドバイスしていた人がいました。
古代インドの叙事詩マハーバーラタには、ヤクシャという精霊が賢人ユディシュティラに「最大の脅威は何か」と尋ねる場面があります。いわく、「日々無数の人々が死んでいるのに、私たちはまるで不死であるかのように生きていること」
人間は、自分の死は信じられません。
絶対に死なないと思っている
誰もが「自分もやがて死ぬ」と言いますが、腹底を尋ねれば「自分だけは絶対に死なない」と思っているのです。
死は他人事
日々、膨大な数の人が死んでいます。「年年歳歳 花は相似たり 歳歳年年 人は同じからず」という詩の通りです。
日本では年間約120万人の死者がいます。
これは約3,300人/日、約140人/時、約30秒に1人が死んでいるということです。
世界では年間約6400万人の死者がいます。
これは約175,000人/日、約7,300人/時、約1秒に2人が死んでいるということです。
こういう事実を目の当たりにして人間は驚くかというと、そうではありません。死ぬのは他人であって、自分とは関係ないと思っているからです。
永遠に生きられる
「今日は死なない」と思っているはずです。頭(意識)では「今日死んでもおかしくない」と思っていても、本心(阿頼耶識)は「少なくとも今日は絶対に死なない」と思っているでしょう。これから説明していくように、いくつになっても、またどんな状況に追い込まれても、腹底は「今日は死なない」と思っています。つまり、腹底では永遠に「今日は死なない」と思っているということであり、永遠に生きられると思っているのです。
「人は自分のことを死なないと勘違いするようになりました。そんなことはない、と仰るかもしれません。人間が死ぬということが知識としてはわかっていても、実際にはわかっていないのです」(養老孟司)
「人は、『人は必ず死ぬ』と思っていても、どうしてか自分だけは絶対死なないと思いたいと思っているようです。よく考えてみると、これは不思議なことです。しかし、これは多分、単に人は死ぬのが怖いからではないでしょうか。自分が死ぬことなど、思ってみるだけでも恐ろしいので、それ以上深く追求するのをそこでやめるのです。考えられないのではなくて、考えるのをやめる、のです。それについて考えるのをやめたことは、もはやそこには存在しないことになる。そこで人は、人は必ず死ぬけれども、自分だけは絶対に死なないと、死ぬまで思っていることになる。これは、幸福なことでしょうか。むしろ、不幸なことではないでしょうか。少なくとも私にはそう思われます。自分が死ぬということを恐れて生きていることは、生きていること自体が常なる恐れなのです」(松野哲也/国立感染症研究所室長)
「わたしたちは躍起になって死を生活から分離しようとしてきた。だが、その結果、わたしたちにできたことといえば、混乱した信念や自分でも半信半疑な疑問だらけの生命観を構築したことぐらいである。こうした混乱は、マスコミが偶発事故による死に重点を置き、それを大きく報道するところにもはっきりとうかがえる。飛行機の墜落事故や火事の生々しい詳報や、休日や週末中の交通事故の死傷者数の克明な報告に、関心がもっぱら集中する。ここで暗に込められているのは、死がわたしたちの内側に抱える何かではなく、『よそで』起こる何かであり、別の場所で待ち構えている何かだ、という含みである。事故による死が、死亡率の重大な部分を占めていると信じ込むように仕向けられてきたわけだが、現実は違って、最も機械化が進んだ社会でも、事故による死亡率は全体の5%にも満たない。
こうした事故死への過剰な関心は、自然死への不十分な関心を隠蔽してきたように思われる。どこかよそで起こる、回避可能な死ばかりを都合よく強調して、ひとりひとりの中にある、不可避な死からわたしたちの目を逸らしてきたのだ」(ライアル・ワトソン/生物学者)
「われわれがいくら自分の死を想像しようとしても、それはあくまでも生きている第3者という立場からのものにすぎない」
「人間というものはすべて、自らの不死性を潜在的に確信している」
「死について想像しようとすると、自分が傍観者だとわかる」(ジークムント・フロイト/精神科医)
「健康な人間が、生に対して持っている安心感は、よく考えてみると、驚くべく強力なものである。そのおかげで、人間は平静な気持ちで生きていられる。理論的には、死刑囚と同じ立場にありながら、死の恐怖に心をおびやかされることなく、生きてゆくことができるのである」
「生きている人間の大部分は、死のことなど忘れはてている。平生、健康なときには、死に煩わされずに生きてゆくことができるからである。生きているということを少しも疑わず、これに自信をもっている。それは、おそるべき自信である。まさか自分が死ぬとは思わない」
「一般的な概念としては、人間に定命のあることを認める。自分も、やがては死すべきものであることを、十分に承知している。しかし、それは、一般的な理論としてであって、現実には、知らず知らずのうちに、自分だけを例外に置いている。死をわが身に即した事実として考えることは、どこまでも避けようとする。もっと具体的に言えば、自分はまだ死なないと考える態度を、つねに持ち続けることになる。病気が重く険悪になって来ても、もう一度は回復すると信じる。まだこのままでは死なないと考える。いよいよ危篤になり、死期が間近に迫れば迫るほど、そのまだを心の中で叫ぶ。意識のある限り、その『まだ』を主張し続けるのである」
「人間の日常生活は、1つのごまかしの上に営まれている。これは、少しも悪意のないごまかしである。しかし、最も深刻なごまかしであるというよりほかはない。このごまかしは、現代人において、ことに著しい」(岸本英夫)
体験者の声も何人か紹介しましょう。
「誰でも死ななくちゃいけない。でも私はいつも自分は例外だと信じていた。なのに、なんてこった」(ウィリアム・サローヤン/小説家)
「ワイドショーなんかのテレビを見ていると、顔を並べて適当なことを口にしている連中が、なんて馬鹿なヤツらだろうって思うね。いい歳をして、テレビで一生懸命になっているフリをしているけど、自分らがいざ死ぬってときに、どうにもならないんじゃないかってさ、おせっかいながら心配したよ。今は他人事でも、いずれ自分が待ったなしの立場に置かれるのは間違いない。そのとき、あんたたち、どうするんだよ」(ビートたけし)
「私たちだっていつ死ぬかわからない。その晩にも死ぬかもしれなかった。地震、自動車事故、心臓発作、何が起こるかわからなかった。誰もがいつも死にさらされているのだ。でも、わたしは別、わたしは若くて、わたしの人生はこれから、わたしはずっと、永遠に生きつづける、そうわたしは思っていた」(スーザン・ストラスバーグ/女優)
「みんな死ぬのをいやがりました。私たちは呻き声、叫び声の1つ1つに答えました。ある負傷者は死ぬんだと感じた途端、私の肩にすがりついたんです。抱きついて放そうとしない。看護婦でもそばにいれば命が消えてしまわないかのように。あと5分、あと2分でいいから、と頼むんです・・・。人間は死んでいきながらも、やはり自分が死ぬということが信じられないんです、自分が死ぬって思わない」(「戦争は女の顔をしていない」より)
「俺は死ぬ、と思ったことはこれまでに何度もあった。だが死ななかった。そうするうちに死ぬかもしれないという思いはいつしか消えていった。蒸発してしまった。しばらくすると、あいつらには自分を殺せないと考えるようになった。俺たちは死なない。俺たちは無敵だ。自分には守護天使がついていて、自分はシールで、運がよくて、とにかく自分は死ぬはずがない」(「ネイビー・シールズ最強の狙撃手」より)
東池袋自動車暴走事故で妻と娘を失った松永拓也さんは、「私はこの立場に立つまでは、交通事故はテレビの向こう側のお話で、自分には関係ないって、正直思っていたんです。でもやっぱりそうじゃなかったんですよね」と語っています。
狂歌師の大田南畝は「今までは 人のことだと 思ふたに 俺が死ぬとは こいつはたまらん」という辞世の句を詠みました。
「死は怖くない」と思わせる心がある
「絶対死なない」と思っているわけですから、死が怖いと思えません。この強力な妄念が「死は怖くない」と思わせようとするのです。
海兵隊員としてベトナム戦争の前線で戦ったアレン・ネルソンは、著書「『ネルソンさん、あなたは人を殺しましたか?』 ベトナム帰還兵が語る『ほんとうの戦争』」の中で次のような体験を語っています。
「頭がない死体もめずらしくありません。そんなときは頭をさがさなければなりません。頭を運ぶときは髪の毛をつかんで、ぶら下げて運ぶのですが、あるとき、髪の毛が焼け落ちてつかむところがない頭が落ちていました。私は、棒切れを拾うとそれを死体の耳の穴につっこんで持ち上げ、運びました。戦場では、そんなふうに、死体に対して何も感じないようになるのです」
東日本大震災による津波で、手足がもがれた遺体が流れてくるのを見て、「最初は物凄い恐怖だったが、毎日毎日流れてくるから見慣れてくる」と語っていた人もいました。
現地を取材した作家の石井光太も著書「遺体―震災、津波の果てに」の中で、「最初は誰もが遺体が床に横たえられているだけで慄いていたのに、数が増加するにつれて見慣れた風景となってしまい、モノとしてしか感じられなくなった」と描写しています。
戦争にしても震災にしても悲惨な描写の連続ですが、ずっと読んでいると慣れてしまっている自分に気づきます。
人間は、死の恐怖を感じ続けることができません。
地震になっては恐怖し、助かっては恐怖が薄らぎ、ウイルスが蔓延してはまた恐怖し、助かっては恐怖が薄らぎ・・・・という流れを死ぬまで繰り返し、最後は死に飲まれて地獄に堕ちていくのです。
いつでも死は突然
「自分だけは絶対に死なない」と思っているところに死がやってくるわけですから、いつでも死は突然に感じます。
歌人の在原業平は、「つひに行く 道とはかねて 聞きしかど 昨日今日とは 思はざりしを」という辞世の句を詠みました。「いつかは自分も死ぬとは知っていたが、昨日今日のことだとは思いもしなかった」という意味です。
「死は、突然にやって来る。思いがけないときにやって来る。いや、むしろ、死は、突然にしかやって来ないといってもよい。いつ来ても、その当事者は、突然に来たとしか感じないのである。現代人の場合には、ことにそうである。平生、死をまったく忘れているだけに、死に直面すると、あわてふためいて、なすところをしらない」
「死は、大きな別れである。すべてのものに別れを告げる。徹底的な別れであるから、これは容易なことではない。もし、死が現実にやって来る前に、十分に心の準備をしておかなかったら、とてもそれに耐えることはできないようなものである。しかし、普通の場合、人間は、驚くほどそのための心の準備をしていない。それで、死は、いつでも不意打ちのような形で襲ってくることになる。それに対して人間は、取り乱して狼狽するだけである」(岸本英夫)
念のため言いますと、心の準備などできず、できたと思っている人は自惚れているだけです。
怒りが出る
「死なんていう酷い結果を受けるような悪いことはしていない」という具合に怒りも出ます。ガンが消えて「無罪放免だ」と言って喜んだ人がいますが、死を回避できると罪が帳消しになったようにも思います。
企業や病院等でリーダーシップ研修を行う傍ら、ボクシングジムのトレーナーとしても活動している刀根健は、末期の肺がんを宣告された時の心境を著書の中で次のように綴っています。
「僕よりも悪いことしているヤツ、いっぱいいるじゃないか!なんで僕なんだ!不公平だ!僕以外にもいっぱいいるじゃないか!なんで僕なんだよ!いやだ、いやだ、いやだ、死にたくない、死にたくない、死にたくない!頭の中を何かが暴走していた。心臓が高鳴り、脈拍が速くなる。真っ暗な暗闇から何かが僕をつかみ込んで、漆黒の穴へ引きずり込もうとしていた。いやだ!いやだ!いやだ!抵抗むなしく、ぐるぐると回転しながら底なしの穴へ落ちていく。死にたくない!怖いよう!」
死の恐怖を感じれば、誰でも自分は弱い人間だとわかります。
「僕は自分が強い人間だと思っていたが、真実は違った。僕は弱かった。すぐに弱気になる。すぐにネガティブに巻き込まれる。すぐに死神が頭の中でしゃべりだす。弱い、本当に弱い。自分が強い人間だと思っていたのは、弱い自分を隠すために作り上げた虚像だった。僕は必死で虚像にエネルギーを投下し、虚像を強化してきた。講師もそう、心理学もそう、ボクシングもそう。それを使って弱い自分に直面しないようにしていただけなんだ。そしていつのまにか、虚像を自分自身だと思い込んでしまったのだ。虚像は弱い自分を守るための鎧でしかなかったのに。そして僕は、虚像の自分を生きていた愚か者にすぎなかった」(刀根)
死の直前で気づいては遅いので、死ぬ前に、特に平生元気がいい時にこのことに気づくことが重要です。
キューブラー=ロスは次の「死にゆく過程の五段階説」を提唱しました。
第1段階(否認)
大きな衝撃を受け、「何かの間違いだ」と死の事実を否定する
第2段階(怒り)
死が否定しきれない事実だと自覚した時、「なぜ私がこんな目にあうのか」と怒る
第3段階(取引)
「何でもするので助けてください」と神と取引する
第4段階(抑うつ)
取引も無駄だとわかり、絶望し、抑うつ状態になる
第5段階(受容)
最後は、死を受容し、心が安らかになる
5段階目の「死の受容」ができないことは何度も説明しましたが、前4段階については仏説と共通点があります。
6万人以上の市民を虐殺したルーマニアのチャウセスク大統領は妻と共に公開処刑されました。その時の動画は今でも見ることができます。彼は死の前に「私は犯罪人ではない、大統領だ」と叫びましたが、抵抗空しく処刑されました。悪人であるのにその自覚がない男の悲惨な末路ですが、どの人間の最期も彼と大差はありません。
死なない理由を見つけようとする
「あの人は死んでも仕方ない事情があったのだろう。でも自分はそうではないから大丈夫」という具合に、自分に都合がいい理由を見つけて落ち着こうとします。この心理はどれほど年を取っても、どんな状況に置かれても働きます。
「病気で死んだ人がいる」と聞けば、「あの人は不摂生だったから。でも私は健康に気を使っているから大丈夫」と安心し、「100歳で死んだ人がいる」と聞けば、「あの人はもう年だから。でも私はまだ99歳だから大丈夫」と安心するという具合です。
自分が死なないことを裏づける証拠のためなら、心は世界中を飛び回り、どんな些細なことでも飛びつこうとします。
死ぬまで死なないと思っている
死は、いくら考えてもわかるものではありません。人間は死ぬまで死がわからない生き物といえるでしょう。体験するまで、死は想像することさえできないのです。
「バカは死ななきゃ治らない」という諺のようなものがありますが、死が信じられない人間の本性を的確に表現しているといえます。
人間はすぐ死を忘れる
歌手のマドンナはこんな話をしています。
「エイズで亡くなった男性をこの目で六人見たわ。彼らの最後を看取ったの。そのたびに『生きることや人生の意味って何?』って思ってた。それから子供ができて、彼らに強い愛情を感じると・・・この疑問は棚上げにされて、愚かにも答えを知りたくないって思うようになるのよ」
人間はすぐ死を忘れます。幸せというのは、死苦を始め、無数の苦悩が迫っていることを忘れさせる麻薬のようなものなのです。
「人生最大の喜びを手に入れること。それはすなわち危険な生活を意味する」(ニーチェ/哲学者)
「人間が幸福の夢を追うときに犯す大きな過失は、人間の生来から備わっているあの『死』という弱点を忘れてしまうことだ」(シャトーブリアン/政治家)
「残水の小魚 食を貪って 時に渇くを知らず」(吉川英治/小説家)
やがて滝つぼに堕ちてしまう船の中で、ドンチャン騒ぎをしているようなものです。船の中にいる人は、全体を俯瞰することができないので気づかないのです。
「人間は生まれたときから、滝つぼに連なる川の中を流れている。上流に居る間は、滝つぼの存在に気がつかない。しかしあるところを超えると、急に流れが速くなって後戻りできなくなる」(今野浩/東京工業大学名誉教授)
また、溶けかけている薄い氷の上を安心して歩いているようなものであり、鋭い刀の上の甘い蜜を夢中で舐めているようなものです。人間は、自分が置かれている状況がまったくわかっていません。
「人間の、自分の生命に対する自信と安心感とは、心の表面に張った薄氷のように薄い意識の層にすぎない。それを一枚めくれば、その裏には危うい限りの生命の現実がある。死は、いつ襲いかかってくるかわからない。死は、至るところで牙をみがいている。まっくらな口を大きく開いて、忍び寄ろうとしている。ただ、人は、薄氷の上をわたりながら、自分の踏んでいる氷が、そのように薄いものであることを感じないだけである。いつ崩れ始めるかわからない安心感の上にあぐらをかいて、たよりにならないものをたよりにして生きているのである」(岸本英夫)
シチリアの僭主ディオニュシオスの富や権力を、延臣のダモクレスは羨み称えました。それを聞いた僭主は、ある宴の席でダモクレスを王座に座らせました。ダモクレスが席に着き、ふと上を見上げると、頭上には鋭い剣が細い糸で吊るされていました。王者には常に危険がつきまとっていることを教えた有名な「ダモクレスの剣」ですが、この話のように、どんな人も地獄と隣り合わせなのです。
正月気分で浮かれた町を、一休が歩いていました。しかし、その姿に皆ギョッとしました。一休は、ドクロが刺さった竹竿を持って歩いていたのです。
「このとおり、このとおり。ご用心、ご用心」
こう言いながら一休は、町中の家々の戸を叩いてまわりました。それを見兼ねた人が、「一休さま、せっかくの楽しい正月なのですからおやめください。正月は目出たく祝うものです」と注意しました。
すると一休は、「正月といえど死は待ってはくれない。このしゃれこうべを見たまえ。正月を祝っていた人が、今は目が出て穴ばかり残っている。これを目出たしというのだ」と言って、また家々をまわっていったといいます。
一休の歌に「門松は 冥土の旅の一里塚 めでたくもありめでたくもなし」というものがあります。
門松はめでたいものとされていますが、それを立てるということは年を取ったということであり、死に近づいたという標示とみることもできます。それを一休は、このように詠んだのです。一休が警告しているように、めでたいことなど何もないのです。
顛倒の妄念
「無常」が真実であるのに、「常」と見てしまう妄念が人間にはあります。他にも「苦」に対して「楽」、「無我」に対して「我」、「不浄」に対して「浄」と見てしまう妄念があり、「常」を含めて四顛倒といいます。
この強力な妄念があるため、どんなに強い恐怖を感じても、その恐怖は続きません。そして、絶体絶命の状況に置かれても「自分だけは絶対に死なない」「死は怖くない」と思ってしまうのです。
また、肉体は入れ物であり本体は魂(阿頼耶識)であることを頭ではわかっていても、それもすぐ忘れてしまいます。
「地球と私たちが呼んでいるこの学校の持つ問題の1つは、私たちは物質的な体ではなく、魂なのだということを思い出すのが、とても難しいことです。私たちは常に、この3次元の世界の幻想や錯覚に惑わされています。お金、権力、名声、物の所有、蓄積、快楽などは非常に大切で、時には人生の目的でさえある、と教え込まれています。また、幸せになるためには、他の人々から好かれ、尊敬されねばならないと教育されています。1人でいるのは惨めだと、教え込まれてもいます」(ブライアン・ワイス/マイアミ大学医学部精神科教授)
今日、妙好人(仏教の篤信者のこと)と評される浅田正作という人は、「やどかりが自分の殻を自分だと言ったらおかしいだろう。私は自分の殻を自分だと思っている」と表現しました。
仏説譬喩経には、この妄念を含め、人間の実相を教えた次のような話があります。
ある強盗が長者に目をつけ近づきました。すぐには襲わず、信用させるまで従順に働くフリをしていました。長者はすっかり信用し、いよいよ機会が訪れたと思った強盗は、長者を殴りつけ、耳や鼻、手足、舌を切り、体の皮をはぎ惨殺してしまいました。
これは、修行道地経にある話ですが、このたとえのように、妄念に騙されて最後は惨殺されて地獄に堕ちてしまうのが人生なのです。そのため経には「人間は笑いながら地獄に堕ちる」と説かれています。
・悪の根源
この強力な妄念は阿頼耶識から生じるものですが、根源を辿っていけば、正確には末那識が阿頼耶識に作用して生じるものです。
阿頼耶識が最も深層の心ですが、その1つ上の第7番目の層に末那識という心があります。末那識は阿頼耶識を布団のように覆っており、本当の姿を見えなくする働きがあります。この妄念から無数の悪が生み出されるため、末那識は悪の根源というべき存在です。
世間というのは、この妄念によって麻痺した人間が集まった世界です。「自分だけは死なない」「人生は楽しいところ」「人間は美しい」といったことを自分も信じ、人にも信じさせようとします。そして、この妄念に反して「死」や「苦」を主張する人を忌み嫌うのです。
第2巻で説明した通り、人間は急がなくてもいいことを急いでいますが、それは死が遠いからです。死が近ければ急がないことを急いでいるのです。それだけこの妄念は強力ということです。
・頭下足上
妄念にとらわれているため中阿含経には、「足を上、頭は下には、かの人は地獄に堕つる」と説かれています。
ある時、妙好人として知られる庄松が寺の中で逆立ちしていました。
「庄松、そんなことしてるとケガするぞ」
それを見た人たちが庄松をからかいました。しかし、庄松はこう言い返しました。
「お前たちが地獄に堕ちる姿を真似しているんじゃ」
経には、顛倒の妄念があるために真っ逆さまとなって人間は地獄に堕ちると説かれていますが、それを庄松は教えたのです。
・常に戒める
蓮如は「今日の日はあるまじきと思え」と言いました。
「今日死んでもおかしくない」「明日があると思うのは間違い」ということは、頭ではよくわかるでしょう。しかし、本心ではそうは思っていないため、常に自分を戒めて死を近づける必要があります。
親鸞は9歳の時、出家するために京都にある青蓮院へ行き、天台宗の僧侶、慈円と会います。
夜遅くのことだったので慈円は、「今日は遅いから明日にしてあげましょう」と言いました。ところが親鸞は次の歌を詠んで返しました。
「明日ありと 思う心の仇桜 夜半にあらしの 吹かぬものかは」
「明日があると思う心は儚く散る桜のようなものである。夜中に死がやって来ないと誰が言えようか」という意味です。
「今日死んでしまったら、明日まで生きていられないではないか」という抗議の歌です。
ちなみに、「桜」はあっという間に散ってしまうので無常の代名詞のような花で、次のように仏教ではよく使われます。
「散る桜 残る桜も 散る桜」(良寛/禅宗僧侶/辞世の句)
「死に支度 いたせいたせと 桜かな」(小林一茶/俳人/辞世の句)