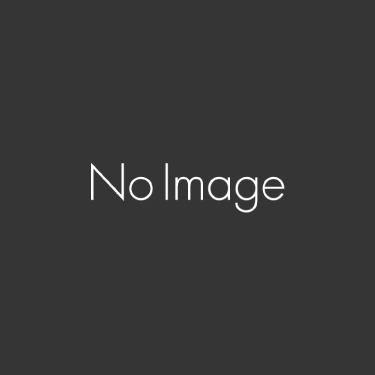仏教の生命観
まず、仏教の生命観を紹介しましょう。仏教では次のような生命観が説かれています。
・六道輪廻
科学では38億年前に生命が誕生したといわれていますが、仏教では、始めの無い始めから、終わりの無い終わりに向けて、車の輪のように転生を際限なく繰り返していると説かれます。有名な六道輪廻です。
六道とは、六趣または六界ともいい、次の6つの世界を指します。
地獄界:苦しみしかない世界で、六道の中で最悪の世界
餓鬼界:餓鬼が住む世界で、飢え苦しむ世界
畜生界:犬や猫、虫や魚などの世界
修羅界:修羅が住む世界で、争いが絶えない世界
人間界:私たち人間が住む世界
天上界:天人が住む世界で、六道の中で最も楽しみが多い世界
・四生
生物の出生方法を四種類に分類したものを四生といいます。
化生:業の力から出生するもの。天人や幽霊など
湿生:湿気のある中から出生するもの。魚類・両生類など
胎生:母胎から出生するもの。人類や獣類など
卵生:卵から出生するもの。鳥類など
化生以外は科学でも明らかになっていることもあり、わかりやすいでしょうが、化生はわかりづらいでしょう。
多少なりとも化生をわかりやすく説明するなら夢のようなものです。夢の中では、人間にしても動物にしても、突如現れたり消えたりします。このような生まれ方を化生といいます。
・生命は同根
そして、生命は同根と説きます。
歎異抄には「一切の有情は、皆もって世々生々の父母兄弟なり」と説かれています。これは、「すべての生物は、これまでの無限の生と死の繰り返しの中で、父母や兄弟という関係にあったのだ」という意味です。
また、奈良時代の僧、行基は「山鳥の ほろほろと鳴く 声聞けば 父かとぞ思い 母かとぞ思う」という歌を詠んでいます。
科学の生命観
次に科学の生命観を紹介しましょう。
・動物
1739年、スコットランドの哲学者、デイヴィッド・ヒュームは次のように語りました。
「動物の外面的な行動が私たちのとる行動と似ていることに鑑み、私たちは、動物の内面も私たちの内面と似ていると判断する。さらに、その原理をもう一歩進めれば、こう結論づけざるをえなくなるだろう。すなわち、互いの内面の動きが似ているということは、それらを引き起こす原因も似ているに違いない、と」
しかし、こうした意見は1980年代後半まで問題にされませんでした。
「あの頃、犬に想像力があるとか、ラットは笑い、ほかのラットの痛みに共感するなどと言ったりすれば、一部の人たちから鼻で笑われて、感傷的で擬人化するきらいがあると非難されるのがおちだった」
「20世紀、野生動物は野菜か何かのように管理されることがごく一般的だった」(ヴァージニア・モレル/科学ジャーナリスト)
「20世紀の全般にわたって、動物に意図や情動があると考えるなど、幼稚で通俗的な愚行と見なされた」
「しかし、今では毎週のように動物の高度な認知に関する新発見がある」(フランス・ドゥ・ヴァール/エモリー大学教授)
「今日では懐疑家は次第に減ってきており、『動物は情動を備えているかどうか』という議論はいまだに続いてはいるものの、問いの中心は『動物の情動は、なぜ現在の形態へと進化したのか』というものへと変わりつつある」(マーク・ベコフ/コロラド大学名誉教授)
2012年、神経生理学者などの著名な科学者たちは、「すべての哺乳類や鳥類および、タコなどの他の多くの生物が、意識を生み出す神経基質を持っている」「ヒトのような大脳皮質がなくても、動物は情動を経験することができる」という「意識に関するケンブリッジ宣言」を発表しました。
哺乳類や鳥類など人間に近い種については常識となっているので、遠い種について見てみます。
・昆虫
ダーウィンは、昆虫でさえ、「怒り、恐怖、嫉妬、愛情を、摩擦音(羽のこすりあわせなど)で表現できるし、嘆きや恐れからきしんだ音を出す」と言いました。
パブロフの犬のような「古典的条件づけ」は昆虫でも起こるといいます。
「昆虫の脳は構造と機能の面で哺乳類の大脳皮質と酷似すると、多くの研究者が考えている。さらに言うと、脳の大きさは、一般に考えられているよりはるかに重要性が低い。コンピュータと同じことが動物にも当てはまる。大きなマシンのほうが優れているとはかぎらないし、大きな脳が、思考や問題解決能力を測る正しい尺度というわけでもないのだ」(ヴァージニア・モレル)
「昆虫は記憶、学習、思考、コミュニケーションを実に様々な予想外の方法で行えることが、次第に明らかになっている」(オリヴァー・サックス/コロンビア大学医科大学院教授)
「昆虫の行動の大部分は遺伝子に刻まれた本能の表現であり、学習によって得ることの多いヒトの行動とは根本的に異なることから、ヒトと昆虫を照らし合わせることに批判的な意見もあるかもしれない。しかし、食欲や性欲はもちろん、突発的な行動や感情に代表されるように、ヒトは普段の行動も多分に本能に支配されているし、生物としての営みは、昆虫のような一見『下等』な生物に共通する部分も非常に多い。この世の中をとりまく問題に対する様々な評価や対処には、われわれヒトを一介の生物であると認識していないがために不自然になっていることが多いように思える」(丸山宗利/九州大学総合研究博物館助教授)
「学習成立の速さ、記憶を生涯にわたって保持する能力、記憶の書換の柔軟性、記憶容量の大きさのどれをとっても、コオロギの匂い学習能力は、ラットやマウスなどの哺乳類の学習能力にひけを取らない。さらにミツバチもコオロギと同等か、あるいはそれをしのぐほどの匂い学習能力をもつ。これらは昆虫が小さな脳しかもたないことを考えると、驚くべきことではないだろうか」(水波誠/北海道大学教授)
東京大学分子細胞生物学研究所は、2017年にキイロショウジョウバエを使った研究で次のように発表しています。
「五感の基本を備えた脳を持つ生物が先カンブリア紀に存在し、その共通の祖先から、私たち哺乳類を含む脊椎動物と昆虫を含む節足動物が分かれてきた可能性が高まりました」
「五感のすべてについて、昆虫脳と哺乳類脳の基本回路構造がほぼ同じであることが明らかになり、両者がばらばらに進化したのではなく、先カンブリア紀の共通の祖先から進化した可能性が高まりました」
「私たちの研究成果は、昆虫と人間が体の仕組みだけでなく脳の仕組みにおいても予想以上に似通っていることを示しています」
・ダンゴムシ
動物行動学者の森山徹(信州大学准教授)は、ダンゴムシにも「心のうつろい」があると言います。
「観察者は、観察対象を未知の状況に遭遇させ、予想外の行動を観察することで、その心の存在を確かめることができる」
「私は、ダンゴムシにおいてその行動を自律的に選択する何者か、『内なるそれ』を実感しました。この『内なるそれ』が、『ダンゴムシの心』なのです」(森山)
・イカ
「イカの脳では脊椎動物と同じく記憶や学習といった高次の機能がきちんと処理される」(池田譲/琉球大学教授)
・魚類
「動物行動学的、神経生物学的な研究によって、魚類は意識、知性、感覚能力を持ち、自分の好みを表現できることを示す説得的なデータが得られている」(マーク・ベコフ)
「あらゆる動物が、バクテリアさえも、人間と同じように経験から学べる」
「魚はチンパンジーや人間と同じくらい打算的になれる。自分の望むものを手に入れるために、仲間を操ったり、ひどい目にあわせたり、だましたり、力を貸したりすることもある」(ヴァージニア・モレル)
大阪市立大学の幸田正典教授の研究グループは、魚類が鏡に映る姿を自分だと認識できることを明らかにしています。
「魚類の記憶力や認知能力は低い(=魚はバカ)と、人は昔から考えてきました。本発見は魚にも自己認識など高度な知性や洞察力があることを示唆しています。我々は魚に対し『大きな勘違い』をしていたのかもしれません。ヒト中心ではなく、魚類を含め脊椎動物の知性を見直すべき時が来ていると思われます」
「高い心的認知能力の一つである自己認知は、ヒトに近縁な動物や脳の大きな『賢い』ほ乳類やカラス類だけができるとされてきました。最近、我々の研究室では、魚類の論理的思考、顔認知に基づく個体識別などを明らかにしています。このほか、相手の考えを理解する能力、さらに共感性といったこれまでは想像もされなかった能力も次々と魚類で明らかにされつつあります。今回の発見が、霊長類、類人猿やヒトのみが賢いとする従来の捉え方を根本から見直すことに繋がれば、と考えています」(幸田正典)
・粘菌
粘菌コンピュータの研究で知られる北海道大学教授の中垣俊之(2008年、2010年イグ・ノーベル賞受賞)の研究も興味深いです。
「一般的にいって、迷路解きは、動物の賢さを評価する標準的な試験としてよく使われますが、まさか単細胞の粘菌がそれを解いてみせることは驚くべきことです」
「驚いたのは、生物の知性といって真っ先に思い浮かぶ『記憶』や『学習』の能力についても、粘菌にその芽生えがあるということです」
「細長いレーンの途中に、粘菌が嫌うキニーネという化学物質を微妙な濃度で置いた時、このキニーネに近づいてきた粘菌は数時間もの間、その前で立ち止まったあと突然に動き出し、乗り越えるか、引き返すか、2つに分裂するかという異なった『ためらい』ともとれる行動を取るのです」
「私たちが『人間らしい』と思うようなこうした振る舞いや『知性』の芽生えともいえるものが何なのか、粘菌という生き物を通じてほんの少しずつ、そこに近づいている感覚があります」
「進化した脳を持つ生物こそが賢いというのは自明のことなのでしょうか。脳を持たない生物に目を向けることで、改めて見えてくるものがある、そう思えてなりません」
・痛み
最近は、魚も痛みを感じるとする研究も増えているようです。
「実験とその結果は、この本のタイトルでもある『魚は痛みを感じるか?』という問いに答えるのに十分な証拠を提供する。そう、魚は痛みを感じるのである」
「依然として魚は『ちがう』とみなされているが、魚についての理解を深めれば深めるほど、私たちは魚に鳥類や哺乳類との多くの類似点を認め、正しい評価を下せるようになるはずだ」(ヴィクトリア・ブレイスウェイト著「魚は痛みを感じるか」より)
「実際に調べてみれば、結果は常識のほうと一致する。針にかかって身をくねらせ、痛がっているように見える魚は、本当に痛がっているのだ。
自分に従属する者たちが苦しみや痛みをあまり感じていない、あるいはまったく感じていないと考えるなら、支配する側にとってこれほど楽なことはない。昔から常にそうだった。罪悪感を抱くことなく、罰せられることもなく、そのものたちを利用し、搾取できるからである。偏見の歴史で目につくのは、下層階級や他の人種の人間は自分たちに比べ鈍感だとする主張。
似たような話をあげるなら、1980年代まで、人間の赤ん坊の手術は麻痺薬だけで行われ、麻酔は使わないのが普通だった。乳児は実は痛みを感じないものと長年信じられていた。確固たる証拠もなしに、赤ん坊の神経組織は未発達なものとされてきたのである。大声で泣きわめくという事実に真っ向から反する考え方で、不思議な科学の伝説としかいいようがない。しかしそれがこれまでの医学の教えであり、誤りが認められたのはつい最近、痛みの治療をしない赤ん坊は手術後の回復に時間がかかることが研究で明らかになってからだった」(ジェフリー・M・マッソン/精神分析学者)
マッコーリー大学のカルム・ブラウンによれば、釣り上げられて呼吸ができない環境に置かれた時の魚のストレスは、溺れている人とまったく同じだといいます。
ちなみに、こういった痛みに関する研究を踏まえ、スイスではロブスターなどの甲殻類を生きたままゆでたり、焼いたりすることは法律違反になっています。
魚が痛みを感じないとする根拠は「魚には大脳新皮質が欠けているから」というものでしたが、類似する機能を果たす領域が哺乳類とまったく異なる場所にありました。
ブレイスウェイトは、ここから下の動物は痛みを感じないといった「そのような境界線が存在するという確たる科学的証拠は得られていない」と言い、次のように語っています。
「動物が異なる様式で世界を経験しているからといって、そのことは、動物にまったく情動が欠け、何らかの形態の苦しみを経験する能力がまったく備わっていないということを意味するわけではない」
「痛みを経験する能力が進化の過程のなかで大きな利点になるのは、ほぼまちがいがない。このようにダーウィン流の思考の道筋をだどってみれば、痛み、あるいはそれに類似する感覚がさまざまな動物のあいだに広く浸透していないことのほうが、実に奇妙だといわざるを得ない」
これまでがそうだったように、これからも痛みを感じるとされる生物が増えるかもしれません。
また、そもそも罪悪という点では痛みを感じないからといって殺したり傷つけたりしても問題ないということにはなりません。痛覚がない無痛症の人たちの寿命が短いように、生存に有利な「痛み」を感じない人や生き物を傷つければ、むしろ罪悪が大きい可能性もあります。
魚にしても虫にしても単細胞生物にしても、捕まえようとすれば逃げますし抵抗します。死にたくないのです。
「すべての生き物は生き抜くために懸命にエサを探し、天敵から必死に身を守る。ミミズやミジンコでさえも危険から逃れ、生き抜こうとする。死にたいと思っているような生き物はいない。すべての生き物は、できることならすこしでも長く生きたいと思っているはずである」(稲垣栄洋/静岡大学農学部教授)
・心はいつからあるか
「地球上に現存する生物は1つの祖先生物の子孫であることは明らかである。『われわれはどこから来たのか、われわれは何者なのか』という問いに生物進化の面から答えると、『私たち地球に生きる70億人の1人1人は、40億年の生命進化を受け継いできた存在』なのであり、『すべての生物は親戚関係にある』ということである」(薄井宏/新潟大学助教授)
「私たちはしばしば、やれ下等生物だ、高等生物だなどと言いますが、原始的な生物が必ずしも下等だというわけではなく、まったく別のライフスタイルや生存戦略でもってやはり巧みに生きているという見方が浸透してきました」(中垣俊之)
「進化論の立場から人の心の起源を考察すればするほど、外界からの情報を分析し次の行動を決めるために心は単細胞動物の時代から存在していたと考える方がすっきりするのだ。心とは最初の細胞が誕生し広い外界に泳ぎだしたその時から始まったと思う」
「心というものが昆虫にも魚にもネコにも存在すること、そして明らかに心も生命の起源以来、動物の体の進化とともに常に進化を重ねてきた」(宮田彬/大分医科大学名誉教授)
「進化論的には、原始的な動物にも『こころ』の原型は見られる。下等な動物でも身体が傷つくような刺激からは逃れるだろう。これは、『いやだ』という感情、つまり嫌悪感の原型と言っていい。そして、餌のような報酬にありつけるという情報があれば、それに向かっていくはずだ。これは『喜び』の原型といえるはずである。このように、大脳皮質がほとんど発達していない下等動物にも『こころ』の原型は見られるのだ」(櫻井武/筑波大学教授)
「粘菌を使って心の研究を行った中垣俊之教授らは、粘菌では『代謝反応系によって脳機能を構成している可能性』があると報告しています。これは驚くべきことです。なぜなら、脳を持たない粘菌でも、脳が行っている情報機能に対応する機能を、代謝反応系で実現しているのですから、ここに心を認める可能性が出てきます。生命科学の発展により、地球上の生命体はすべてDNAを共有する兄弟姉妹だという考え方が受け入れられてきました。さらに、DNAだけでなく、情報機能つまり心も進化的に共有しているということになれば、従来の生命と心を別々に論じてきた議論の仕方は、根本的に見直されることになるのではないでしょうか。
このように見てくると、どうも生命が起源した当初から、生命と心は一体のものとして登場してきたのではないかと思えてきます。脳はなくても、後に脳が効率よく実現することになる機能のごく原初的なものを、粘菌が実現しているのであれば、心は脳がなくても創発されるということになるのではないでしょうか」(立木教夫/麗澤大学経済学部特任教授)
「思考する存在は人間だけかもしれないが、動物のみならず、バクテリアも含めてあらゆる生命は何らかの方法で外界を感じ、そしてそれに反応する主観(主体的意思)を持っているのだと言う主張は、きわめて合理的である。地球上のあらゆる生命が、数十億年を遡る共通の祖先を持つことを考えれば、『私』が持っている主観と同様の何かをすべての生命が持つと考えることは、むしろ自然であろうと思う」(橋元淳一郎/科学評論家)
「われわれのような意識はなくとも一種の潜在する意識、あるいは意識以前の意識といった方がより適切と思われるような原始的意識を想像するということが許されてならないだろうか。われわれの意識の中心がわれわれの生命や行動の中心を代表するのと同じように、これらの生物にあってはこの意識以前の意識、原始的意識の中心が、やはりそれらの生物の生命や行動を中心づけていると想像されはしないだろうか」(今西錦司/京都大学名誉教授)
「私は『細菌から哺乳類まで、あらゆる生物は、主体的な認識を持つという点で共通している。そしてその主体性は、階層を成すようにして進化してきたものだ』という確信を持つに至った」
「意識は、原初の生物体が持っていた感覚世界が、階層をなして成長し発展してきたために、やがて形成されてきたものと考えるべきなのだろう」
「『意識に関するケンブリッジ宣言』は、21世紀の生物学が激しく変化していく潮流の中にあって、新たな重要な一歩を記したものとなった。(中略)ようやく自然科学は日本古来の『一寸の虫にも五分の魂』といった観念に辿り着いたという言い方もできるかもしれない」(実重重実/元農林水産省農村振興局長)
・生命誕生実験
原始地球の環境を再現するというアプローチから生命誕生実験に成功したと主張する川田薫の研究も興味深いです。
ミネラル、生体構成成分、アミノ酸、リゾチームの混合水溶液をシャーレの中に入れるところからです。一連の操作はすべて無菌ボックスの中で行っています。
「初めは透明な水溶液が見えるばかりでほかには何も見えず、生命体といえるものは何ひとつとして存在しませんでした。
ところが観察をはじめて3日後のこと。突然、1ミクロン程度の『もの』が、ポツンと発生したのです!そして、さらに1時間、2時間と時間が経過するにつれ、同じものが2個、3個と発生してきます。この1ミクロンくらいの大きさの『もの』は、完全に静止していました。これは非常に不思議なことでした。無機物だろうが有機物だろうが、このくらいの小さなものであれば、溶液中では必ずブラウン運動をしているはずなのです」
1日半から2日経つと動き出したといいます。
「おかしいなと最初のシャーレをのぞいた私は、驚きました。2個も3個もある1ミクロンくらいの『もの』が、なんとゆっくり動いていたのです。緩慢な振動と回転とでも表現するしかないような動き方で、3~5ミクロン程度の範囲内を動いています」
川田は次のように推論しています。
「実験で発生したのは、微生物状の『体』ができたものであり、その体に『命』、つまりなんらかのエネルギーが入る。静止していたものが動きはじめるための特別な作用とは、この命(エネルギー)の作用だったと考えれば、うまく説明がつく。したがって、このエネルギーが解明できれば、命の本質がわかるということだ」
「このエネルギーの凝集体が生命であり、生体に、生命の本質であるエネルギーが移入されて、初めて生命体となるのではないか。そして、これは直観としかいいようがないが、そのエネルギーは意志と意識をもっている。こう考えなければ、発生した生体がある日突然、固有の動きをはじめることの説明がつかない」
「このように考えると、現在までの生物学の全研究は生体という体の研究であって、今後いかに学問が進もうと生命体の半分しかわからないことになる」
また、死は生命エネルギーの抜けた状態ではないかと推測し、精密天秤を使ってラットの死の前後で体重変化を調べる実験を行ったところ、実際に体重が減少したといいます。
「ラットの体から放散されるものを、すべて容器の中に閉じ込めておくことができましたので、死後減少した分の体重は、純粋に持っていたエネルギーの重さだったと考えるしかありません。つまり、生命エネルギーは重さを持ち、それを測定することが可能であることが証明されたわけです」
そして、体重は一気に減少するのではなく、1300~1400秒ぐらいかけて徐々に減っていったといいます。
生命エネルギーの差などではなくドリフト(温度変化等で試料が動くこと)ではないかと言われるため、さらに別のラットで実験したところ、体重の減少と増加を何度も繰り返し、3500秒ぐらいかけて終わったといいます。
「このグラフを見た私は本当に驚きました。(中略)生命体が死を迎える時、最初の実験では、生命エネルギーはすんなりと生体から離れたのですが、今回は生体に何度か出入りを繰り返しているということになります。当然、このような現象はドリフトではありえません。私はここで、生命エネルギーを獲得することで生体は生命体となり、その生命エネルギーが生体から離れることで生命体ではなくなる、すなわち死を迎える。これが生命体の一連の流れであることを確信しました」
「今の科学、あるいは医学の世界では『死』とは心停止や呼吸停止を指しています。しかし、呼吸停止や心停止しても、生命エネルギー、ここではあえて魂といってもいいかもしれません。魂は、まだ生体から離れていないということです。呼吸停止や心停止は、死ではないということが、この実験では明確になったわけです」
仮説として「生命(エネルギー)はヒモのようなもので体とつながっている」と言い、「ヒモのようなものが切れなければ体外離脱と呼ばれる状態になり、ヒモが切れてしまえば、エネルギーはもう元の体に戻ることができず、生命体は死を迎える」と推測しています。体脱体験している時の体重にも変化があるはずだと著者は予想しているようです。
このラットの実験などを経て、次のように推論しています。
「まず化学反応で物質ができて、それが固有の生き方をしていく上で必要な固有のエネルギーを獲得する。そして、体と獲得したエネルギーが一体不可分になって、初めて生命体になります」
「生体やDNAといった部品ができたとしても、生命の保温室である生命エネルギーが獲得されないかぎり、生命体にはならないということを確信した」
「この生命エネルギーは、意志と意識をもって個体に宿っています。いつ、どんな個体に宿るのか、どのように生きるか、そしていつ個体か離れるのかは、それぞれの生命エネルギーが決めることだと考えています」
「生命エネルギーがどの個体に宿り、どのくらいその個体にとどまっているかを、生命エネルギー自身の意志で決定したものが寿命といえるでしょう。(中略)重病で死を迎えたり、生まれてすぐに死んでしまうのも、すべて生命エネルギーに刷り込み済みのことなのです。逆に生まれてくる時のことを考えても同じです。自分はなぜ生まれたのかという問いに、ほとんどの方は両親の計らいで生まれたと答えると思いますが、そうしてできたのは生体であり、その生体を生命エネルギーが意志をもって選び、宿ったというのが本当のところなのです」
また、生体が先にできて後から生命エネルギーが入って来ることから自分で生体を選んだ、つまり自分で親を選んだと推論しています。
さらに、生きる意味について次のようにも推論しています。
「生命エネルギーには死という概念はないと述べてきましたが、そのエネルギーは、100年ほどの人間という生体にたった1度入るだけとはかぎらない。さまざまな生体を選んで出たり入ったりを繰り返していてもおかしくはありません。輪廻転生とはまさにそのことを指しているといえるでしょう」
「では、いったい、どのような意志と意識をもって生命体となったのでしょうか。これを人間に置き換えると、人はなぜ、なんのために生きるのか、という問いに他なりません。この根源的な問いかけは、太古の昔から多くの人々が生命誕生を探求してきた本当の理由であるといっても過言ではありません」
「なぜ、どんな意志と意識をもって、生命というのは、わざわざ生体を選び、苦労の多い生命体になるのでしょうか。この問いへの答えを私は、人間が自らの魂のゆがみを取るためだと考えています」
「両親の計らいで体を得て、自分の意志で魂といわれるエネルギーを体に入れ、生まれてきて、いろいろな経験を経ることで魂のゆがみを修正し、そして体から離れてもとのエネルギーの世界へ帰っていく・・・・。これが私たち人間の人生であり、魂のゆがみを修正することがその目的なのです」
「輪廻を繰り返して、今ここにたしかに自分はいるのですが、輪廻を繰り返すたびにいろいろな体験をしていて、それはすべて潜在意識、すなわち蔵識にストックされています」
・生命エネルギー
1990年代後半、サンクトペテルブルク大学のコンスタンティン・コロトコフ教授は、生きている人間が放出する気体と死後何時間もの間に放出される気体にはほとんど差がないことを突き止めたといいます。
死後数十時間が経つとまったく異なる光りのパターンの放出が始まり、彼にはその変化が死の本質を映し出しているかのように見えました。ゆっくり時間をかけて死ぬ人は光りもゆっくりと消え、壮絶な最後を迎える人は光りも突然変化し、人間の身体につながれていた魂が最後に離れていくエネルギー変化の構造のプロセスだと考えるに至っています。
「生命エネルギー」という概念は、仏教でいう業や阿頼耶識と類似点がありますが、この概念を使って次のような分析をする人もいます。
「生命エネルギーという概念が判るのが胎児の変化です。単細胞生物から人類までの30億年をたった300日で成し遂げる。計算すれば簡単に判ることです。胎児の1日は1000万年に相当します。では、”1日で1000万年もの進化”を可能にするエネルギーとは何でしょう。母体の1日2500キロカロリーなどといった栄養成分のみでは、そんな大それた変化は絶対に起こしえない。その正体こそ”宇宙エネルギー”なのです。宇宙エネルギーが、臍の緒を通して胎児に送り込まれる。つまり、母親は”胎生”という形で子宮を貸しているにすぎないのです」(森下敬一/グルジア国立医科大学名誉教授等)
「脳内物質は、1年たつと原子レベルではほぼ入れ替わっているのに、実際には、私たちの意識はほとんど変わりません。脳の中の原子の配列が、『心』を生み出すという考えには、ちょっと無理がありそうです」
「生きているからだはばらばらになりません。つまりからだは崩壊せずに、秩序を保って存在しています。しかも自由に動かしたり、成長したり、心が生まれたりしています。物理学からみると、このような物質の働きは『奇跡』としか言いようがありません。わかりやすく言えば、地面の土が勝手に動き出して、100階建てのビルがひとりでにできあがるようなものなのです。なぜこんな奇跡的なことが起きるのでしょう。生死の境で、『何か』が失われるのではないでしょうか。ノーベル物理学賞を受賞したシュレディンガーが、これに注目しました。このような秩序のないばらばらの状態から秩序があるものの形成を『マイナスのエントロピー』と呼び、生命のメカニズムとして提案したのです」
「マイナスのエントロピーは『生命エネルギー』に対応すると考えます。さらには意識(エネルギー)が関わっているのかもしれません。(中略)この生命エネルギーがばらばらの原子をとりまとめているのです。この生命エネルギーがあるからこそ、私たちは生きていられるのです」(奥健夫)
「科学者は『タンパク質から偶然に生命ができた・・・・』と主張する。しかし、偶然にできた生命体ならその生命が尽きると、そこで終焉していたはずだ。しかし、実際は人類まで、脈々と生命を継いできた。それは『生命体(物質)』は『神の意志(spirit)』が、注入されてつくられたからだ。『神』というと、反感をもつ人がいるだろうが、要するに『無』から『有』、つまり『空』から『色』をつくるエネルギー(気、霊、スピリット・・・・)を『神』『somethinggreat=何か偉大なもの』と定義すると、異論はあるまい。無神論者の生命の起源も、30億年前の単細胞生物なのだから」(石原結實/医師)
生物学者の福岡伸一は、生物だけが時間経過と環境に伴って自分自身を変化させながら維持しており、その根底にある原理が動的平衡であると解釈しました。
また、シュレーディンガーも論じたように、生物はエントロピー増大の法則(自然のままにほったらかしにすると、秩序ある状態から無秩序の状態へ変化するという法則)に反し秩序を保っています。
こういった力の動力源が業であり阿頼耶識であると仏教では説くのでしょう。
フランスの研究者ルネ・ペオックは次のような実験を行いました。
乱数発生装置によって運動が決定されるロボット、つまりデタラメな動きをするロボットを用意します。
産まれたてのヒヨコに、このロボットを見せたところ、ヒヨコはロボットの後を追いました。ヒヨコは最初に出会った物体に対して強い愛着心を抱き、その後をつきまといます(刷り込みと呼ばれる)。
次に、このヒヨコを籠に入れてロボットの後を追えないようにしました(籠の中からロボットは見える)。するとロボットはヒヨコに近づいてきました。
さらに刷り込ませなかったヒヨコに変えて同じように実験してみると、ロボットはデタラメに運動したままでした。
また、ウサギを使った次の実験も行っています。
ウサギを檻に入れ、このロボットが見えるところに置いたところ、ウサギはロボットを怖がりました。するとロボットは遠ざかっていきました。
しかし、数週間にわたって毎日ロボットを見せたところウサギは怖がらなくなりました。するとロボットは近づいてきました。
生物学者のルパート・シェルドレイク(ケンブリッジ大学フェロー)は、この実験から次のように推測しています。
「動物の願望ないし恐怖が離れたところの無作為現象に影響を及ぼして、ロボットを引き寄せたり追い払ったりしたわけである。動物の願望や恐怖が脳の内部に閉じ込められていては、こんな芸当ができないのは明らかだ。彼らの意図は脳の外に出てこの機械の挙動に影響を及ぼしたはずである」
シェルドレイクは、偶然説や嗅覚説等々を検討した結果、一部の動物にもテレパシーや予知といった超能力があると言います。
たとえば、別の部屋に隔離した仔犬に危害を加えようとすると母犬の身もすくんだり、遠い場所にいる飼い主に危害を加えようとすると犬の心拍数があがるといった事例が彼の著書で紹介されています。親子関係といった結びつきが何もないと、何の反応も示さなかったといいます。
「動物のテレパシーに関する科学的な研究は端緒についたばかりである。研究が進めば、テレパシーは超常的なもの、常軌を逸したものというより、自然なものとみなされるようになるだろう。社会集団ないし社会コミュニケーションの生物学における1つの様態なのである。それは、集団の仲間同士が感覚コミュニケーションの及ばない範囲にあっても影響し合うことを可能にする、その生存にとってきわめて重要なものであるのかもしれない。そうであるとすれば、テレパシー通信の能力は自然選択を受けてきたに違いない。進化してきたのである。その根源は、進化の歴史の奥深く、最も初期の社会性動物のあいだに存在するのかもしれない」(シェルドレイク)
ちなみに、福来によれば、福来記憶説は「下等動物」にもあてはまるといいます。
また、生まれ変わり事例の中には、少ないながらも過去生が動物だったものもあるようです(犬につけた徴と一致する母斑を持って生まれた子など)。
・まとめ
以上、科学の生命観について簡単に紹介しました。
「悟り」の章で説明する内容も考慮すると、次のようなことがいえるのではないでしょうか。
「地球にはさまざまな生物がいる。そしてそれらはすべて、最初に誕生したものの直系の子孫だとされている。ということは、今いるヒトもクラゲも大腸菌も大いに違う生物だが、それぞれの祖先をたどっていくと共通の祖先生物にたどりつけるということである。(中略)今いる生物たちは、血がつながっており、『われら生物、皆、親戚』と考えざるを得ない」(本川達雄/東京工業大学名誉教授)
「万類共尊の仏教思想は、今や最先端の量子論や生物学の知見とも一致することが明らかにされるようになってきた」
「従来の生物学は生物間の違い(その特殊性)を明らかにすることに重点をおいてきたが、新しい生物学は『万類共通』の普遍性を明らかにすることで生命の本質を明らかにしようと、その方向を転換しつつある。この方向は、いずれは『万類共尊』の新しい思想を、仏教思想とは別の面で追究することになるものと考えられる」
「人間が、人間の生命の価値のみを他のいかなる生物の生命の価値よりも高く、かつ尊いとするのは、人間の手前勝手な価値観であり、他の生物からすれば甚だ迷惑であり、かつ許しがたいことである」
「キリスト教では、動植物のランクは人間よりも低く最低である。ゆえに、キリスト教徒の欧米人にとっては、人間の生命と他の生物の生命とが同じ価値であることは到底認めがたいであろう。これに対し仏教では、人間をも含めてあらゆる生物の生命は、すべて等しく、かつ尊いとの『万類共尊』の思想があり、ために仏教徒の東洋人にとっては、人間生命と他の万類生命との『等価性』は西洋人よりははるかに受け入れやすいであろう」(岸根卓郎)