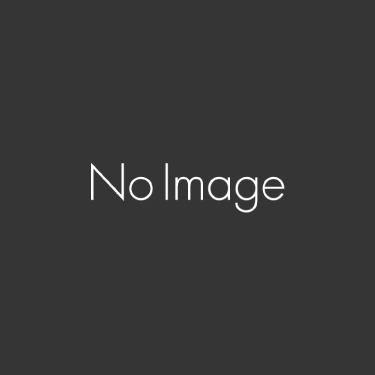「戦争は常に人間の最悪の部分を引き出す。平和な時ならあいつも普通の男だ」(映画『シンドラーのリスト』より)
「米軍史上最多、160人を射殺した、ひとりの優しい父親」(映画『アメリカン・スナイパー』より)
平時は良き父であり良き母であった人が、戦時となれば罪悪感を感じることなく多くの人を殺すようになります。
ニューヨーク生まれのアフリカ系アメリカ人、アレン・ネルソンは、海兵隊員としてベトナム戦争の前線でベトコンと呼ばれる反政府軍のゲリラ兵たちを敵に戦ったという人です。その体験を著書「『ネルソンさん、あなたは人を殺しましたか?』 ベトナム帰還兵が語る『ほんとうの戦争』」に綴っているので、簡単に紹介します。
まず、戦争体験を子供たちに語るようになっても真実は語らなかったという話をしています。
「私は、統計学者か評論家のような、おおざっぱな数や、ピントのぼやけたイメージを使って、綺麗ごとばかりを語り続けました。それは相手が子供たちだからであり、本当の戦争の話、つまり、ベトコン兵の死体がバラバラになっていたり、敵の死者数を調べるためにそのバラバラになった首や腕や足や胴体を集めたりするような話は、とうてい彼らにはたえられないだろうし、すべきではないと思ったからでした」
しかし、1人の少女から「あなたは、人を殺しましたか?」と「運命的な質問」をされてから真実を語ろうとしたといいます。その時の衝撃についてアレンは、「誰かにおなかをなぐられたような感じがしました。私の体はこわばり、重くなり、教室の床にめりこんでいくような気がしました」と語ります。
海兵隊での訓練をしていくにつれ、徐々に罪悪感が薄れていったという話からしています。
「ライフル銃の扱い方と撃ち方。手榴弾の投げ方。爆発物の取り扱い方。また、素手でいかにして敵を殺すかも学びます。私たちが学ぶものはすべて人を殺すための方法であり、その目的は人を殺すことをなんとも思わない心をつくりあげることです」
「そんな日々の繰り返しの中で、私たちは人を殺すことへのためらいや、罪の意識を少しずつ失っていきました」
また、飛行機で戦場へ旅立つ時の心境について「今度の戦争は善だ」と思っていたことや、死の恐怖がなかったことなどを語っています。
「ヒーローになるための旅が始まったのだと、私は思いました。多くのベトナム人は共産主義者に支配されて自由も人権もなく、アメリカに助けを求めている。だから、わたしたちが戦って彼らを救わなければならない。そのように教えられていましたから、いよいよ、ヒーローとしての仕事が始まるのだと、胸を高鳴らせていたのです。死の恐れなどみじんもありませんでした」
ベトナムに到着するとすぐに、アメリカ兵の死体が入ったボディーバッグを目にし、アレンは衝撃を受けますが、「自分はそのアメリカ兵とは違う」と思っていたといいます。
「まったく予期していなかっただけに、その光景は衝撃的でした。しかし、わたしがボディーバッグに入ることがあるだろうとはまったく考えませんでした。わたしはこう思ったのです。彼らはドジをふんだのだ。間抜けだったのだ。だから生きのびられなかったのだ。だが、わたしは違う。わたしはけっしてヘマはしない。わたしは強い海兵隊員なんだから、と」
初めて銃撃戦に巻き込まれた時についても、「すぐに戦闘に加わりたいと思いましたし、うしろの分隊の連中は撃ち合いができて、なんてラッキーなやつらなんだと思っていました」と言います。
そんなアレンですが、味方の死体を見て「恐怖にこおりつきました」と言います。
「私が見たのは顔がない顔でした。目も鼻もない、ただ真っ赤につぶれた顔でした。銃弾によって顔が吹き飛ばされていたのです。私ははじかれるようにして立ち上がりました。ブーツの上に彼のわれた頭から脳みそがこぼれ落ちました。それは濃いピンク色をした、しわのある大きな卵の黄身のようでした。
衝撃のあまり、筋肉から血液まで、体中のありとあらゆるものが硬くひきつり、わたしは呆然と立ち尽くしました。その間も、すぐそばを弾丸が飛びかっていましたが、恐怖と衝撃が私から思考をすっかり奪い去っていました」
そして、この時から「わたしはすっかり変わってしまいました」と言います。
「私はふるえていました。はげしくふるえていました。そのおそろしさの中から、にくしみに似た感情がわき上がってきました。みんな殺してやる。自分があんな目にあう前に、みんな殺してやる。わたしの心はそうさけんでいました」
そして、アレンは初めて人を殺す体験をします。
「私は人を撃ったのでした。あまりの簡単さと、あっけなさに、ひどく驚きました。こちら側で指を少し動かしただけで、彼方で人がたおれたのでした」
その後は殺戮の連続だったといいます。
「女性や子供たちを数多く殺害しました。これは戦争です。戦争では安全な人間などひとりもいないのです。女性だろうが、子供だろうが、年寄りだろうが、戦闘にまきこまれれば死ぬであろうし、わたしたちに刃向かえば殺されるのは当たり前のことだと思っていました。それが、ベトナムの人々にとっては、たった1つの家族とたった1つの命をかけた絶望的なものであったとしても、わたしたちにとってはありふれた戦闘のひとつでしかありませんでした」
そのうち、ジャングルに隠れているベトコンをおびき寄せるために、ある残虐な方法を用いるようになったといいます。その方法とは、村に残っている女性や子供、老人を殺すことです。
「これは彼らにとって、家族を失うと同時に、食糧などの支援も失うことを意味しました。わたしたちは村人の死体、つまり女性や子供や老人たちのむごたらしい死体を、かくれている男たちによく見えるように、村の入り口に並べます。男たちは家族を皆殺しにされたことを知ると、ようやくみずからすがたをあらわし、わたしたちと真正面から戦うようになるのでした」
また、「死体がただの物に見えた」とも語っています。
「頭がない死体もめずらしくありません。そんなときは頭をさがさなければなりません。頭を運ぶときは髪の毛をつかんで、ぶら下げて運ぶのですが、あるとき、髪の毛が焼け落ちてつかむところがない頭が落ちていました。私は、棒切れを拾うとそれを死体の耳の穴につっこんで持ち上げ、運びました。戦場では、そんなふうに、死体に対して何も感じないようになるのです」
「死者への冒瀆だとか、そんな観念は戦場では通用しません。ただのモノとして、わたしたちは死体を集め、積み上げ、勘定するのです。死が1個、死が2個、死が3個、死が4個・・・と」
「子供たちは死んだ母親の腕や足にしがみつき、泣き叫びます。その泣き声は、家々が燃え盛る炎の音とともにジャングル中にひびきわたってゆきます。わかい女性が、その子供にかけ寄り、死体から子供を引き離そうとしますが、子供は力をふりしぼって母親の死体にだきつき、けっして離れようとしないのです。
一方で老婆たちは死体の山の中に家族をさがします。そして、身内がみな殺されてしまったことを知ると、老婆は地面につっぷし、子供のように泣きじゃくるのです。こんなことが、何度も何度もくりかえされたのです。
そして、その光景が目の前で何度くりかえされようと、わたしたちの感情は少しも動かされることがなく、ただただ無関心でした。わたしたちの部隊だけでなく、他の多くのアメリカ軍の部隊が出撃したすべての村で、似たようなことが数知れずおきたはずです。そして、そんな残虐で無慈悲な死体の山を背に、子供たちや老婆の泣き叫ぶ声がひびくなか、兵士たちはベトコンの耳を切り取ったり、基地にもどったら売り払うための金歯をさがすことに余念がないのです。それが戦場でした。それが戦争でした」
帰還する時には、旅立つ前の心境とは一変し、「わたしは殺すのも、殺されるのも、もうたくさんだと思いました。一刻も早く、戦場から離れたいと、心の底から願いました」と語ります。そして、帰還後は、戦地と平和な日常とのギャップに苦しんでいます。
「アメリカに帰り、ニューヨークの実家にいたときのことです。わたしには自分たちが平和に食事している間にもベトナムでは戦いが続き、人が死んでいるのだということを家族が想像すらできないことに、ひどくいらだっていました」
「わたしには、ベトナムのことなどすっかり忘れて、平穏な日々が繰り返される社会はひどくまちがっているように感じられたのです」
帰還後は悪夢にも苦しんでいます。
「金色の炎に包まれて燃え上がるベトナムの村。断末魔のさけび。われた頭から飛び出す脳みそ。ちぎれた腕。子供たちの恐怖に満ちた顔、顔、顔。そして死んでも死んでも生き返って私を追うベトコン兵・・・。夜ごと眠りにつくたびに、心は地獄をさまよい、おぞましい光景に、はりさけんばかりのさけびをあげ、その自分の悲鳴におどろいて目を覚ますのでした」
アレンの母は、戦争前とは別人のようになってしまった息子を恐れて部屋に閉じ込め、やがて家から追い出したといいます。
「無理もありませんでした。毎晩、私は悪夢にうなされ、跳ね上がるようにして起き、あぶら汗をうかべ、けだもののような顔でせまい家の中を歩き回るのですから」
悪夢から目覚めた直後に妻をベトコンだと思い込み、羽交い絞めにして殴ろうとしたこともあったといいます。
このような体験をしたアレンは、いかに戦争が残虐な行為であるかを訴えています。
「戦争の本質は、今も昔も変わりません。本当の戦争は無慈悲で残虐でおろかで、そして無意味です」
「戦争から生まれ出るのは新たな戦争でしかなく、戦争から平和が生まれることなどけっしてありえないのだと気づいてもらうことです。前線で実際に戦った者で戦争を賛美する者はひとりもいません。もし、戦争を経験していてもなお、戦争を肯定する者がいたとしたら、その人は後方の基地でデスクに向かっていたか、炊事班でコックをしていたかで、人が殺しあう前線に行ったことがない人にちがいありません」
しかし、それでもアレンは、「怒り」の感情が出ることに苦しんでいるといい、たとえば弱者が虐げられる姿を見ると、「あいつらを殺したい」と思うといいます。
「こんな私はどうしたらいいのだ。人には非暴力を説き、自分自身もたくさんの人を殺して、そのことに死ぬほど苦しんできた。にもかかわらず、まだ私の中から暴力が消えていない。こんな私はどうしたらいいのだ」
以上、簡単に紹介しましたが、アレンは「普通の人」であり、戦時となれば多くの人がアレンと同じような心理状態となっています。
「自分が三等軍曹に向かって、『こいつらは、探している男たちではありません』と言う。すると三等軍曹は『心配するな。どのみち何かしでかしていたさ』と言いました。
そうしているあいだ、目の前では母親が泣きながら自分の足元に接吻しようとする。自分はアラビア語はわかりませんが、人間の言葉はわかります。母親は『どうかお願いします。なぜ息子を連れて行くのですか。この子たちは何もしていません』と言っていました。自分をとても無力に感じました。第八二空挺師団歩兵連隊に所属して、アパッチ攻撃ヘリコプターもブラッドレー戦闘車も防護服もM-4ライフルも手にしていた。でも自分は無力でした。その母親を救うには無力でした。戦争では人間性が失われます。振り返ってみると、自分自身が身を置いていたところはまるで異世界です。
ある日、車でバグダードあたりを走っているとき、道端に死体を見つけました。死体を確保するために車を脇に寄せ、憲兵が来て男の死体に対処するのを待っていた。男は明らかに殺されていました。すると仲間たちが車から降り、おきまりの満面の笑顔で死んだ男と一緒に写真を撮り始めた。そして聞きました。
『おい、バイジェス、おまえもこいつと写真を撮るかい』
『いいや』と答えました。そう言ったのは、その行為が倒錯的だからでも倫理の基準に反しているからでもありません。断ったのは自分の殺しではなかったからです。自分が殺してもいないのに戦利品を得るわけにはいかない。それがあのときの思考状態でした。その男が死んでいることにうろたえてさえいなかった。自分でやってもいないことを手柄にするものじゃないと考えていた。しかし、それが戦争です。それが戦争なんです」(「冬の兵士 イラク・アフガン帰還米兵が語る戦場の真実」より)
スタンフォード大学の心理学者、フィリップ・ジンバーゴは、「そのような条件の下では、正常で、高い倫理観を持ち、理想主義者でさえある人も破壊的な残虐行為をするようになる」と言います。
縁がくれば誰でも罪悪感を感じることなく人を殺し、そして、後になって「なぜあんなことをしていたのか」と異常な精神状態だったことを懺悔するのです。
沖縄戦での「集団自決」で肉親を手に掛けた上原進助さん(87)は、「米軍に捕まったら天皇陛下に恥をかかせることになるから、自分の始末は自分でするべきだと大人から教えられた。あのときの教育は本当に愚かだった」と振り返っています。