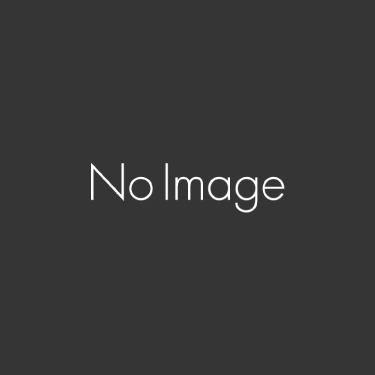煩悩とは
煩悩とは、書いて字の如く人間を煩わせ悩ませる心です。煩悩は、一般的には108あるといわれますが、これは満数といって無限を意味します。ちなみに、除夜の鐘を108回叩くのは、この煩悩の数からきています。「今年は煩わされた一年だったが、来年は煩わされないように」という願いを込めて叩くわけです。もちろん、叩いたぐらいで何ともなるものではありません。
三毒
煩悩の中で特に強いものが3つあり、三毒の煩悩といわれます。
貪欲:欲を貪るように求める心
瞋恚:怒りの心
愚痴:因果の法則といった真理に無知な心
六大煩悩
三毒の煩悩に次の3つを加えたものが、六大煩悩とされます。
疑:物事や人を疑う心
慢:自惚れる心
悪見:物事や人の悪い面を見ようとする心
他にもありますが、この6つの煩悩が根本煩悩であり、他の煩悩は6大煩悩に伴って起こります。
煩悩は闘うもの
煩悩は付き合うものではなく闘うものです。死の解決をした後は煩悩が邪魔になりませんが、信前は煩悩が邪魔になるため闘う必要があります。闘っても消すことはできませんが、信前でも多少はコントロールできるようになり、惑わされにくくなります。四弘誓願には「煩悩無数誓願断」とあり、これは簡単に言えば、「規則正しい生活をする」という誓いです。
煩悩は消せない
どんなに努力しても、生きている限り煩悩は消えません。人間は、煩悩に目鼻をつけたような存在であるため、煩悩具足の凡夫ともいわれます。
「無明煩悩しげくして 塵数のごとく遍満す」(正像末和讃)
(訳:煩悩は塵のように全身に広く満ち溢れている)
「凡夫というは、無明煩悩われらが身にみちみちて、欲も多く、怒り、腹だち、そねみ、ねたむ心多く、ひまなくして臨終の一念に至るまで止どまらず、消えず、絶えず」(一念多念文意)
(訳:凡夫というのは、煩悩が身に満ち溢れ、欲も多く、怒り、腹立ち、嫉み、妬む心が多く、常に絶え間なく、完全に命が終わる一念に至るまで止まらず、消えず、絶えない)
「悲しきかな、愚禿鸞、愛欲の広海に沈没し、名利の太山に迷惑して、定聚の数に入ることを喜ばず、真証の証に近づくことを快しまず。恥ずべし、傷むべし」(教行信証)
(訳:何と悲しいことだろうか。この愚かな親鸞は、愛欲の広い海に沈み切っており、山のように大きな名誉欲や利益欲に迷い惑っており、真実の幸福が欲しいと思う心が微塵もない。何と恥ずべきことであり、傷ましいことであろうか)
どうしたら煩悩から解放されるか
煩悩は消すことができません。では、どうしたら煩悩に苦しめられないようになるのか、その方法に2通りあります。
生きている限り煩悩は消えないわけですから、自殺するという方法があります。しかし、死後は地獄であり、もっと激しい苦がやってくるため、「飛んで火にいる夏の虫」で、この方法は間違いです。
もう1つの方法が煩悩を楽に変えるという方法であり、これが正解です。ある年少の修行者が、「これがあるばかりに修行ができない」と思い、男根を切ろうとしました。その心を見抜いた釈迦は、「男根を断っても色欲はなくならない。煩悩があるがままで救われる法を求めよ」と諭したといいます。いつの時代も、肉体の1部を切除すれば苦しみから解放されると考える人はいますが、その努力は徒労に帰します。煩悩を消さずに救われる道を求める必要があります。
煩悩即菩提
死の解決をしても、煩悩は減りもしなければ増えもしません。
死の解決は、正確には苦が無くなるのではなく、煩悩(苦)が即、菩提(楽)に転じ変わる境地です。「即」は同時即ともいい、時も隔てず、場所も隔てず、時間の極まりを意味します。煩悩があるがまま菩提となる境地であり、苦しんだまんまが喜びという世界です。たとえば、ナイフが刺されば痛みを感じますが、それが障りとならないため、結果として痛みが無いのと等しいということです。
・煩悩が出るほど喜びとなる
煩悩即菩提の境地となれば、煩悩が喜びのもととなります。信前は煩悩によって苦しめられますが、信後は煩悩が障りとならず、煩悩が出るほど喜びも増えるのです。
「罪障功徳の体となる 氷と水の如くにて 氷多きに水多し 障り多きに徳多し」(高僧和讃)
(訳:罪や障りが喜びのもとになる。氷が多ければ水も多いように、障りが多ければ喜びも多い)
「渋柿の 渋がそのまま 甘みかな」という古歌があります。柿は、渋みがそのまま甘みへと転じ、渋みが多いほど甘みも多くなります。同じように、死の解決の境地は苦が楽に転じ、苦が多いほど楽も多くなります。渋柿のたとえでは、渋みが甘みに転じるまでに時間がかかりますが、この境地は即であり時間がかかりません。
苦しみが多いほど楽しみもまた多いことは説明しました。
このように人間は苦が楽に転じ変わることを誰でも体験しています。この境地は一時的で不完全な境地ですが、死の解決をした煩悩即菩提の境地は完全です。
・苦が欲しいということではない
苦が多いほど楽が多いからといって、積極的に苦が欲しくなるということではありません。たとえば、ナイフで自傷しようと思うかというとそうではないのです。苦が無くても最上の幸せです。
・苦も楽も無い
もっと言えば、苦でも楽でもどちらでもいいという境地であり、苦や楽といった概念さえ無い世界です。
「無苦・無楽をすなわち大楽と名づく。涅槃の性は無苦・無楽なり。このゆえに名づけて大楽とす」(教行信証)
(訳:苦も楽も無いことを大楽という。涅槃には苦も楽も無いので、涅槃を大楽という)
無常の幸福は、有無同然であり有っても無くても苦しみですが、この境地は有っても無くても幸せという、まったく逆の意味の有無同然に変わります。「何にも無かったなー」と言って喜べる世界です。
・数珠
数珠は、多くの小さい珠が一本の糸でつながれていますが、これは死の解決をして煩悩が整えられた状態を表しています。小さい珠は、煩悩の数である108個が正式なものですが、それだと長く重くなって邪魔になるため簡略化されています。
・肉食妻帯
「肉を食い妻を持つ」ということですが、肉食妻帯といえば親鸞、親鸞といえば肉食妻帯というぐらい、親鸞を語る上で有名な話です。
当時の仏教界では、性を破ることは最も罵倒されるようなことであり、殺人よりも重い罪とされていましたが、それを親鸞は破りました。実際は皆隠れてやっており、「せぬは仏、かくすは上人」といわれていたのですが、親鸞は公然とやったため激しく非難されたのです。なぜ公然とやったのかというと、煩悩にまみれた情けない人間、悪を造る情けない人間でも救われる道があるということを示すためです。
・涅槃
涅槃とは、サンスクリット語のニルヴァーナに漢字をあてたもので、中国語で入滅、日本語では「煩悩が吹き消された安らぎの世界」を意味し、仏の死をいいます。
涅槃には2種類あります。1つは「有為の涅槃」で、これは煩悩があり常楽我浄の徳が備わっていません。有為は有漏ともいい、煩悩が漏れ出た状態をいいます。もう1つは「無為の涅槃」で、これは煩悩がなく常楽我浄の徳が備わっています。
釈迦は35歳で仏の悟りを開いて有為の涅槃に入り、80歳で入滅するまでの45年間を有為の仏として生き、その後、無為の涅槃に入ったということです。
・死の解決をしても迷うことがある
救われても煩悩があるので迷うことがあります。
たとえば、苦しんでいる人を見たり聞いたりした時に、すぐにその場に助けに行って、食物や金といった名利を与えたくなるという具合です。なぜこのような行為が迷い心かというと、最高の利他が開顕であるということを知っているにもかかわらず、それ以下の利他である名利を与えようとしているからです。これは利他心が強すぎるあまり、迷い心が生じた例といえます。
親鸞にも、浄土三部経を1000回読もうとし、途中で誤りに気づいてやめたというエピソードが伝わっています。経典を読誦しても人を救えないことは当然知っていたはずですが、当時の仏教界では常識だったので、伝統的な因習に惹かれてしまったのです。
他にも、死者供養の気持ちがあるなど、迷い心は死の解決をしてもあるのです。