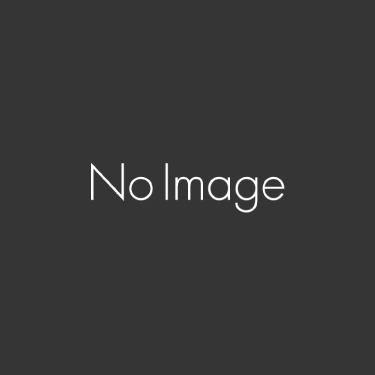諸行無常
仏教には諸行無常という言葉があります。一切のもの(諸行)は続かない(無常)という意味です。
鴨長明の方丈記の冒頭には次のようにあります。
「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。よどみに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし。世の中にある人とすみかと、またかくのごとし」
哲学には「同じ川は2度入れない」という言葉もあります。
物理学でも関連する法則に、熱力学第2法則(いわゆるエントロピー増大の法則)があります。自然のままにほったらかしにすると、秩序ある状態から無秩序の状態へ変化するという法則です。他の物理法則同様、なぜこの法則が成り立つのかはわかっていません。
・無常の幸福
人間にとって何より重要なのは、幸せが無常であるということです。今日あっても明日どうなるかわからない幸せなのです。こちらで詳しく説明しています。
・死
無常の最たるものが死ですので、仏教では無常といった場合、特に死を指します。死についてはこちらで詳しく説明しています。
無常の速さ
人生は凄まじいスピードで進んでおり、あっという間に終わってしまいます。それがわかる表現をいくつか紹介します。
無常を直視する
臭い物に蓋をするのではなく、無常を直視しなければなりません。釈迦は死人や病人を見て反省する材料としました。修行本起経には、釈迦が出家する大きな動機となった有名な四門出遊の話があります。
寂しさには2種類ある
寂しくて修行する人も多いですが、寂しさといっても、大きく2つあります。つまり、「幸福が手に入らない寂しさ」と「幸福が手に入る寂しさ」です。
前者の寂しさは生活苦であり、仏教で説く無常観とは違います。
後者の寂しさが人間苦であり、仏教が説く無常観です。その例として、先に、鬼塚勝也や芥川龍之介などを紹介しました。現代では「実存的な孤独やうつ」などといわれるのかもしれません。
「仏教の聖者たちの呈したノイローゼ様症候群は、主体的精神次元の世界における、現存在を超越せんとして発した実存的苦悶であります。これに反し凡人の陥るノイローゼは、客観的次元の世界における平均値より下降して、そこにもがく苦悩であって、まったく質を異にするものであります」(岸本鎌一/精神科医/名古屋大学名誉教授/「人間回復の道―仏教と精神医学」より)
心理学者のクラーク・ムスターカスは、「この世に生まれ、激しく生き、ひとりで死んでゆくことの本質にある孤独が、実存的孤独である」と言いました。
無常観には強弱がある
また無常観といっても、強弱があります。
たとえば、寂しいとか虚しいといった無常観はまだ弱く、もっと強くなれば恐怖を感じるようになります。死が自分に迫っていることがわかれば、寂しさではなく恐怖を感じます。
平生元気がいい時に観じる無常は、ほとんどの場合、弱い無常観です。そのため、死を解決したいとまでは思わなかったり、求道を始めても途中で脱線したりしてしまいます。
今日、優れた仏教者と評される人でも、無常がわかっていない時期がありました。
「往生要集」で有名な源信がまだ若い頃、出家していた姉の願西尼を訪ねたことがありました。その時、願西尼はいつになく容(かたち)を改めて、源信に「無常とは何か」と問いました。すぐに源信は「花に嵐、月にむら雲」と答えました。それを聞いた願西尼はひどく落胆し、次の歌を書いて示しました。
「出づる息 入る息待たぬ 世の中を 君はのどかに ながめつるかな」
無常とは、散りゆく花や、雲に隠れる月といったものではなく、あなた自身が死ぬことをいうのですよ、という戒めの歌です。これに大きな衝撃を受けた源信は、その後、死を見つめることに専念したといいます。
この時の源信の無常観は文学的な無常であり、のどかな無常です。死が他人事になっています。
・四馬の譬喩
無常に驚く人を4通りの馬にたとえた、「四馬の譬喩」があります。
1.鞭影を見て驚く馬
例:火葬場の煙や花が散るのを見て無常に驚く人
2.鞭、毛に触れて驚く馬
例:知らない人の葬式や霊柩車を見て無常に驚く人
3.鞭、肉に当たって驚く馬
例:親戚や知人の死を見て無常に驚く人
4.鞭、骨にこたえて驚く馬
例:肉親の死を見て無常に驚く人
先に説明した通り、人間はどんな状況に追い込まれても、無常を無常と思えません。鞭が肉を裂き、骨を砕いても本性は少しも驚くことができません。四馬の譬喩のどれにも当てはまらない駄馬の中の駄馬なのです。
無常観の目的は、この無常を無常と思わない屍のような心を白日の下に引きずり出し、驚くことにあります。無常を無常と思わない心に驚くのです。
・「死が怖い」はまだまだ弱い
「死が怖い」という人も多いですが、それはまだまだ弱い死の恐怖です。ですので、もっと死を問い詰め、本物の強い死の恐怖を知る必要があります。
浄土真宗本願寺派祐光寺の住職、野々村智剣は次のように言っていました。
「仏教の原理にしたがう限り、いま現在、あなたの来世は、すでに決まっている。地獄行きの自覚すらないあなたなら、確実に地獄におちる。その理由は、ほかでもない。あなたは日常に、地獄行きの罪を重ねつつあるからである。仏教の道理は因果応報である。悪いタネを播けば、悪い実がなる」
しかし、彼が命にかかわる重い病気にかかった時のことです。
「そのとき私は、大きな恐怖を抱いた。1つは死の恐怖、そしてもう1つは『地獄』の世界そのものに対する恐怖であった。健康なとき、地獄はこんなに恐ろしいところだと得意気に話、それを文章にしていた私は、病をきっかけに、私自身がおちなければならない地獄の恐怖について、熱心に筆を走らせていたのだということに気づかされた。実際に地獄の門口に立たされていたのである」
「すさまじい責苦の地獄におちねばならぬ『罪』の実感がありすぎるために、他人事ではなく、筆者自身の戦慄だったといってよい」
どんなに死後は地獄だと知り、死は怖いものだと思い、人に説教する立場であっても、実際の死はまったくわかっていないのです。
江戸中期の禅僧、白隠は死後の地獄が問題になり、それがきっかけとなって仏門へと入りました。
しかし彼は、一生涯、聖道門の修行をして終わったことから、それほど強い無常観ではなかったことがわかります。強い無常を観じれば自力仏教では消せないことがわかるからです。聖道門や自力仏教についてこちらで詳しく説明しています。
・無常観を極めるとどうなるか
無常観が問い詰まるにつれ、寂しさから恐怖となり、最後は黒闇(無明)となります。一水四見の記事でも説明した通り「色」というのは自己のフィルターを通して見えるものですので、深層の自己であり不変の心理であり苦悩の根源である無明の色、つまり黒闇がこの世の本当の色ともいえます。
先に事例も紹介したように臨終に無明が見えますが、臨終では遅いので、平生元気がいい時に無明を引きずり出す必要があります。
・生きながら死ぬ
死は大きく「肉体の死」と「心の死」に分けられます。
一般的にいわれる死というのは、心と肉体の両方が同時に死にますが、死の解決は肉体は生きたまま心が死ぬ体験です。
「平生のとき善知識の言葉の下に、帰命の一念を発得せば、そのときをもって娑婆のおわり、臨終とおもうべし」(執持鈔)
(訳:生きている時に死の解決をすれば、その瞬間が心の臨終である)
つまり、ほとんどの人は臨終が1回ですが、死の解決をした人は臨終が2回あることになります。
二河白道の譬喩でいえば、三定死の境地です。
・死の恐怖を感じるように生命は進化している
死の恐怖は、死後が地獄であることを警告するシグナルといえます。死の恐怖を直視し、中に入り込んでくるよう自然は望んでいるのでしょう。
「本当に人間は死ぬために生まれてきたのだ。それは人間の運命である。それが運命であるなら、人間は泰然自若として平気で死ぬようにできていてもよさそうなものであるのに、実はそうではない。人間は死を怖れる」
「真理は、人生存在の意義は死によって消滅することである。人間の智識が進むにつれて、否応なしにこの怖ろしき真理と直接対面せねばならぬ。こう考えてみると、生命の進化が無意味になってくる。人間が進化すれば、その智識が進むにきまっている。智識が進めば、死の意味を知らざりしものが、それを知るようになり、その結果、死の恐怖が高まり、生をあじわうことがますます深刻となってくる。生命の進化は人間を不幸に導くということになる」(福来友吉)
「自然は、老いや死への恐怖をある意味を持って人間に投げかけているにちがいない。その恐怖は、それから逃れるためのものではなく、その恐怖の中に入り込んでくることを望んでいるはずなのだ。
というのは、その不安定な幸福の中で、必ず、我々は、心の奥深いところに何かある、もっと心を満たしてくれる何かがあることを感じとっているからだ。その感じがあるから、刹那的な快楽の後から、どうしようもない空虚感が襲ってくる。そして、その空虚感が、我々に、何かもっと本質的に心を満たすことのできるものを求めさせようとしているのである。
でも、我々は、その空虚な心をどうにかして満たしたい、死に対する恐怖からどうにかして逃れたいと思いつつも、どうすることもできないものだと始めから諦め、再び刹那的な快楽の中に落ち入ってしまうのである」
「死の恐怖は、悠久なる生命の存在を知らしめようとしている。死を意識させることによって、その死の恐怖を生み出している暗黒の世界に明かりを灯させようとしているのである。
そして、その暗黒の世界に明かりを灯そうとする営みこそ、動物的快楽から離れ、崇高なる心の在処を求めようとする動きでもある」
「我々を動物的欲求の渦の中から目覚めさせ、さらに進化を遂げさせようとする働きこそ、死への恐怖であり、内から聞こえてくる『人生いかに生きるべきか』という命題でもある」(望月清文)
そして、この命題に対する答えは、「自ら生と死を直視し、自らの心の奥に入って行くことの中から生まれてくるものである」と言い、この命題に答えを見つけたいという欲求こそ、「人間だけに与えられた人間的欲求であり、その欲求こそ精神的進化の目指す方向でもある。それは動物的欲求に満ち溢れた火宅に開かれた狭き門であり、闇の彼方に輝く一点の光でもある」と言います。
死の恐怖を感じるというのも人間の優れた能力の1つです。
たとえば、年を取ると様々な能力が衰えますが、死の恐怖を感じる能力も衰えるのではないでしょうか。そのことが、年齢が上がるにつれて「死は怖くない」と思う人が増える一因となっているのではないでしょうか。
死の恐怖は、死を解決するようケツを叩いてくれる有り難いものであるのに、これまで説明してきたように、人間は向き合い方がわからないから臭い物だとしか思えず蓋をしてしまいます。
死の恐怖を感じないことを誇り、死に怯えている人を笑う人は多いですが大きな間違いです。
映画「甘い生活」では、「僕は平和が怖い。何よりも怖い。地獄を隠しているような気がしてね」というセリフが出てきますが、このように普段の日常に恐怖を感じるのが正常で、日常に恐怖を感じないのが異常なのです。
死を直視する幸せ
死を直視し、無常を問い詰めることは苦しいことだけではありません。様々な現世利益(現在世での幸福)もあります。
一例を挙げます。
・真剣になる
生命の危機に直面している人は真剣になります。適当に生きてきた人も、死を目の前にすれば真面目に人生を考えざるを得ません。
巣鴨拘置所の教誨師としてA級、B級、C級戦犯の多くを世話した花山信勝によれば、最初はいい加減に説法を聞いていた人たちが、死刑の執行が近づくにつれ、次第に緊張して真剣に聞くようになったといいます。
「最初は未決の人たちが多く、服装もまちまちで、中にはどてらを着た人もあった。下駄をガラガラ引きずって、話しながら入ってきた人もあれば、寄席にでも出かける気持ちの人もあったように見受けられた。
しかし、それが回数を重ねるとともに、次第に緊張して、真剣に法話を聞こう、という気持ちに進む人が多くなったのは、うれしいことであった」
「二階の仏間は窓が一方だけにしかなく、風も通らない。蒸し風呂にでも入っているような熱苦の中で、夏服をもちあわせていない老将軍たちは、冬の軍服や、モーニングを着て、出て来られたのである」
「1時間の勤行と法話の間身動き1つせず、謹厳そのものの姿で、真剣に聞いて下さったことを、いまもなお忘れることができない。顔からは、汗がダラダラと流れ落ちるのが、よく見えた。しかし扇子もつかわず、ハンカチでぬぐおうともしなかった。人生一大事の『死』の前には、そんなことは、問題でなくなっていたのである。私も、自然、その真剣さに引きずられて、ポタリポタリと顔から汗を流しながら、ぬぐうこともせず、法話をつづけたのである」
・生の喜び
肉体・家族・財産etc.大切なものを永遠に失った後の心理が、失う前にわかってくれば感謝が生まれ、喜びが生まれます。
「終末について考える人々は、とても健康的に行動するので、むしろ長生きするようだ。また、自尊心が高まることも証明されている」(エリック・バーカー著「残酷すぎる成功法則」より)
「末期がんを宣告されたがん患者が、風に揺れる一本の雑草を見て感動する、という話があるけれど、人は生まれながらの死刑囚なんだから、誰もが、そういう眼を持てるはずなんだよね」(ビートたけし)
「死に直面し、そして一時的にその執行を猶予されたことにより、あらゆるものがこの上なく貴く、神聖で、美しいものに感じられ、私はすべてを愛し、抱擁し、それらに圧倒されたいという衝動をかつてないほど強く感じている。見慣れた川がこんなに美しく見えたことはなかった」(アブラハム・マズロー/心理学者)
阪神大震災で生き埋めになった安楽徹さんは、「地震に殺されそうになったからこそ、一日一日を大切に生きるようになった。幸せを感じるようになった」と言います。
死を直視することは苦しいことですが、苦に立ち向かうことは心身の健康につながります。冷水に入れると身が締まるように、苦は人間を鍛え、結果として楽も多くなります。
「苦難が神経の抵抗力をつけ健康を促進させる」
「逆境こそが強靭な精神、肉体を創る」
「この原則の存在を忘れてしまった人々は、肉体と精神の退化という代償を支払わねばならない」(アレクシス・カレル/1912年ノーベル生理学・医学賞受賞)
目の前に近づいてくるヘビに対して、勇気をもって近づくと決めた時の脳活動を計測した実験もあり、結果は、怖さを感じながらも身体の緊張は低下したといいます。
・人間関係が上手くいく
「1人暮らしをして、初めて1人じゃないことがわかった」というフレーズが出てくる不動産会社のCMもありましたが、人間関係は距離感が大切です。近すぎると客観的に見れなくなり、衝突しやすくなったり様々な問題が生じます。
死は距離感の最たるものです。ですので、死んだ後に、嫌いだった人を好きになるというのはよくあることです。
映画評論家の淀川長治は、小さい頃から父を憎み続けていたそうですが、死んだ後に「いいおやじだったな」と思ったと言い、「生きているときには見えなかった長所に、急に気づくこともあります」と語っています。
しかし、死んでから気づいても手遅れです。無常観を問い詰めることで距離感が生まれ、長所に気づきやすくなり、人間関係も上手くいきやすくなります。
・足るを知る
仏教には「足るを知る」という言葉があります。
・正しく恐怖する
無常を観じるということは正しく恐怖するということです。正しく恐怖を感じれば、たとえば危険を回避できます。
私は毎日乗っていた自転車を止めました。一度便利に慣れてしまうと、痛い目を見ない限り止めることは難しいものですが、その前に止めることができました。なぜできたかというと、簡単に言えば私の無常観です。止めた直後は不便でしたが、今では徒歩が当たり前の生活となったので不便とも思いません。同じ理由で車の免許も持っていませんが、一生取ることはないでしょう。乗らなければ、少なくとも交通事故の加害者になることはありません。
・正しい目的が必要
他にも死を直視する様々なメリットがあります。そのため、死を見つめることの大切さを強調している人は少なくありません。
「死への絶望なしに生への愛はありえない」(アルベール・カミュ/小説家)
「僕が死を考えるのは、死ぬためじゃない。生きるためなんだ」(アンドレ・マルロー/政治家)
「人は、いつか必ず死ぬということを思い知らなければ、生きているということを実感することもできない」(ハイデッガー/哲学者)
「明日死ぬかのように生きろ。永劫永らえるかのように学べ」(マハトマ・ガンジー/政治家)
「私は毎日鏡の前で問いかけている。もし今日が人生最後の日であるとしたら、今日予定されていることを本当にやろうとするだろうか。その答えが『ノー』である日が続くたび、私は何かを変える必要に迫られた。死と隣り合わせであると自覚しておくことは、人生を左右する決断をする際の最も重要なツールだ」(スティーブ・ジョブズ)
「今死ぬと 思うに過ぎし 宝なし 心にしめて 常に忘るな」という古歌もあります。
「100日後に死ぬワニ」の著者、きくちゆうきは次のように語っています。
「『いつか死ぬ』。生きているということはいつか死ぬということ。自分の『終わり』や周りの人の『終わり』、それを意識すると、行動や生き方がより良い方向にいくのではないか。ワニを通してそれらを考えるきっかけにでもなればいいなと思っています」
寺の掲示板に「お前も死ぬぞ」と掲げられたことが話題になったことがありました。寺の住職は、「人生の真実のあり方を端的に教えるのが仏教。死をひとごとに思いがちだが、死は誰にも平等に訪れる。そのことに目覚めることで、命や生き方を見つめ直してもらえれば」と語ります。
このように多くの人が死を見つめる大切さを訴えます。
しかし、ここで重要なことは、「死を直視する幸せ」も無常の幸福にすぎないということです。第2巻でも詳しく説明しましたが、大前提として正しい人生の目的を知っている必要があります。
世間の人は、死を直視して真剣になったところで何をするかというと、結局、無常の幸福しか知らないため、今までより真剣に無常の幸福を求めて人生が終わります。人生の目的がわからなければ意味がなく、せっかくの死の恐怖も手段として活かすことができません。死を直視する目的、無常観の目的は死の解決のためであり自己を知るためです。無常の幸福を求めるために死を見つめるのではないのです。死の解決という目的を知って初めて、死を直視することが活きます。
不幸を勝縁にする
勝縁とは、すぐれた良い縁のことですが、一切の不幸(幸もですが)を死の解決のための勝縁とすべきです。
・家族が死んで
私も家族の死を経験していますので、今や体験的にも仏教が真実であると言うことができます。人生は悲しみや苦しみしかないこと、大切なものは失った時の苦しみも激しいこと、死んだことが信じられないこと、「あんなことをしなければよかった」と罪悪感を感じたこと、「もっとああしてやればよかった」と後悔したこと、早く死後の地獄から救ってあげたいと思ったこと、家族の死にさえ悲しみ続けることができないこと、次は自分が死ぬ番だという死の恐怖を感じたこと、死を自分事として受け止め続けられないことetc.こういったことが体験的にわかりました。
・記録する
時間が経つにつれ、体験時の記憶が捻じ曲がっていくため、体験して感じたことや理解したことをすぐに記録しておくべきです。大切な人が死んだ時など、何度も体験できないことは特にそうです。
・できない人はできない
できる人は不幸であろうと幸せであろうと無常を問い詰めたりする勝縁とできますが、できない人は不幸であろうと幸せであろうとできません。
できる人は花が散るのを見ただけで無常を観じますが、できない人は家族を亡くしても観じません。
わかる人は3歳でも仏教がわかりますが、わからない人は100歳でもわかりません。
「ある時は室家・父子・兄弟・夫婦、一は死し一は生ず。かわるがわる相哀愍す。恩愛思慕して憂念結縛す。心意痛着してたがいに相顧恋す。
日を窮め歳を卒えて解け已むことあることなし。道徳を教語するに心開明ならず。恩好を思想して情欲を離れず。昏曚閉塞して愚惑に覆われたり。深く思い熟ら計らい、心自ら端正にして専精に道を行じて世事を決断すること能わず。すなわち旋り、おわりに至る。年寿終わり尽きぬれば道を得ること能わず。奈何とすべきことなし」(大無量寿経)
(訳:ある時は、親子・兄弟・夫婦などの中で、一方が死んで一方が残されることになる。そうなると、互いに別れを悲しみ、恋しく思い慕い憂う心に縛られ、心を痛める。
長い年月を経ても相手への思いが消えることはなく、仏法を説いても心を開かず、昔の楽しい思い出に浸ってばかりいて離れることができない。心は暗く塞ぎ込んでしまい、愚かに惑い続ける。深く熟慮し、世間事を捨てて、心を取り乱すことなく一心に求道に向かえばいいのだが、そうすることができない。このように迷っているうちに一生を終えてしまい、命が尽きれば地獄に堕ちてどうすることもできない)
「苦を受くる者は常に憂へ、楽を受くる者は常に著す。苦と云い楽と云い、遠く解脱を離れ、若しは昇若しは沈、輪回に非ずということ無し」(往生要集)
(訳:苦しんでいる人は常に悩んでおり、幸せな人は常に執着している。苦でも楽でも、死の解決から遠く離れており、一喜一憂しても、結局は輪廻するだけである)
・自分の死に泣く
他人の死には同情し涙を流す人は多いですが、自分の死に泣く人は少ないです。いつまでも愛別離苦を引きずっているのも、結局は死が他人事になっているからです。死が自分事になれば、死苦より小さい愛別離苦は消えてしまいます。
激しい無常を観じるような求め方
特に、無常を観じ、菩提心が生じるような求め方が大切です。つまり、幸せの中に寂しさや虚しさを感じるような求め方をすることが大切なのです。
本物の菩提心は、真剣に幸せに向き合わないと生じません。幸せを全力で求めた結果知らされる無常観や無力観、罪悪観といったものが爆発的な求道心につながります。
「魂が成長してくると菩提心が目を覚まして、今まで気がつかなかった人生の無常がまざまざと心眼の前に浮いてくる。生きることの価値が疑われてくる。それは科学によって与えられた、生きることの便宜によって慰められない要求である」(福来友吉)
最終的には「火の中をかき分ける真剣な聴聞」をすることが要求されますが(詳しくは第6巻)、仕事が聴聞になっているのであれば、「火の中をかき分ける真剣な仕事」、恋愛が聴聞になっているのであれば、「火の中をかき分ける真剣な恋愛」をすることが大切ということです。
・無常の幸福の力
別な言い方をすれば、無常の幸福は、自己を知ることへつながる大きな力、絶対の幸福へつながる大きな力を秘めているともいえます。ですので、世間的な無常の幸福だからといって侮ることはできません。「相対的な苦や楽」「相対的な善や悪」を過小評価する人は少なくないので注意が必要です。
平生に解決する
死は確定しているのですから、本当は生まれてすぐにこの事実に驚くべきですが、これまで説明した通り、人間には強力な妄念があるため驚くことが非常に難しくなっています。そのため、ほとんどの人は平生に弱い無常を観じ、臨終に強い本物の無常を観じて一生を終えていきます。
どんなに無常に鈍感な人でも臨終に激しい無常に驚き、強い菩提心が生じます。「全財産を投げうってでも死を解決する方法を知りたい」と願うようになるということであり、仏法の本当の価値を知るということです。
「このたび生死をはなるべき身となりなば、一世の身命を捨てんはものの数なるべきにあらず。身命なほ惜しむべからず。いはんや財宝をや」(持名鈔)
(訳:死の解決をして苦悩の輪廻から解脱することができるならば、一世の短い命を捨てること等ものの数ではなく、惜しくもない。まして財宝を捨てることなど言うまでもない)
しかし、この流れでは遅いので、平生元気がいい時にゾッとするような強い無常を観じなければなりません。仏説譬喩経の旅人のように、すべての人間は絶体絶命の状況にすでに置かれており、それに気づき驚く必要があります。そうすれば自ずと必死の求道ができるようになります。
臨終でわかるより、人生の早い段階で強い無常を観じるというのは幸せなことなのです。
・臨終に期待する求道者
臨終に期待する求道者もいます。死が近づけば労せずして真剣になれると考えているのでしょうが、これはあまりに危険な考えです。臨終は、苦しみが激しくてとても真剣になれるものではなく、時間も短くほとんどは間に合いません。平生元気がいい時に最後まで求め切るべきです。
「もし人いのちをはらんとするときは、百苦身にあつまり、正念みだれやすし。かのとき仏を念ぜんこと、なにのゆゑかすぐれたる功徳あるべきや」(唯信鈔)
(訳:臨終には、ありとあらゆる苦しみが襲いかかってきて、正念は乱れやすい。このような時に阿弥陀仏を念じたとして、どれほどの功徳があるだろうか」
・仏教は若い時にやるもの
勝縁にしようと努めることも大切ですが、人生には勝縁にすることが非常に難しい激しい苦しみがあります。ですので、特に若くて健康な時に求め切るべきです。
・絶対にしなければならない
死の解決をしなければ死後は地獄です。一度地獄に堕ちれば助かる方法はありません。ですので、死の解決は「絶対に」しなければならないものであり、「したほうがいい」とか「できたらいいな」というものではありません。
どんなに苦しくても、どんなに年を取っても、ずってでも這ってでも求めてゴールする必要があります。どんなに真面目な求道者でも、ゴールしなければ意味がありません。
死の解決をして極楽に行く100点の人生となるか、死の解決をせず無間地獄に堕ちる0点の人生となるか、人生は2択です。
激しい無常が吹き荒れており、見ようと思えばいくらでも見ることができます。有名な「見えないゴリラ」の実験のように、見ようと思わないと見えません。
私は東京の池袋周辺に住んで久しいですが、ご存じの通り、池袋は日本有数の繁華街です。すぐそばには病院もあります。そのため、楽しそうに歩く人と苦しみに顔を歪めて担架で運ばれていく人が、同時に目に飛び込んでくることがあります。対照的な光景です。
またある時は、人身事故の現場に遭遇したこともあります。
通勤時間帯だったので、足早に職場や学校に向かう人々の間を、白い袋に入った遺体が運ばれていきます。これも対照的な光景です。
人の苦しみを他人事として受け止め、無常を観じることができなければ、地獄という最悪の結果が待っています。
正法念処経には三天使の話があります。
ある罪人が死んで地獄に堕ちると、獄卒の手で閻魔大王の前に引きずり出されます。そして、恐ろしい形相をした大王は、大地が割れんばかりの怒鳴り声で罪人に問います。
「汝、娑婆にありし時、頭白く、歯落ち、目かすみ、肌ゆるみ、腰まがり、気力衰え、杖にすがって呻きながら歩く老人を見なかったか。これがわしが使わした第1の天使だ。
汝、長年病床にあって、飲食や排泄すら人の助けがないとできず、身心の痛みに呻き苦しむ病人を見なかったか。これがわしが使わした第2の天使だ。
汝、棺に納められ、火葬されて煙と消え失せた死人を見なかったか。これがわしが使わした第3の天使だ。
娑婆で三天使にあいながら、放逸な生活に堕し真剣に求道しなかった。今地獄に堕ちて諸々の苦を受けるのは、父母のせいでもなく、兄弟のせいでもなく、友人のせいでもない、祖先や沙門のせいでもない、他ならぬ汝自身の過ちによるのである」
詰問が終わると大王は獄卒に命じて、血の涙を流して恐れおののく罪人を地獄の猛火の中に容赦なく投げ入れます。
・急いでしなければならない
人間は死と隣り合わせであり、今日死んでもおかしくありません。今日死ねば、今日から地獄が始まるのです。今、幸せの絶頂にいようが、不幸のどん底にいようが関係ありません。ですので、一刻も早く死を解決する必要があります。
「ああ、夢幻にして真にあらず、寿夭保ちがたし、呼吸のあひだ、すなわちこれ来生なり。一たび人身を失ひぬれば、万劫にも復せず。この時悟らざれば、仏、衆生をいかがしたまはん。願わくは深く無常を念じて、いたずらに後悔を貽すことなかれ」(教行信証)
(訳:ああ、この世は夢、幻であって真実ではない。命は保ち難く、吐いた息が吸えなければ死んでしまう。一度死んでしまえば、無間地獄に堕ち、永遠に抜け出すことはできない。生きているうちに死の解決をしなければ、阿弥陀仏でもどうしようもできない。どうか深く無常を問い詰めて、いたずらに後悔しないでほしい)
「一日も片時も、いそぎて信心決定して、今度の往生極楽を一定せよ」(御文)
(訳:一刻も早く急いで死の解決をし、極楽浄土への往生を決定せよ)
「人生死出離の大事なれば、これより急ぐべきはなく、またこれより重きはあらざるべし」(御裁断申明書)
(訳:死の解決ほどの一大事より急ぐべきことはなく、これほど重いことはない)
・必ず後悔する
死の解決ができなければ、血の涙を流して後悔することになります。
「明日も知らぬ命にてこそ候うに、何事を申すも命終わり候わば、いたずらごとにてあるべく候う。命のうちに、不審もとくとくはれられ候わでは、定めて後悔のみにて候わんずるぞ。御心得あるべく候う」(御文)
(訳:明日もわからない無常の命であり、何をしようとも死ねば意味がない。生きている間に死の解決をしなければ、必ず後悔することになる。よくよく心得なければならない)
阿育王譬喩経には、「餓鬼が寒林で屍を打つ」という話があります。
ある日、釈迦が寒林を散歩していると、泣きながら「しゃれこうべ」を打っている餓鬼を見つけました。不思議に思った釈迦が「なぜそんなことをしているのか」と餓鬼に尋ねると、餓鬼は涙で顔をくしゃくしゃにしながらこう言いました。
「私は、前世で人間に生まれておりました。このしゃれこうべは、そのときの頭です。人間界にいたときに、こいつがもっと真剣に仏法を聞いていれば、餓鬼道に堕ちてこんな苦しみを受けずに済んだでしょう。それを思うと悔しくて悔しくて、こいつを打たずにはおれないのです」
この話は、死んで堕ちる餓鬼道について説いたものではなく、人間の臨終の姿を説いています。
・無常を問い詰めるには
では、無常を問い詰めるにはどうしたらいいかというと、一言で言えば「聴聞」ということになります。無常観にしても罪悪観にしても、聴聞以外問い詰めることはできません。