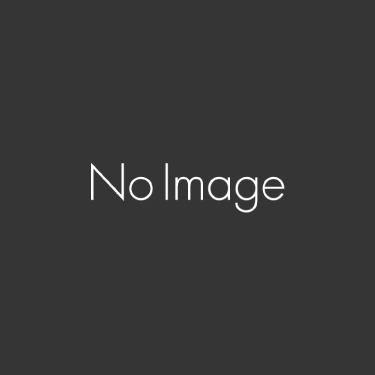聴聞とは、「聴」も「きく」で「聞」も「きく」と書きますが、真実の仏法を聞くことをいいます。
仏法は聴聞に極まる
「仏法は聴聞に極まる」といわれるぐらい、聴聞は重要です。
・聴聞でしかわからない
なぜ、これほど聴聞を重視するのかというと、仏教の一切は聴聞によってのみ理解できるからです。自己にしても、無常や罪悪にしても、死や地獄にしても、聴聞でしか知ることができません。つまり、苦悩の根本解決は聴聞でしかできないのです。
ですので、初めて仏教を聞いた人から「何をしたらいいのか」と聞かれますが、聴聞するよう勧めます。聴聞しないことには何も始まらないのです。仏教は聴聞で始まり、聴聞で終わります。
・目的は心が聞くこと
「聴聞ということは、なにと意得られて候やらん。ただ耳にききたるばかりは、聴聞にてはなく候。そのゆえは、千万の事を耳にきき候とも、信得候わぬはきかぬにてあるべく候。信をえ候わずは、報土往生はかなうまじく候なり」(一宗意得之事)
基本的には仏教を耳から聞くことを聴聞といいますが、これだけではありません。自己を知る行為はすべて聴聞になります。
ですので、経典を読んだり(勤行という)、仏教を人に話したりすること(開顕という)も聴聞になります。
また、後述しますが仕事や恋愛といった世間的な行為も聴聞になり得ます。活かし方次第です。
生活をするままが求道の一部とすることができます。これを「生活即求道」といいます。
・生活即聴聞
仕事をしたり、子育てをしたりと、普通の日常生活がそのまま聴聞のチャンスとなります。たとえば、失恋して爆発的な求道をした場合、失恋が聴聞となったということであり、一生懸命仕事をして自己が知らされたら、その仕事が聴聞になったということです。
・一切は手段
別な言い方をすれば、耳や目、口や鼻といった肉体は、あくまで心に聞かせるためのツール(手段)にすぎないということです。ですので、たとえ耳が聞こえなかったり、目が見えなかったりしても絶望する必要はありません(むしろメリットにさえなり得ます)。生きている限り救われる可能性があるのです。しかし、死ねば心が聞くことができず、救われる可能性がなくなります。
・人による
「自己を知る」「死の解決に近づく」「進歩する」「求道する」「善をする」「聴聞する」、これらはほぼ同義です。
「自己を知る行為」というのは大まかには決まっていますが、厳密には人によります。ある行為が、その人のその時の心理状態によって善にも悪にもなり、聴聞になったりならなかったりします。このあたりについては、これから詳しく説明していきます。
・聴聞は質と量
どんな努力にも言えることですが、聴聞も質と量が大切です。長く聴聞を続けても、真剣に聞かないと大して聴聞になりません。真剣な聴聞をしても、長く聞かないと大して聴聞になりません。
「水滴石を穿つ」という言葉があります。何度も何度もぶつかれば水滴でも石に穴をあけることができるように、真剣な聴聞を繰り返せば、軟弱な心でも無明を破ることができます。
「至りて堅きは石なり。至りて軟らかなるは水なり。水よく石を穿つ。『心源、もし徹しなば、菩提の覚道、何事か成ぜざらん』といえる古き詞あり。いかに不信なりとも、聴聞を心に入れて申さば、御慈悲にて候う間、信を獲べきなり。ただ、仏法は、聴聞に極まることなり」(御一代記聞書)
聴聞は難しい
聴聞は、聞くだけなので簡単なようですが、非常に難しいことです。真理のことを諦といい、真理を明らかに観察することを諦観、真理を明らかに聞くことを諦聴といいますが、様々な力が働き、諦観・諦聴することが難しくなっています。詳しくはこちらを参照ください。
・業に合わせて仏教を聞く
何より怖いのが、業に合わせて仏教を聞いてしまうことです。一水四見であるために、同じ言葉に触れても人によって受け止め方が変わります。自分の業にあわせて聞いてしまい、諦観・諦聴できず、釈迦の意図する通りには聞けないのです。
「仏、一音をもって説法を演説したもうに、衆生、類に随って解を異にする」(維摩経)
(訳:仏が一つの法を説いても、その人の業によって違う解釈をする)
衆生とは生きとし生けるものすべてを指し、もちろん人間も含まれます。
たとえば、一緒に聴聞した人に、どう理解したか後で聞いてみると驚くべき理解をしているということがよくあります。
源信は、自己の姿を「予がごとき頑魯のもの」と言っています。これは、「私のような頑固で愚かなもの」という意味ですが、すべての人間は「頑魯のもの」です。
・早合点
仏教は奥深い教えであるために、早合点してしまう人が多くいます。「群盲、象をなでる」という諺があります。これは次のような意味です。
「大勢の盲人が象の体をなでて、それぞれが自分の触れた部分の印象だけから象について述べたというたとえによる。凡人には大人物や大事業などの全体を見渡すことはできないものだ。元来は、涅槃経・六度経などで、人々が仏の真理を正しく知り得ないことをいったもの」(大辞林)
象の足だけを触った人は、象というのは柱のようなものだと思い、象の鼻だけを触った人は、象というのは太い綱のようなものだと思うという具合です。この話では、盲人たちはしまいには殴り合いのケンカをしてしまいます。
最初は意味がわからなくてもよく、聞き続けることが大切です。やがて、ところどころですべてがわかるようになります。
・「私」を捨てる努力
このように、内側からも外側からも様々な力が働き、諦観・諦聴することを妨げています。ですので、意識的に諦観・諦聴できるよう努力していく必要があります。
「研究結果から明らかになったのは、あなたが悟りを求めているなら、自分の通常のものの考え方や現実の体験の仕方を積極的に阻害することで、自ら意図的に悟りを求めていかなければならないということだ」(アンドリュー・ニューバーグ)
仏教を聞く時は「私」を入れてはなりません。「己を虚しゅうして聞く」などともいわれます。
「聖教は句面の如く心得べし、その上にて師伝・口業はあるべきなり、私にして会釈すること然るべからざることなり」(御一代記聞書)
(訳:聖教は一字一句加減せず、その文面に書かれている通りに頂くべきである。その上で、先生の言葉を頂くべきである。自分勝手な解釈をすることは決してあってはならない)
「親鸞におきては、『ただ念仏して、弥陀にたすけられまいらすべし』と、よきひとの仰せを被りて、信ずるほかに別の子細なきなり」(歎異抄)
(訳:この私は、「ただ聴聞して阿弥陀仏に救われるのである」という善知識の言葉を信じているだけであり、別の何かがあるわけではないのだ)
善知識とは仏教の正しい先生という意味です。
・自分で気づくしかない
真実の自己に気づかせるために仏教では様々な教えが説かれていますが、最終的には、自分で気づくしかありません。
ガリレオは「人を教えることはできない、ただ自悟させる手助けをするにすぎない」と言いましたが、自分で自分の欠点に気づいて自分で良くしていくしかないのです。
有名な「見えないゴリラ」と呼ばれる実験のように、気づけば必ず驚き、「なぜ、こんな当たり前のことに気づかなかったのだろう」と不思議に思うはずです。
行学
行動して学ぶことを行学といいますが、座学よりも行学のほうが重要です。座学だけで聴聞となり自己を知ることができるのであれば、それに越したことはないのですが、大抵の人は座学だけでは頭だけの理解になってしまいます。行学でないと聴聞にならず、自己はとてもわかるものではないのです。
聴と聞
求道は、聴聞の一本道ですが、聴聞は、正確には「聴」と「聞」に分けられます。
・聴とは
「聴」は、「自分から出て聴く」ということであり、法座で善知識の説法を聴くことを指します。ですので、正確には「聴聞に行ってくる」ではなく「聴に行ってくる」というのが正しいのです。
・聞とは
「聞」は、「向こうから聞こえてくる」ということであり、阿弥陀仏の呼び声を聞くことを指します。「南無阿弥陀仏」の六字の名号を賜り、阿頼耶識に阿弥陀仏の呼び声を聞信させることをいい、これを「聞即信の一念の体験」ともいいます。
「かの仏の名号を聞くことを得て、歓喜踊躍し、乃至一念すること有らん。当に知るべし」(大無量寿経)
感覚器官を介さずにコミュニケーションが取れる可能性があることは超心理でもみました。阿弥陀仏の声は声なき声です。
・名号を聞くことを勧める
このため、釈迦は名号を聞くことを勧めています。
「阿弥陀仏を説くを聞きて名号を執持せよ」(阿弥陀経)
(訳:六字の名号を聞き、その名号を心に留めよ)
「汝好くこの語を持て。この語を持てとは、すなわちこれ無量寿仏の名を持てとなり」(観無量寿経)
(訳:よくこの言葉を心に留めなさい。この言葉を心に留めるとは、つまり阿弥陀仏の名号を心に留めるということである)
・意識から阿頼耶識へ
阿頼耶識は、人間の最も深い深層心理であるため、いきなり聞かせることはできません。ですので、まずは浅い心である意識(頭)から入って「聴」を繰り返し、最終的には深い心である阿頼耶識(腹底)に「聞」と聞かせるという流れを辿る必要があります。電波が流れても周波数が合わなければテレビやラジオが流れないように、「聴」を繰り返すことで阿弥陀仏が流す念力を受け取れるように心を調整し、周波数が合った瞬間に「聞」と聞くことができます。
ですので正確には、仏教は「聴」で始まり「聞」で終わるということになります。
どのくらい真剣な聴聞をすればいいのか
聴聞といっても真剣に聞けば大きな宿善となりますが、真剣に聞かなければ大した宿善にはなりません。もっと言えば、真剣に求めること自体が聴聞になり宿善になります。
たとえば、山本良助の場合、必死で善知識を求めること自体が聴聞になっていたといえます。彼を導いた庄松は教授の善知識とはいえません。
東条英機についても同じことがいえます。死刑が間近に迫り、真剣に求めたこと自体が聴聞になっていたといえます。東条に仏教を教えた人は花山信勝という人で、私も彼の著書や講演(録音)を聞きましたが、「あの話で東条はよく死の解決ができたな」と思えるような内容です。生きた教授の善知識に遇えなかったにもかかわらず求め切ることができたのは、必死だったからでしょう。
「真剣」というのは、これほど重要なことですが、どれくらい真剣に聞けばいいのか、それがわかる表現をいくつか挙げます。
真剣に聞くというのは難しいことです。そのため、針を刺して聞いたり、昔から求道者は真剣になるために血のにじむ努力をしていたのです。稲盛和夫は、「絶え間ない創意工夫が、すばらしい成果を生む」と言っていますが、何をしたら真剣になれるのか、常に考えるべきです。